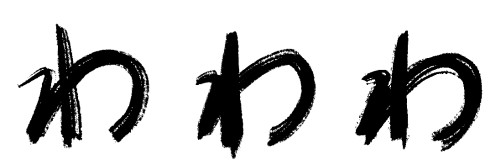夜中に何度も起きた気がする。それに死ぬほど夢も見た気がする。思考が霞み、意識をはっきりと保てない。
大切な夢だったような。覚えていなきゃ、と思ったような。風船のようにふわふわと不安定な思考は、枕元の目覚まし時計のアラーム音によってパチンと弾けた。
ハインツは呻き声をあげながらアラームを止め、二、三回寝返りをしてからゆっくりと起き上がった。時計を眺めると、時刻の下に表示されている日付けが目に入った。
「ハインツ、起きた?」
母親のアリスがノックもせずにドアを開けた。おもむろに電気をつけるので、ハインツは思わず顔をしかめる。
「朝ごはんちゃんと食べなよ」
そう言うと、パタパタとリビングへ戻っていった。
『——最近では街頭演説が多く行われており、それに感化された人々がポケモンを逃し、町中で行き場を失ったポケモンたちがゴミを荒らすなどの問題が——』
ハインツが着替えを済ませてリビングに向かうと、ニュースキャスターの声が真っ先に耳に入った。父親のビルがコーヒーを飲みながらニュースを見ている。カラクサタウンの郊外にある工場の警備員として働くビルは、職場で制服に着替えるというのにオフィスで働くサラリーマンのようにワイシャツとスラックスを身につけていた。
「おはよう、ハインツ。今日からだっけ」
「おはよ、そう今日から」
ビルの正面に座ると、ハインツは用意してある朝食に手を伸ばした。
「せっかくこれから楽しい旅が始まるっていうのに、いやなニュース流さないでよ」
キッチンに居たアリスがリビングまでやってきて、テーブルの上に置いてあるリモコンを操作しようとするとビルがそれを止めた。
「今日こそこういうニュースを見るべきなんだよ」
ハインツ、と父親の呼ぶ声に、思わず顔を上げた。
「ポケモンと暮らすのは当たり前だけど、でも決して楽なことじゃない。ポケモンだって生きているし、性格の相性だってある」
テレビには、捨てられたポケモンたちが保護されている様子が映し出されている。愛玩用のポケモンならまだしも、バトル用に育成されたポケモンを保護するのは骨が折れるようだ。
「その大変さを、しっかり感じてくるんだ。つらくなったら、大人たちに頼りなさい。途中でやめてもいいんだから」
平日は朝くらいしか会わない父と、こうして話すのは久しぶりだとハインツは思った。普段からあまり顔を合わせていないというのに、なんだかひと月会えないのが寂しく思えた。
「一ヶ月頑張っても、途中で挫折しても、きっと今回の経験はハインツにとって大切なものになると思うよ。めんどくさがったり、適当にやらない限りね」
そう言って微笑むと、ビルはまたテレビに視線を戻した。ハインツは朝食を咀嚼しながら、同じようにテレビの方を向いた。
一ヶ月後、一体どんな自分がここに座っているのだろう、そう思いながら。
職場へ向かうビルの車に乗せてもらい、ハインツとアリスはアララギ研究所まで向かった。既に研究所にはチェレンと両親が到着しており、少し遅れてベルと母親が到着した。
「パパったら、前に同意書にサインしてくれたのに今になって旅は危ないんだ、とか言い出してね、思いっきりケンカしてきちゃった」
ハインツとチェレンと合流したベルが、苦笑いを浮かべて言った。
「これからしばらく会えないっていうのに、ずいぶん嫌な別れかたしたね」
チェレンの言葉に何も言い返せないのか、ベルは「そうだよねえ」と言ったきり黙り込んでしまった。
「ハーイ! チェレン、ベル、ハインツ! よく来てくれたわね」
研究所の正面玄関ではなく、裏口から駆け足で出てきたアララギが三人に向けて手を振った。目の前まで駆け寄ると保護者たちに挨拶し、正面玄関まで向かうよう促した。
研究所に入ると、すぐ右手にある会議室に案内された。先日、オリエンテーションで使ったのもこの部屋だった。会議室というより多目的室のようだ。研究所は相変わらず忙しなく、アララギの助手たちが廊下で行き交っていた。
「軽く最終確認をしたあとにポケモンを譲渡します。私と一緒にポケモンの体調チェックを行い、いよいよ旅立ちとなります」
ハインツたち三組の親子が、まるで教室のように横並びに置いてあった椅子に座ると、その正面——いわゆる教壇の位置——にアララギが立って説明し始めた。
ポケモンセンターの使い方や、トレーナーカードの扱い方、どこでどう使えるのかなど、オリエンテーションで学んだことを復習した。何かあったらアララギ博士に連絡すること、連絡しにくいと思ったら家の人でも良い、ポケモン協会公認の施設に駆け込むのでも良い。
「協会に属する人たちは皆あなたたちの味方です。困ったらなんでも言ってちょうだい。ポケモンのことはもちろん、体調が悪いとか、たとえば三人で喧嘩しちゃって人間関係がうまくいかないとか、話すほどのことじゃないって思っても気軽に相談していいのよ」
冷たい言い方になるかもしれないけど、とアララギが少し言い淀んだ。それが協会の人間の義務なのだと。未来ある若者たちの手助けをする責任があるのだと言った。
「あなたたちをサポートするのが私たちの仕事なの。だからもし、そういう人たちから不当な扱いを受けたと感じることがあったら私に言って。私が直接本部に職務を放棄している人が居ると報告します」
協会からの支援で行うこの旅は、多くの人間の努力によって成り立っているんだとハインツは思った。旅を始める前から、既に多くの大人に助けられている。
楽しみな気持ちもたくさんあるが、言い表せない不安も感じていた。数多くの人の努力によって支えられているこの旅を、大人たちが望むように有効活用できるのだろうか。
ハインツの不安を感じ取ったのか、アララギが柔らかく微笑んで口を開いた。
「レポート提出は厳守だけど、それでもどんな旅をするかはあなたたち次第です。例年はジムを目指す子が多いけれど、ほとんど地元から動かずにゆったりとポケモンと過ごすだけの子も居たわ。あなたたちだけの旅を楽しんでちょうだい」
「は〜い! すごく楽しみです!」
ベルの元気な返事を聞いて、ハインツは肩の力が抜けていくのを感じた。
「ハインツ、ベル」
チェレンの声かけに、ふたりが顔を向ける。
「旅を思いっきり楽しもう」
「もちろん!」
ハインツも自然と笑みを浮かべて頷いた。そうだ、どんなことがあっても、ふたりとなら。
「いいねいいね、気合い充分って感じじゃない。じゃあお待ちかねのポケモン譲渡よ」
そう言うと、アララギの助手がモンスターボールを三個持って現れた。ベルは大袈裟に喜んでいるが、僅かに身を乗り出してボールを眺めているチェレンも、興奮を抑えられないようだった。ハインツはというと、未だに実感が湧かず、他人事のようにボールを眺めていた。
「博士! あたしたち、もうどのポケモンにするか決めてあるんですよお!」
「あらそうなの? じゃあ、ポケモンを渡す前にもうひと言だけいいかしら」
アララギはコホンと咳払いすると、旅立つ三人の若者たちの顔を見た。
「あなたたちに譲るポケモンたちは、研究所で育てられたポケモンたちです。でもあなたたちに譲渡した瞬間、データ上ではあなたたちが『親』となります。それはそのポケモンの成育、行動、全ての責任を負う人になる、ということ。それをよく考えて旅をしてください。もちろん、あなたたちに責任を負わせる、ということの責任は……なんかややこしい言い方ね……」
うーん、と悩むアララギにチェレンが助け舟を出した。
「つまり、ポケモントレーナーとしての責任を自覚し遵守して欲しい。その上で何か問題を起こしてしまったら、博士や保護者がその責任を負う、ということですね」
「そういうこと! かっこつかないわね、ハハハ」
ポケモンに適切な餌を与え、適切な休息を取らせ、適切な管理を行うこと。それがトレーナーに課せられた責任である。アララギは繰り返し伝えた。
「堅苦しいことばっか言ったけど、とにかく言いたいのはポケモンを大事にしてね、ってことよ。いいかしら?」
「は〜い!」
ベルの元気な返事が部屋中に響いた。
「チェレンとハインツは?」
アララギに指を差され、二人はビクッと体を振るわせた。
「もちろんです」
慌てて答えるチェレンに合わせてハインツも力強く頷いた。それを見てアララギは力を抜いて微笑み、ハインツの瞳を覗いた。
「ハインツ、あなたは物静かで引っ込み思案だと聞いているわ」
一瞬、ハインツの体が強張った。何かまずいことをしたのではないかと身構えたが、アララギの声は穏やかで、自分を安心させようとしているのがなんとなく分かった。
「それが駄目とは言わない。でも、ポケモンを大事にしてね、という私の言葉には、あなた自身の返事が欲しいの」
「あ……」
自分を主張しなければ、周りから自分を認知されることなくその場に溶け込める。俺は居るのに居ないのだと、そうすれば文句を言われることも、迷惑をかけることも、誰かとぶつかることも無く一日をやり過ごせる。
アララギはハインツの意志を探していた。周りに流されない、ハインツの胸にある想いを。
「はい……ポケモン、大切にします」
頬が熱くなる。自分の気持ちを伝えるのは、こんなに難しかっただろうか。
「ありがとう、その言葉が聞けて本当に嬉しい。私もあなたたちを全力でサポートします」
誰かに助けられること。誰かに守られていること。ハインツは忘れていた感覚を思い出した。
「さあ、三人とも前に出てきて! ポケモンを受け取ってちょうだい」
ハインツはチェレンとベルと共にアララギまで近寄った。そして、事前に相談していた種類のポケモンの入ったモンスターボールをそれぞれ手に取った。
「トレーナーへの第一歩よ。ボールから出してあげてみて」
一度ボールのボタンを押して開閉モードに切り替えてから軽く投げると、中から光を纏いながらポケモンが出てくる。
ポカブ。ハインツが選んだ初めてのポケモン。
鼻筋の黄色の模様にそっと触れ、耳の根元に向けて撫で上げると、ポカブは気持ちよさそうに目を瞑った。さすがほのおタイプと言うべきか、チクチクと固い短い毛を撫でていると人間よりもはるかに高い体温が伝わってくる。
ハインツはアララギの言葉を思い出した。あなた自身の言葉が欲しい、と。俺は今からこのポケモンの親になるんだ。
「よろしく……俺はハインツだ」
その言葉に応えるように、ポカブは楽しげに鳴き声をあげた。
「準備はいい? ハインツ、チェレン!」
親たちに見守られながら研究所を出発した三人は、カノコタウンから一番道路へ行く道で横並びに立っていた。
旅立ちの第一歩は全員で一緒に踏み出したいというベルの願いを叶えることろだった。
「せーの!」
三人は同時に足を前に出し、一番道路を踏みしめた。学校に通うときは毎回通る道も、今日は何故か初めて通る道のように感じられた。
「やったあ! あたしたちの旅の始まりだよ! わくわくするねえ!」
飛び跳ねたり手を振ったり、体いっぱいに喜びを表現するベルを見て、ハインツもチェレンも自然と笑みが溢れた。