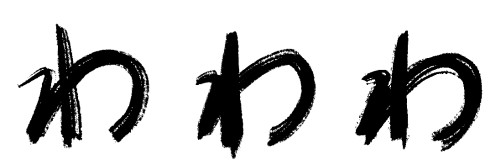響く怒号、金属のぶつかる音、咽せてしまうほどの砂埃。ハインツはそれらを感じ取って目を開けた。
戦場だった。武装したポケモンと人間が傷付け合い斃れていく世界だった。なぜこんなところにいるのか分からないが、今すぐ逃げ出したいはずなのに、まるで足が固定されているかのように動かせない。
「——兄さん」
声のする方に顔を向けると、そこには漆黒の鎧に身を包んだNが無表情で立っていた。
「兄さん」
昨日会ったそのままの顔。服装が違うだけで、同じ姿が目の前にあった。
「兄さんのことが分からない。ボクは獣たちの想いまで知ることができるのに兄さんの想いは全く分からないんだ」
Nの顔をした男は、やはりNと同じように早口で、時間に追われているのではないかと思うほどだった。
おそらくこの男はNなのだろう。しかしどこか確証を得られないような気持ちにさせられるのは、きっとその瞳の冷たさの所為かもしれない。いや、Nも柔らかさや温かさを秘めていたわけではなかったが、目の前の男はN以上に感情が無く、鋭い眼差しをこちらに向けている。
「今感じているものが何なのか分かるか」
自分の口から勝手に言葉が紡ぎ出され、ハインツは僅かに目を見開いた。
「それは恐怖だ。私を恐れているな? 我が弟よ」
ハインツではないハインツの言葉を聞いて、Nと同じ顔をした男はおもむろに顔を歪めた。恐怖、憤慨、それ以外の何かか。ハインツには全く読めなかった。
すると突然、大地を震わすほどの咆哮が辺りに鳴り響いた。
白き竜と黒き竜。巨大な二頭の竜は向かい合う男たちの上空を旋回すると、白き竜はハインツの後ろへ、黒き竜はNの後ろへと降り立った。
「血を分かつ兄弟よ」
ハインツの口が再び勝手に動く。
「恐怖に支配された者が人を導けるとは思えぬ。さあ、剣を持て。どちらが王に相応しいか、決着をつけようではないか」
もはや思い通りになる部位などなかった。腕を持ち上げ、握っていた剣の切先をNに向けた。
なぜ俺はこんなところに居るのだろう。どうして戦っているのだろう。
Nが剣を鞘から抜き、構えたところで目の前が真っ暗になった。
「今日はサンヨウシティに向かうよ」
ポケモンセンター内の小さなレストランで朝食を済ませると、マップを開いたチェレンが目的地を指差した。
「ジムがある最初の町だ。僕は挑戦するつもりだけど二人はどうする?」
「う〜ん考え中……チェレンのを見て決めようかなあ」
「ハインツは?」
チェレンの呼びかけは全く耳に入っておらず、ハインツはぼんやりと虚空を見つめているばかりだった。
「ハインツってば!」
ベルが肩をつんつんと突つくと、ようやく我に返ったようで交互にベルとチェレンを見た。
「あ……ごめん。何?」
「大丈夫?」
「夢見悪くて……」
何か恐ろしい夢を見た気がするのだが、何を見たのかはっきりとは思い出せなかった。ただそれが妙に気になってしまい、どうしても頭から離れてくれなかった。
「サンヨウシティのジムに挑戦するって話をしてたんだ。ベルはまだ決めかねてるみたい。でもどうしようか、ハインツの顔色ちょっと悪いし、無理して今日出立することもないよね」
協会特別認可トレーナーカードがあればこうしてポケモンセンターに泊まれるので、体調面を気にしてその場に留まることもできる。まだ旅は始まったばかりだ。急ぐ必要もないだろう。
それでも、ハインツは気を紛らわせられる環境が欲しかった。
「いや、行こう、サンヨウシティ。俺もジムに挑戦したい」
チェレンの方を向いて、なるべく元気に見えるよう少し声を張って喋った。
「分かった。もしつらくなったらすぐ言ってよ」
「ああ」
カノコタウンからカラクサタウンの間はよく行き来するが、三人にとってサンヨウシティへの道はあまり馴染みのない、ようやく旅に出たのだと実感できる道だった。旅への不安と興奮が一歩を踏み出すごとに増していく。
「明日の夜にはレポート提出しなきゃだね」
ベルが独り言のように呟いた。
ポケモン協会から支援を受けられる代わりに、トレーナーは三日に一度ポケモンの状態や旅の記録をまとめたレポートを提出しなければならない。昨日旅が始まったばかりのハインツたちは、初めてのレポート提出が明日に控えていた。
「チェレンはこういうの得意そうだよねえ」
「まあね、記録をまとめるのは好きだよ」
「あたしは苦手だなあ」
「博士は日記みたいに気楽に書いて良いって言ってたし、テキトーだったり雑に書かなければ良いんじゃない?」
ベルとチェレンの会話を聞きながら、ハインツは昨日のことはどう書くべきなのか悩んでいた。おそらく、初めてやったバトルのことは書くべきだろう。どんな技を出したのか、ポケモンはどういう状態だったのか、反応は早かったか遅かったか、バトルは好きそうか苦手そうか。そして——
「あのさ」
ハインツは、ふと疑問に思ったことを二人に投げかけた。
「プラズマ団のこと、レポートに書いた方がいいんだろうか」
「プラズマ団か……」
チェレンは口元に手を当てて考え込んでしまったが、ベルは胸を張って堂々と発言した。
「あたしは書くよ。プラズマ団のことはいろいろ難しいけど、そのあとに博士から聞いた話はすごく大切だと思ったの」
ポケモンを傍に置くか、野生に放つか、どちらにしても人間たちはポケモンを知ろうとしなくてはいけない。アララギが語った言葉だ。
解放せよと語りかけるプラズマ団。馬鹿馬鹿しいと呆れ返る人たち。不安がる人たち。プラズマ団のことを良いか悪いか言える立場ではないと言う博士。旅に出たばかりの自分たち。ポケモンは自由ではないと言っていたN。誰が正しいのだろう。人は何をすべきなのだろう。
「プラズマ団の演説を聞いて、博士から話聞いて、それであたし自身が感じたことについて書くのは悪くないと思うんだ」
ベルは前を向いて力強く歩いた。
「まだ旅は始まったばかりだもん。いっぱい悩んで、答えが出なくてもぐるぐる考えて、いつか自分なりの答えを出せばいいんじゃないかなあ」
「そうだね。そのための旅だよね」
ベルの言葉にチェレンも大きく頷いた。
「自分の感じたことを素直に書く……単純だけど、それが一番大切なのかもしれない。プラズマ団のことは書いた方がいいんじゃないかな、ハインツ」
「そう、そうだな」
するとベルが突然、そういえばサンヨウシティってご飯が美味しいんだって、と話題を急に変えてきた。いろいろ話したがりのベルはこういうことは珍しくなく、チェレンもハインツもそのまま相槌を打ったりベルに合わせて食事の話をした。そうこう話しているうちにサンヨウシティの町並みが少しずつ見えてきたのに気付く。
「あっ、みてみて二人とも! もうサンヨウシティが見えてきたよ」
ハインツとチェレンを置いて先に走り出したベルがサンヨウシティの地を踏む。
「じゃん! 一番乗り!」
「別に競争してるわけじゃないんだから」
ベルに続いて到着したチェレンが呆れた様子を隠さず言うが、どこか悔しそうにも見えた。ハインツも町の敷地内に足を踏み入れる。家族と数回しか訪れたことのない町を、幼馴染だけでこうして訪れているなんてなんだか不思議で仕方がない。
「まずはポケモンセンターで部屋を取っておこうか。そのあとジムに挑戦しにいこう」
ふらふらとどこかへ行きそうなベルを押さえて、チェレンが声を少し張り上げながら提案する。どこか抜けているベルと、基本的に大雑把で頓着のないハインツをアテにしないぞという気合いが感じられるようだった。
「そうだね! まずポケモンセンターがどこにあるか探さないとだねえ」
「ちょっと待って、今確認するから……」
チェレンが鞄からタウンマップを取り出そうとした瞬間、三人の背後から声がした。
「旅のトレーナーさんかな? ポケモンセンターを探してるの?」
驚いて三人が一斉に振り向くと、買い物帰りなのだろうか、果物類が入った紙袋を抱えた青年が立っていた。ウェイターのようなモノトーンの制服を着ていて、鮮やかな緑色の髪がよく映えた。
「ようこそサンヨウシティへ。ポケモンセンターはこっちだよ、ついてきて」
そう言うと、ハインツたちの返事も待たずにくるりと方向を右に変更して歩き始めた。
「あっ、ま、待ってくださ〜い! チェレン、ハインツ、追っかけよう!」
走り出したベルの後を二人も追いかけた。通りをふたつほど抜けると、すぐにポケモンセンターが見えてきた。
「ポケモンセンターはここだよ。サンヨウシティはあまり大きくないから少し不便だろうけど、のどかでいいところなんだ」
青年の人懐っこい印象を受ける柔らかい笑みに、三人も思わず顔が緩んだ。すると突然、チェレンが「あ!」と声を出す。
「も、もしかして、あなたは……」
何を思い出したのか分からずハインツもベルもチェレンを見て首を傾げるが、当の青年は変わらず微笑んだままだった。
「言い忘れてたね、僕はデント。サンヨウジムのジムリーダーのひとりだよ」
「ええっそうなんですか」
ベルが大袈裟に驚いた。
「どこかで見たことあると思ったわけだ……サンヨウジムはジムリーダーが三人居て、そのうちのひとりがこのデントさんなんだ」
チェレンの説明に、ハインツは軽く「へえ」と返した。
「さっきジムに挑戦するって言ってたよね。予約はしたのかな」
チェレンが恥ずかしそうに眼鏡の位置を直す。
「あ、そういえばしてないですね。すっかり忘れてた」
ジムに挑戦する際はポケモンセンターかジムに直接足を運んで、専用の端末で予約をする必要があると研究所で説明を受けていたのを思い出した。
「もしかして初めてのジムだったりするの? なんだか嬉しいなあ」
デントが三人の顔を順番に眺めながら嬉しそうに笑った。
「ほら、サンヨウシティって田舎の方だからあんまり挑戦者が来てくれないんだよね。だからジムも三日に一度しか開けてないんだよ」
イッシュの中心地であるライモンシティやヒウンシティから遠く離れたこの町は、どうやらあまり人の出入りが無いらしい。デントたちが新米のジムリーダーというのもあって、わざわざサンヨウシティまで足を運ぶトレーナーは少ないようだ。
サンヨウジムは基本的にレストランとして経営しており、三日に一度だけジム挑戦の予約を受け付けている。この頻度でも、あまり予約数は多くないらしい。
「君たち運がよかったね。明日がちょうどその予約を受け付けている日なんだ。よければ予約の仕方も教えてあげるよ」
デントがポケモンセンターの隅にある専用端末を指差すと、チェレンがすかさず頷いた。
「いいんですか。お願いしたいです」
「うん、いいよ。じゃあこっちおいで。三人とも挑戦でいいのかな?」
「あっあたしは……違います、二人だけです」
ベルは二、三歩下がって距離を取り、勢いよく手を振り体全体を使って否定を表していた。そんなベルを見てデントは少しうーんと悩むと、ゆったりとしたトーンで話し始めた。
「どうだろう、君もジムバトルに挑戦してみない? サンヨウジムは三人ジムリーダーが居て、君たちもちょうど三人。三対三のトリプルバトルも面白そうだと思うんだけど」
もちろん無理強いはしないよ、と笑顔で付け足した。
「ジムバトルは挑戦者のバッジ所持数によって難易度を変えていくんだ。みんなはまだひとつも持ってないよね。だから本格的なジムバトルは行わず、最初はポケモンたちと力を合わせる楽しさを知ってもらうスタンスのバトルをするんだよ」
「な、なるほど」
少し引き気味だったベルが身を乗り出してデントの説明を聞いていた。
「三人で旅してるみたいだし、せっかくだから思い出作りをする気持ちで挑戦してみたらどうかな?」
「ええっと……」
眉尻を下げて不安そうにしながらベルはチェレンとハインツの方へ顔を向けた。どうしようという感情がダイレクトに浮かんでいて、ベルには申し訳ないと思いつつも二人は思わず笑ってしまった。
「ベルも一緒に挑戦しようよ」
チェレンはベルの正面まで歩き、肩を軽くぽんぽんと叩いた。
「でもあたし、二人の足引っ張っちゃうかも……あたしの所為で負けちゃったらどうしよう……」
手をぎゅっときつく握りしめ俯くベルを見て、ハインツは無意識のうちにチェレンの横まで歩き出していた。なんだろうと少し顔を上げたベルの瞳がハインツを捉えるが、ハインツ自身何を話すか全く考えていなかったので必死になって言葉を捻り出そうとした。
言葉が出てくる気配が全く無く、沈黙が訪れる。いたたまれない気持ちになってきたハインツは、恥ずかしさか、後悔か、顔がかっと熱くなるのを感じていた。ベルになんと声をかければいいのか。一体自分は何て言いたいのか。時間が経てば経つほど頭はどんどん真っ白になり、逃げ出したい気持ちだけが腹の底から膨れ上がってきた。
「その…………」
ようやく声を絞り出したが、その後が続かず、ハインツはベルよりも深く俯いた。だんだん自分が何をしたかったのか分からなくなってきて、なぜか泣きたくなるような気持ちまで湧いてくる。
「ハインツ」
ベルの声に、ハインツは顔を上げた。
「あたし、二人と一緒にバトルしてもいいかな。うまくいかないかもしれないけど、一緒に頑張ってみたい」
先程の不安そうな表情から一転、完全に不安は拭えていなさそうなものの、姿勢を正し、少し興奮した様子で真っ直ぐハインツを見つめていた。ハインツはすかさず頷いた。
「……っ、もちろん」
「決まりだね! じゃあ三人ともこっちへおいで。予約の取り方を教えるよ」
ハインツとベルのやりとりを見守っていたデントが手招きしながら専用端末まで歩いていく。
「このジムバトル予約のボタンを押して、この画面になったらここにトレーナーカードを入れるんだよ」
手際良く、そして三人にもちゃんと見えるように端末を操作する。カードを読み取るよう説明書きが出ている画面が表示されたのを確認すると、デントはカード差し込み口を指差した。
「今回はトリプルバトルってことでちょっと特殊だから誰か代表ひとり分の予約だけしてくれればいいよ。ジムに戻ったら僕が責任持ってうまいこと調整しておくから」
「じゃあチェレンにお願いしちゃおうかな」
ベルの提案にハインツも頷いた。
「分かった。今回は僕が代表ということで」
チェレンは鞄からトレーナーカードを取り出すと差し込み口に躊躇なく入れた。読み込み中、という画面が十秒程度表示されると、予約が完了しました、という端末からアナウンスが発せられたと同時にカードが出てくる。
「これで予約は完了! 明日のジムバトル、とっても楽しみにしてるよ」
果物の入った紙袋を抱え直したデントにチェレンが感謝を述べた。
「何から何までありがとうございます」
「こちらこそ、お節介に付き合ってくれてありがとう。挑戦者なんてなかなか来ないからちょっとはしゃいじゃったよ。さあて、そろそろ帰らないと怒られちゃうかな」
あはは、と笑いながら紙袋を少し持ち上げてみせた。どうやら買い出しを頼まれていた途中だったようだ。
「よかったらレストランにもおいでよ。サービスしてあげるから」
じゃあね、と軽く手を振るとデントは踵を返し、ポケモンセンターを出て右手方向へ小走りで去っていった。
「サンヨウシティに着いて早々すごい人に出会っちゃったねえ」
デントが去っていった方を眺めながらベルが誰に言うでもなく呟いた。ハインツとチェレンも、そうだな、と呟いた。