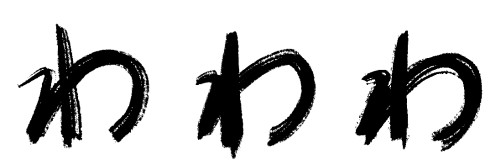アララギが作文を読む数ヶ月前——。
「ええっ? ハインツっていじめられてるの?」
「ベ、ベル! 声が大きいって!」
カラクサタウンの外れのカフェで、室内よりテラス席の方が周りを気にせず話せると思って外で席を取ったが、あまり意味がなかったようで通行人が何事かと見てきた。
チェレンは持ち上げかけた腰を下ろすと、咳払いをして腕を組んだ。
「いじめられてるんじゃないって、ただ、うまく馴染めなくて孤立しちゃってるらしい」
「そうなんだあ」
そう言ってベルは息を吐いた。安堵からなのか、それともため息なのかチェレンには判断できなかった。なんとなく気まずさを感じて、チェレンは目線を手元のカフェオレに移す。
カノコタウン。昔ながらの景色を色濃く残す、イッシュ地方でも有数の——田舎町。特に少子化問題は深刻で、昨年はカノコ唯一の学校が廃校になり、チェレンたちはカラクサタウンの学校に通わなくてはならなくなった。
ベルは元々人懐っこく、昔から誰とでも仲良くなれるし、チェレンも人と話すのは好きな方で、新しい環境になっても積極的に声をかけてあっという間に馴染んでいった。
一方、幼馴染のハインツはというと、引っ込み思案というか人見知りが激しいというか、そもそも口数が少なく、チェレンと少し離れたクラスになってしまったが故にどうにも誰にも頼れず孤立してしまっているようだった。
「最近、休みがちなのはそういう理由らしい」
「相談してくれればいいのに」
「できないのがハインツだろ。すぐひとりで抱え込むんだから」
そう言いながら、それだけ自分は頼りないのかもしれないと静かに落ち込んだ。
「どうにか元気付けてあげたいよねえ……」
「そこで相談なんだけどさ」
チェレンは鞄から封筒と冊子を取り出すと、テーブルの上に広げてみせた。ベルは早速その冊子を手に取り、開いて中を見始めた。
「アララギ研究所トレーナー支援?」
「そう、夏休みにちょっとだけポケモントレーナーになれるんだ。三人で旅に出てみない?」
封筒の中の募集要項を取り出す。イッシュ在住の健康な十歳から十八歳の子供なら誰でも応募できる。トレーナー資格を持っていなくても、アララギ研究所で研修を受けるので問題ない。
「まだまだ先になっちゃうけどさ、ハインツのこと僕なりにいろいろ考えてみた結果がこれなんだ」
ベルはひとつ下だが、ほとんど生まれてからずっと何をするにも三人で一緒だった。学校やら何やらでバラバラになることも多くなって、三人で居る機会も昔より少なくなった。
「ハインツには、口でどうこう言うよりも、態度で示す方が効くと思ってる。生まれ故郷を離れて、三人で力を合わせて旅をしながら、ハインツはひとりじゃないってことを伝えたい」
「いいねえ、それ!」
ベルはようやく冊子から目を離し、目を輝かせてチェレンを見た。何度も頷き、満面の笑みを浮かべている。
「ポケモンたちとも触れ合って、あたしたちと一緒に過ごせば、きっとハインツも元気になるよ」
「もしかしたらハインツは思っている以上に落ち込んでて、この考えはかなり楽観的かもしれないけど、僕たちにとってもいい経験になると思う」
チェレンは再び、まだひと口も飲んでいないカフェオレに目を向けた。
「どんな時も、誰に何を言われようとも、ハインツの味方でいたい。それを伝えたいけど、思いつくのはこれに応募するくらいしかなかった」
多分、今ハインツを元気付けようと声をかけても、何も届かないだろう。学校に馴染めて、こうして通えている自分が何を言っても、ハインツの心に届くまでの言葉をかけてあげられないという確信があった。
「うん、すっごく良いと思う」
そう微笑むベルを見て、ベルも同じようなことを感じているのかもしれないと思った。
「ハインツにいろいろなものを見せてあげよ。学校に行くだけが人生じゃないもん。たくさんの可能性が広がってるんだよって、そういうのを知る旅にできたらいいね」
ベルの言葉に頷いた。そう、ハインツを助けてあげたい。それでもハインツを助けるためには、今の環境じゃ駄目な気がする。
「あいつには夏の思い出作りしようとかそんな感じのこと言った方がいいかな。ハインツのためって知ったら行かなくていいとか言いそうだし」
「たしかに言いそう。でもハインツママにはちゃんと言わなきゃだよねえ」
「そうだな……っていうかまだ行けるって決まったわけじゃないけど」
チェレンは封筒の書類を取り出して眺める。履歴書や健康診断書の提出だけではなく、そこそこ長めの作文も提出しなければならない。まずはこれを書き終えて提出できてから、もし旅に出るならどういう準備が必要か考える方がいいだろう。
「楽しみだな〜」
ベルはようやく手をつけていなかったケーキをひと口食べた。
チェレンも少し間を置いてから、カフェオレをひと口飲む。カラクサタウンの学校に通うようになって、何度か帰りにこのカフェに寄ることがあったが、ハインツとは来ていないことに気が付いた。そもそも、最近あまり外でハインツとどこかへ行くこと自体していなかった。
チェレンはカフェオレの入ったグラスを置くと、いつかハインツともこうしてのんびりとカフェで過ごせたら良いとぼんやり考えた。