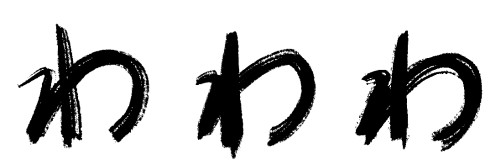色とりどりの野菜や果物、新鮮な肉や魚。市場は大賑わいで大勢の人で埋め尽くされていた。
「これふたつもらっていいか」
サンジは人混みを綺麗に掻き分け、お目当ての食材を次々と買い漁っていく。いつもの店の買い出しとは違って少量なので、荷物が増えても何ら苦ではない。
リルペリタウン。いつもバラティエの船のメンテナンスをしてもらっている小さな町。ほぼ年中無休のバラティエだが、この町に滞在している間だけは珍しく休業中である。従業員たちは町に繰り出し思い思いの休日を堪能しているが、サンジにはリルペリタウンに来るたび欠かさず訪れている場所があった。
「おいジジイ、買うもん買えたか?」
「誰に向かって言っていやがる」
そこはサンジだけでなく、ゼフにとっても特別な場所だった。
「お、鳩か。太ってるな〜。美味そうだ」
サンジはゼフの荷物をヒョイと奪うと中身を興味津々に眺めた。
「じいちゃん喜んでくれるといいな」
二人は市場を後にし、町外れに向かって歩き始めた。リルペリタウン外れの豪邸。十人住んでも部屋が余るだろうと思われるその豪邸には、意外にも二人ほどしか人は住んでいない。
この豪邸の主はホーレルバッハ・ピッケーニ。東の海有数の美術鑑定士であり、多くの海賊が見つけ出したお宝の価値を決めてきた男でもある。かつては各地を回り鑑定をし、その鑑定料でかなり儲けていたらしいが、もう年だと言ってここ十数年ある程度の財を手元に置いてすっかり隠居している。
今ではピッケーニ本人と、長年仕えているという従者の二人だけで暮らしているのである。
サンジとゼフはピッケーニの豪邸に到着すると、玄関のドアを三回ノックした。
「じいちゃん! おれだ! メシ作りに来たぞ〜!」
玄関の扉ではなく、二階のテラスに向かってサンジが叫んだ。ひと呼吸おいてテラスの扉が開くと、中から老人が出てきて玄関先を覗き込んだ。色ひとつ混じらない白髪と顔に刻まれた深い皺からそこそこな年だと感じられるが、背筋の伸びた筋肉がしっかりついている体のおかげで実年齢より若い印象を受ける。
「ゼフくん、サンジくん、よく来たね。バラティエが港に入っていくのが見えたから今か今かと待ち侘びていたよ」
ピッケーニの声はそう大きくなかったが、玄関の二人の耳にも届いていた。よく通る声だとサンジはいつも思う。
ガチャリという音と共に玄関の扉が開き、ピッケーニの従者であるミルテンが姿を見せた。ピッケーニと違い、ミルテンは小柄で痩せぎすで、どこか頼りない印象を受ける男だ。
「お久しぶりです、お二人とも。ささ、どうぞ中へ」
サンジもゼフも軽く挨拶をするとピッケーニの館へと足を踏み入れた。二人は躊躇せず真っ直ぐに厨房へと向かい、市場で仕入れた食材を慣れた手付きで厨房の台へ並べていった。
ワンワン、と犬の鳴き声が聞こえてきてサンジは厨房の入り口に目を向けた。立ち上がったらサンジよりも大きいと思われる白い狼にも似た犬が、厨房の手前で座り二人に己の存在を知らせている。
「ハロ! 元気にしてたか?」
サンジの言葉に、ハロと呼ばれた白い犬は短くワンと鳴いて応えた。テラスのあった部屋から下りてきたであろうピッケーニが、厨房の入り口に寄りかかりながらハロの頭を撫でる。その様子を横目で見たゼフが毛が舞うだろうと小言を呟くが、犬の主人は少し肩を竦めるとまた愛犬を撫で始めた。
「僕もハロもミルテンも元気さ。二人はどうだい? 何も変わりないかな」
「見たまんまだ。お互い元気そうでなによりだな」
サンジが笑って見せると、ピッケーニも柔らかく微笑んだ。
「じゃあ僕らはゆっくりご飯を待つとしよう」
「おう! 楽しみにしてろよ」
ピッケーニが従者と愛犬を連れて居間に向かう背を見送ると、サンジとゼフは目を合わせた。
「さてジジイ、何から手をつける?」
店とは関係ない、好きなように作っていい料理。いや、バラティエでの調理に不満があるわけではなく、もちろん好きだしやりがいだって感じている。だが市場を見て回ってその場でレシピをああしようこうしようと考え、大人数で分担せずに一から調理するとなると普段の仕事とはまた違った楽しさがあるのも事実だった。
「てめえはソルベを仕込め。それが終わったらセビーチェだ。おれは鳩をやる」
「了解!」
それはゼフも同じようで、いつも通りの仏頂面だが心なしか楽しそうに見える。
何よりサンジはこの時間が好きだった。船のメンテナンスでこの町に寄るたびにこうしてピッケーニの館で料理を作っているが、二人きりで料理を作れる機会など他ではそうそう訪れない。ゼフの調理を間近で見られること、ゼフと分担して調理すること、バラティエの厨房では決して得られない経験である。
まだバラティエで雑用ばかりしていた頃は、ここの厨房でも皮剥きとか湯を沸かすとか皿の準備とかそういうものしか任せてもらえなかった。だが今は違う。一緒になってメニューを考えるし、買い出しついでにメニュー変更の提案をして意見を出し合うことだってある。この厨房に立つたびに自分の成長を感じられると共に、それが自信にも繋がっていく感覚が好きだった。
日が傾き、おそらく多くの家庭で夕食が振る舞われているであろう時間に、ピッケーニの館の食卓にも同じように夕食が並べられていた。普通と異なるのは、この食事が東の海で一位二位を争うほどのレストラン『バラティエ』の料理長と副料理長によって作られたものである、というところだ。
四人(と一匹)で食卓を囲みたいというピッケーニの要望で、コース料理ではなくオードブルもメインディッシュも全て一緒くたにテーブルに並べられている。ピッケーニに続いてゼフとサンジも着席すると、ミルテンがそれぞれのグラスにワインを注いでから着席した。ハロは主人の椅子の下で丸くなって寝ている。
「いつもありがとう。君たちの美味しいご飯は僕の人生の喜びだよ」
ピッケーニが正面に座るゼフとサンジの顔を交互に見ると、ワイングラスを手に取った。
「何に乾杯しようか」
「じいちゃん、別になんだっていいだろ」
早く食おうぜ、とサンジが促すが、隣のゼフがグラスを少し上げて「バラティエに」とぶっきらぼうに言い捨てた。
「バラティエに乾杯」
他の三人も続いた。バラティエの船があるのも、そしてゼフとサンジが今こうして料理ができるのも、全てはピッケーニのおかげだった。
コンソメスープにタイのセビーチェ、鳩のサルミなど豪華な料理——決して食材は高価なものではないが、二人のコックの腕の良さとピッケーニの所有する高級皿のおかげで品の良さが強く演出されている——が並び、会話はそこそこに四人は食事を楽しんだ。皆の食事が終わる頃にサンジはそっと席を外し、厨房まで紅茶のゼリーを取りに行き食卓に並べた。
「いつ食べても二人の料理は美味しいね。会うたびに料理の腕を上げていてびっくりするよ」
ピッケーニの褒め言葉を聞いてゼフが鼻で笑う。
「チビナスの料理の腕なんざたかが知れてる」
「うるせえぞクソジジイ。てめえなんかもう伸びしろがねえんだよ」
「生意気な口ききやがる」
二人の言い合いにミルテンはどうしたものかと慌てているが、ピッケーニはというとアッハッハと声を上げて笑っていた。
「いつも通りで安心した。二人してここで寝込んでいた頃が懐かしいね」
その言葉に、サンジは一瞬表情を硬くした。誰にも悟られないようにすぐさま作り笑いを浮かべ、懐から煙草を取り出した。
煙草を咥える前に、ピッケーニがサンジの目の前に煙草ケースを差し出すのが目に入った。せっかくだからもらうよ、と礼を言って受け取ると火をつける。ピッケーニの煙草はサンジの趣味には合わないのだが、だからといって別に嫌いなわけでもなかった。
足に何か触れた気がして椅子の下を覗き込むと、白い大きな塊がサンジの足元まで来ているのが見えた。ハロが純白の毛を黒いスラックスに擦りつけて甘えてくるのを見て苦笑する。まあ分かりきっていたことなのでそこまで気にしていない。
手を伸ばして顎の辺りを撫でてやると、もっとやってくれと言わんばかりに顔を押しつけてきた。取り留めのない世間話をする老人たちをぼんやりと眺めながら、煙草を吸い犬を撫でる。
ここで寝込んでいた頃。先程のピッケーニの言葉をサンジはゆっくりと反芻した。この館には、さまざまな思い出がたくさんあった。
ほとんどを海の上で過ごしてきたサンジにとって、リルペリタウンのピッケーニの館は陸上で最も長く滞在していた場所である。
サンジはいつもと違う煙草の味に違和感を覚えながら昔のことを思い返した。
◇◇◇
ほとんど水のような、どろどろに煮込まれた味付けのされていない麦粥を口に含んだ。皿の粥を一気に流し込んでしまいたい衝動に駆られるが、それは駄目だときつく言われているので必死に抑えた。
昨日は欲望に逆らえずがっついてしまい、弱りきった胃が悲鳴を上げせっかく食べたものを吐き戻してしまった。あんな勿体ない真似二度とするかと誓い、サンジはほぼ液体の麦を咀嚼する。
味気ない麦粥、それでも涙が出るほど美味かった。昨日麦粥を食べたとき、これからの人生でこれ以上の美味いものに出会うことはないと思った。一昨日も食べていたらしいが、意識が朦朧としていたのか記憶に無い。
サンジはひとくちずつ時間をかけて麦粥を飲み込みながら、ちらりと正面の老人に視線を移した。とうに食事を済ませて紅茶を飲んでいるピッケーニは、新聞や本を読んだりして時間を潰しながらサンジの食事が終わるのを待っている。
「もうお腹いっぱいかい?」
視線に気がついたピッケーニが尋ねると、サンジは首を横に振り麦粥を口に運び続けた。
ここ数日は意識が朧げだったのでよく分かっていないのだが、どうやらサンジとゼフはこの老人に助けられたらしい。気がついたときにはあの岩山ではなく、この館のベッドで寝ていたのだ。
「……あの」
ようやく器を空にすると、サンジは小さく呟いた。
「どう、して…………」
長らく発声していなかった喉は、その使い方をすっかり忘れてしまったようで思うように声が出せなかった。
「老後の人生を満喫していたおじいさんのお節介だよ」
ピッケーニはそういうと、カップを持ち上げて紅茶をひとくち飲んだ。お節介、というにはあまりにも待遇が良すぎる。何か裏があるのかもしれないと勘繰るが、長いこと極限状態にあった所為で体力は低下しているし、食事も流動食を少しずつしか食べれていないのでうまく頭が回らない。
サンジは思い出したように襲ってきた疲労感と眠気で、目が開けていられなくなった。微かに残る意識で、ピッケーニによって寝室まで運ばれたのは分かったが、ふかふかのベッドに乗せられた途端意識を手放してしまった。
次に目を覚ましたときは、カーテンの隙間から漏れる陽の光が眩しい昼下がりだった。眠る前も同じような時間帯だったことを思い出し、ああ、丸一日寝てしまったのかと思う。もしかしたら二日かもしれない。一体今が何日なのかサンジは知らなかった。
ひたすら眠り続けても鉛のように重い体をなんとか起こし、左に顔を向けた。サンジが寝ていたベッドと並んでもうひとつベッドがある。朝起きるたびに、死んだように眠る男の顔を見てはみぞおちあたりがぎゅっと縮こまる心地がした。
サンジは自分で食事を取れるようになってから、少しずつ体力が戻りつつある。骨と皮だけのような手足は相変わらずだが、こうしてひとりでベッドから起き上がったり壁伝いに歩いたりできるようになった。
一方ゼフはというと、どうやら脚の傷の具合が良くないらしく、高熱が続き意識も朦朧としたままだ。あともう二、三日この状態なら死んでもおかしくはないと医者が言っていた。
サンジはベッドから出ると、這うようにゼフのベッドへ向かった。普通なら十歩程度で到達するような距離が、筋力も体力も失った今では途方もない距離に思えて仕方がなかった。
ベッドに手をかけて這い上がると、ゼフの右脇に丸くなって寝そべった。確かにゼフの胸が上下しているのを見て少しだけ胸を撫で下ろすが、ふと医者の言葉を思い出してはまた圧迫感が胸に押し寄せてくるのを感じた。
視界が歪む。なんて自分は弱いのだろう。ジジイに助けられて、見知らぬ老人に助けられて、それをただ享受することしかできないなんて。何もできないなんて。
悔しくて悔しくて仕方がなかった。無力感が容赦なく全身を襲う。
どうか、どうかこのクソジジイを助けてください。お願いします。
サンジは嗚咽を噛み殺して、静かに静かに泣いた。
重い瞼を持ち上げると、右腕あたりがぼんやりと温かい気がした。ゼフは少しだけ首を持ち上げると、ぐずぐずと泣きながら自分の傍で丸くなって寝ているあの少年が目に入った。白いシーツに黄色い小さくて丸い頭がぽつりと浮かんで見えて、なんとなく目玉焼きのようだと思った。そう思うと、途端に空腹感を覚えた。
「目が覚めたかい?」
寝ている少年に気を遣ってか、音を立てないよう部屋に入ってきたピッケーニが声を窄めてゼフに話しかけた。
「食べれるかな」
ピッケーニが手にした盆には麦粥が乗っている。食べ物の匂いに更に食欲が刺激され、早く腹を満たしたいと体が訴えた。
体を起こそうと力を入れると、右腕の重みが小さな命の存在を思い出させた。
「おやおや、こんなとこで寝たら風邪を引いてしまうよ」
ベッドサイドテーブルに一度盆を置いたピッケーニが、少年を元のベッドへ戻そうと両脇を抱える。
「…………ま、まて」
酷く掠れた声だった。からからに乾ききった喉は自分の意図を汲んでくれず、途切れ途切れに言葉を発することしかできなかった。
「もう、少し……この、まま……」
この右腕の温もりを離したくなかった。この体温が心地よかった。こうして自分に寄り添ってくれる人間なんて、今までいただろうか。
ゼフは、自分が清い人間だとは微塵も思っていない。海賊として略奪も強奪も数えきれないほど行ってきた。失った脚で、どれだけ人を傷つけてきたことだろう。
それでも、いや、だからこそ、この温もりに応えたいと思った。殺してやると喚いていた、自分の勝手なエゴで生かしたこの小さな黄身が、自分に寄り添ってくれるということがたまらなく嬉しかった。
料理の他に、取り柄と言えるものは暴力しかなかった。海賊くらいにしかなれなかった。だが、この温もりがそうではないと言ってくれているような気がするのだ。同じ青を夢見た瞳が、同じ明日を歩もうと言ってくれているのだ。
取りこぼしてたまるか。死んでたまるか。小さな小さな、この世に生を受けてまだほんのひと握りしか生きていない命が、ただそこに居るというだけで力をくれた。
クッションを背に挟み、少しだけゼフの上体を起こすと、ピッケーニは麦粥を口元に運んでくれた。ゆっくり咀嚼しながら、そういえばもう何ヶ月も一緒に居るというのに、このチビナスの名前が何なのか知らないな、と心の中で呟いた。
食事を終えるとまたすぐに眠ってしまったが、次起きたときも変わらず小さな黄身が同じように丸くなって寝ていた。固まった体を少しだけ動かそうと身じろぎすると、その僅かな動きで少年が目を覚ましてしまった。仕方がないかと諦め眠そうに目を擦る顔に、そういえば名前を聞いていなかったな、と投げかけると、少年は嬉しそうに微笑んで、おれもジジイの名前聞いてなかった、と言うのだ。サンジというらしい。そういえばオービット号の人間がそう呼んでいたような気がした。
熱が下がり意識が朦朧としなくなると、次第にゼフの心は怒りに支配されるようになった。
まずひとつは、思うように回復しない自分自身の体に。年も取ったし脚の怪我のこともある。だから回復が遅いのは仕方ないのだと頭では分かっているつもりだが、みるみる回復して今では家を自由に動き回っているサンジを見ると、どうしても焦りが湧き出てくる。
そう、次にサンジだ。寝込んでいる間に随分とピッケーニに懐いたらしい。ゼフのことはジジイだのクソジジイだの言うくせに、ピッケーニのことは『じいちゃん』と呼んで愛想を振りまいている。どうにも気に食わない。
気に食わないといえばとにかくピッケーニだ。ゼフが海賊だと知っていてもなお海軍に連絡もせずサンジと共に匿い、面倒を見るのには何か裏があるのだろうと疑っていたがどうやらそうではないらしい。
ピッケーニは隠居する前に東の海で船旅をしようと、船を買い船乗りを雇い自由気ままな海遊を楽しんでいたらしい。その旅が終わるころ、船乗りの一人がどうしても気になって仕方がないとゼフたちが打ち上げられた岩山に向かって欲しいと懇願したと聞いた。
鑑定士だというピッケーニはゼフの持っていた財宝を鑑定したらしく、二人の治療費はそこから貰うと言っている。サンジが口走ったと思われる海上レストランの計画にも賛同してくれ、この町の船大工に話をもっていってくれているようだ。それもゼフの財宝の金額でやり繰りしておこうと言っていたが、何ヶ月も海風や雨風に晒し続けた——あとどっかの誰かがおもむろに突き立てたナイフの傷跡もあったはずだ——財宝に、そこまでの価値があるとは思えなかった。ピッケーニは具体的な鑑定額を教えてはくれなかったが、船を造れるほどの金額が果たしてあるのかどうか。
何か騙されているのではないかと、後々何かツケを払う羽目になるのではとゼフは不審に思った。だがそうではないのだ。
ゼフは悟った。ピッケーニの瞳には、深い自責と同情の色が浮かんでいるのだと。
あのとき、岩山に横たわる痩せ細った男二人を見てピッケーニは何を思っただろう。数ヶ月前に己が助けられたはずの男たちを。
彼なりの贖罪なのかもしれない。しかし、罪の意識と同じくらい同情の目を向けられているというのにゼフは腹を立てていた。直接言われたことはないが、こんなになって可哀想だと、助けてあげなくてはという憐憫の色が滲み出ているのが気に食わない。
金持ちに雇われたそこいらの船乗りに気遣われたという事実にも怒りが込み上げてくる。あのときどんな惨めな思いをしようが生き伸びてやると覚悟を決め、右脚を砕き海賊の誇りと共に食ってやった。だがその誇りは飲み込んでも消化されることはなく、再びゼフの血肉となってしまったようだ。
海賊の心が言っている。こんなやつらに情けをかけられるくらいなら死んだ方がマシだと。
「おいジジイ! 起きてるか?」
部屋の扉が勢い良く開くと、盆を持ったサンジが入ってきた。ぱたぱたと小走りでゼフのベットまで近付くと、サイドテーブルに盆を乗せて、スープの入った皿とスプーンをゼフの目の前まで持ち上げる。
「なあ見ろよ! おれが作った!」
小さく刻んだ野菜がたっぷり入ったスープから、牛や鶏の出汁の香りがふわりと漂ってきた。その香りから、ブイヨンの作り方が甘いな、と思う。
「おれに料理を作るなんざ、百年早えぞチビナス」
そう吐き捨てると、いいから食えよ、と皿を渡された。
「このスープが不味いって思うなら、早く体力戻して自分で作りやがれ」
情けをかけられるくらいなら死んだ方がマシだと海賊の心が叫ぶ。
だが、生き抜いてみせろ、ともうひとつの心が叫ぶのだ。
「レストラン、やるんだろ。おれにも料理を教えろよ」
どんなに惨めでも生きる意味があると。この小さな命の鼓動が教えてくれるのだ。
「中途半端に教えるつもりはねえぞ。泣き出しても知らねえからな」
礼のひとつやふたつ言えばいいものを、五十年以上も素直とはほど遠い生き方をしてきたゼフは憎まれ口しか叩けなかった。己の不器用さに内心苦笑するが、今更変えられるものでもねえかと半ば強引に納得した。
「泣かねえよ!」
チビナスの元気な返しに、ゼフは口元を緩めた。
◇◇◇
目を開けると見慣れないカーテンが見え、自分の部屋でないことに気付く。逡巡の後、ここはピッケーニの家だったとサンジはひとり納得した。
コックの朝は早い。自然と目を覚ませば、休みの日だろうが季節によってはまだ日が昇っていない時間に起きてしまう。
見慣れないカーテンの裏には、きっとようやく白んできた空があるに違いない。もう一度寝直そうか、と思うが習慣というのはよくできているもので、どうにもしっかりと目が冴えてしまった。
サンジは首だけを左に向けた。ベッドに横たわる男が目に入り、血の気が引いていくような感覚が胸のあたりからじんわりと広がるのを感じた。
何度この家に泊まっても慣れない。指先が冷えていく。喉元で息が詰まる。
ゼフは意外と静かに眠るのだ。あまり身じろぎせず、寝息もそこまで大きくない。この部屋で眠る度、いや起きる度に、サンジはこうしてベッドの中でゼフを見て、僅かな呼吸や動きを感じられるまでじっとしていた。
何故そうしているのかサンジ自身にも分からなかったが、ある意味これも習慣というか、こうしていないと落ち着かず毎回同じことを繰り返してしまう。ゼフは気付いているのだろうか。もしかしたら狸寝入りをしているのかもしれない。
ゼフのゆっくりと上下する胸を見ていると、下がっていた体温が徐々に戻っていくような気がした。もうあれから十年近く経っているというのに、寝て起きたらゼフが死んでいたらどうしようという漠然とした不安が押し寄せてくる。
サンジは慎重に毛布を退けると、サイドテーブルに置いておいた煙草ケースとマッチを手に取り忍び足で部屋を後にした。
日が昇っていない庭はひんやりとしていて少し寒かった。ベンチに座るともっと冷えそうだと思い、しゃがんでアーチのオブジェに背を預けながら煙草を吸っているとどこからかハロが駆け寄ってきた。
「おはようハロ。お前も早起きだな」
早朝だと理解しているのか、くーんと喉を鳴らすだけで鳴きはしなかった。大きな温もりが身を寄せてくれて寒さが少し和らぐ。
「あったけえなあ」
煙草を持っている右手を遠ざけながらハロの長い体毛に体をうずめた。ハロは負けじと体を押し付け、身を捩ってはサンジの顔を舐めようとしている。べろり、と頬を舐められ、サンジは勘弁してくれと立ち上がった。
右手の煙草を口に咥え直し、吸って、白煙を吐き出した。その煙が空気に溶けていく様を、ぼんやりと眺める。
「お前にも、じいちゃんにも、ミルテンにも会えて、嬉しいよ」
白煙が消えた空間を、どこに焦点を合わせるわけでもなく眺め続けた。
「ジジイと料理できて楽しかったし、また次来るのも楽しみなんだ」
この町に着く前、市場で食材を見ているとき、ゼフとああじゃないこうじゃないと言いながらの料理中、会っていなかった間の話をする食後、楽しさと嬉しさが混ざり合って、充足感で満たされるのに。
この家で朝起きると、意味もなく胸が締め付けられる。不安感と喪失感が大きな波のように押し寄せて、あの岩山に打ち上げられた日々が昨日のことのように思えてくるのだ。
黒い空、激しい嵐、岩山の感触、溜まった雨水、ひと握りの食料、耐え難い空腹感、袋いっぱいの財宝、片方だけの脚、己が奪ったひとりの男の夢。
「なんだろうな……」
ピッケーニが使っているであろう屋外用の吸い殻入れに煙草を捨てると、サンジは再びしゃがみ込みハロを両手で抱きしめた。先程とは打って変わって尻尾を振る以外微動だにしないのを見て、聡い犬だなあと心の中で呟いた。
港町から少し離れたこの館で、思い出すのは海のことばかり。波の音も聞こえなければ、周囲は森に囲まれているから潮風だってあまり届かない。
それなのに、普段目を背けているものが自然と脳裏を過ぎていくのだ。
四方を海に囲まれているバラティエに居るときよりもこの海から離れたピッケーニの館に居るときの方が、海の過酷さを、夢の青さを思い出すなんて不思議なものだ、とサンジは思った。