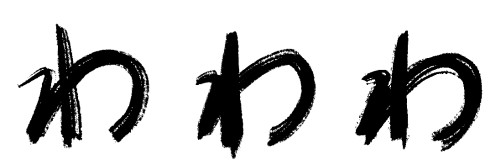バックヤードの情報圧は非常に厄介なもので、常に生物が霧散するほどの高密度であることは変わりないが、空間内には波のようなものがあり絶えず密度の数値が変化し続けているのである。人間が耐え得る圧力に変換するには、その『波』の規則性を計算し適応させなければならない。
常にバックヤードに引きこもって居られればいいのだが、そうも言っていられないのはこの『波』の規則性も変化し続けるというところにある。
ここ最近その規則性の変化を察知し、自身にかかる負荷の上昇を感じた飛鳥は、体の療養も兼ねて現世のセーフハウスに身を潜めていた。聖戦を機に放置されたらしいこの家は、おそらく二世帯家族が住めるほどの広さがあるため、大型の機材も難なく収納できた。人里離れた森の片隅にひっそりと建っているので、法術の実験などを行うとき騒音に対してそこまで神経質にならずに済むのは気が楽だった。一時的な避難場所ではあるが、飛鳥はこのセーフハウスを気に入っていた。
カーテンの隙間から差し込む日光が顔にかかり、飛鳥は思わず毛布を頭の上まで引き上げた。バックヤードでの生活に慣れきっていた彼にとって、日光や朝という概念は自分の生活とかけ離れた異質なものでしかなかった。
(寝室……地下室にするべきだったか……)
毛布に潜り込んでもなお、瞼の裏で光がチカチカと瞬いているような気がして目を更に固く瞑った。レイヴンに移動を頼むか、と考えた途端、おや、と異変に気付く。飛鳥はゆっくりと上体を起こし、やけに眩しく感じる窓をカーテン越しに眺めた。
(…………昼、だな)
明るさに慣れず目を細めながらも、寝ぼけてごちゃごちゃと散らかっていた思考が段々と整理されていくのを感じ取った。
この部屋は朝日が入らないはずだ。おかしい。飛鳥は指先を動かして更に覚醒を促した。いつも昼前には必ずレイヴンが起こしに来るんだけどな。
一応ここには療養目的で滞在しているので、規則正しい睡眠と食事は大切だと言ってレイヴンがいつも以上に世話を焼きたがっているのだが、どうやら今日はそうではないらしい。
(何かあったのかな)
飛鳥はゆっくりとした動きでベッドを出ると、クローゼットを開けてカーディガンへ手を伸ばした。そこに並ぶひと回り小さな衣類を見て、ああ、そろそろか、と思う。
カーディガンの袖を掴んだままの自分の手を見た。少し骨張った、青白く細長い指。張りのない乾燥した血管の浮かぶ手の甲。友人より遥かに細かったけれど、それでも子供より太さのある手首。いつの間にか、体はあの頃と同じくらいにまで成長してしまっていたのか。
幼若化させるにも体を万全な状態にしておく必要があるし、何よりレイヴンの協力が不可欠だ。とりあえず目の前のことを片付けるべきだ、と言い聞かせ、飛鳥はカーディガンを取り出すと乱雑に羽織ってから部屋を後にした。
むわり、とむせ返るほどの血のにおいが立ち込め、僅かに頭の片隅で存在を主張していた空腹感が遥か彼方に消え失せていくのを感じた。胃のあたりが引き攣り、何かが迫り上がってくる感覚がして飛鳥は咄嗟に口元を押さえた。
キッチンは、酷い有様だった。鮮血がそこら中に飛び散り、床には大きな血溜まりができていた。その血溜まりの中央にはレイヴンが仰向けに倒れ込んでいて、意識が無いのか見開かれた瞳は虚空を見つめていて動かない。レイヴンの首には深々とナイフが突き立ててあり、今もなお鮮血が吹き出していた。
(発作だな……しばらく起きていなかったから油断していた)
飛鳥はレイヴンの自傷行為を一種の趣味だと受け入れている。痛みが彼に生きる実感を与えてくれるのなら、彼がそれを望むのなら、それでいいのではないかと。彼が痛みで得る喜びや快感の代わりになる何かを持ち合わせているわけでもない。ならば、境遇を、必要性を理解し、受け入れることが自分にできる唯一のことだと飛鳥は考えていた。
レイヴンは痛みを通して感じられる生の実感を常に渇望している。だが、飛鳥の指示には忠実に従うし、そういう時には『趣味』を露わにすることはほとんど無い。彼なりに分別があり、なるべく飛鳥の頼み事と己の趣味を切り離して考えてくれているようにも思える。
ただ時折、どうしても切り離せないことがある。
どんな状況だろうと、どれだけやらねばならぬ事があろうと、何もかもお構いなしに痛みを求めてしまう。レイヴンの全てを揺さぶり、激しい衝動となって襲いかかる。痛みを欲しているのではない。快楽を求めているのではない。
今生きているのだという実感を得ねばならないと、そうでなければ輪郭のない漠然とした膨大な恐怖と狂気に支配されてしまうと、必要に駆られて彼は己の体にナイフを突き立てる。
この状態を、飛鳥は発作と捉えていた。
キッチン脇の小さなテーブルに置いてある、おそらく飛鳥のために用意されていたであろう朝食は血にまみれ、純白の丸皿がよりその赤を際立たせていた。自分は食物を必要としないにも関わらず、レイヴンは飽きもせず毎日飛鳥の食事を用意してくれる。自分とは無縁だと思っているからこそ、食事というものを大切にしているのかもしれない。
彼が大切にしているものを、他ならぬ彼自身が壊してしまっている状況を目の当たりにするたびに、飛鳥は体が冷えるような物悲しさを覚えた。彼の用意してくれる料理はいつも温かくて美味しいのに、彼がそれを感じることはない。それが、どれだけ苦しいか、きっと僕には一生理解できないだろう。
飛鳥はレイヴンの頭の近くにしゃがみ込むと首に深く刺さっているナイフの柄を握った。ひと呼吸おいてから更に強く握ると、ゆっくり、ずるりとそれを引き抜いた。傷口から勢いよく血が吹き出て飛鳥の顔に跳ねたが、飛鳥は顔を逸らさず、目を瞑ることもなく、塞がっていく傷口を眺め続けていた。
「レイヴン」
小さく弱々しい呼びかけだったが、レイヴンの瞳が一瞬揺れ、瞳孔が開いたかと思うと左右に動き、やがて飛鳥の顔を捉えた。
「おはよう」
レイヴンは傷が塞がってしまった首元を撫で、微かに残る痛みを感じているようだった。はあ、と艶っぽいため息をつき、目を閉じて指を這わせている。痛みが引いたのだろうか、しばらくすると目を開き再び飛鳥の顔へ視線を向けた。
「……ご迷惑を」
「いや、気にしていないよ」
気怠げに上体を起こしたレイヴンは、悲惨な状態のキッチンを端から端まで見渡し、先程とは随分異なるため息を溢した。指で眉間を押さえ俯いてしまったレイヴンを見て、飛鳥は彼の衝動に対して何をするのが最善だっただろうかと考えた。どれだけ思考を巡らせても答えは出てこなかった。