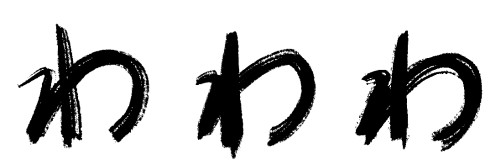「ほら、声に出して言ってみなよ」
まるで鏡を見ているような、自分と寸分違わない顔が目の前で言う。目の前の男が鏡像でないことは、本来ならば目があるはずの場所に生えている翼が左右反転せずに右目側にあることと、その翼と左目の色が異なることから判断できる。
その鏡像ではない瓜二つの男が再び口を開いた。
「君は、誰だい」
「——僕は」
喉に何かがつっかえているような、そんな圧迫感を覚えた。言葉がうまく出てこない。これは喉の問題なのか、それとも思考の問題なのか。
「っ、僕は……っ」
込み上げてくる。
何かが。
それが何なのか全く分からなくて、とにかく恐ろしかった。
ふと、脳裏に浮かんだ景色があった。凍えるほどではないが、ひんやりとした涼しさを感じる風が頬を撫でる感覚を思い出した。緩やかな波の音が、遠くで鳴く海鳥の声が耳を刺激する。眩しく光る朝焼けを背に、こちらを眺める友の姿。
「最後にひとつだけ、お願いをしても?」
優しい響きの友の声に、別れの寂しさと彼を解放してやれる喜びを感じながら頷いた。
「僕が出来ることの範囲であれば、何だってするよ」
その返事に、友は痛みを堪えているような表情を浮かべた。
「貴方が成すべきことを全て終えたとき」
風が吹く。指先が冷える。海鳥が飛ぶ。
「どうか、貴方自身の人生を歩んで下さい」
不思議なことを言うものだと思った。自らの意思でこの道を選択して歩いてきた。いつだって投げ出せたはずだ、諦めてしまえたはずだ。それでも自分は、覚悟を持って今の人生を選択したのだ。
それを否定されたような気がしたからだろう。そうではないと、今までもそしてこれからも僕は僕の人生を歩んでいくのだと言おうとしたけれど、なぜか言葉を発することができなかった。
「魔王でも、あの男でも、ギアメーカーでもない、飛鳥=R=クロイツというただひとりの男の人生を、歩んで欲しいのです」
ああ、そうか。そういえばそうだ。
僕の人生なんて無かった。
千年を生きた友は全てを見抜いていた。自分が持ち合わせている覚悟とは、苦難に満ちた道を選択をするようなものではなく、悲惨な現状を前に納得して歩き抜くと決めるだけのものだ。
友の願いの言葉に、返事をすることができなかった。それでも彼は柔らかく微笑んで、応えられずとも今日のこの会話を覚えてくれているだけでいいのだと、そう言って去っていった。
自分と瓜二つの顔を眺めながら、友の願いを思い出した。三度、口が開かれた。
「君は、誰だい」
「僕は」
何度自分はこの世に存在すべきではないと思っただろう。
人として、また社会性のある生き物として、備わっているべきもののほとんどが欠如している自分が生きている価値などあるのだろうか。しかし、忌まわしいことに生存本能だけは一人前に働いていて、苦痛に対して特に耐性がなく、死にたくないという気持ちだけは人並みに持ち合わせていた。
僕はいつだって僕が生き続けている言い訳を探していたんだ。
探究心、ギア細胞、贖罪。何もせずに生きていることに対して、押し潰されそうなほどの後ろめたさを感じていた。
役割を取り上げられたら、何ひとつ残らない。
陽の当たった新芽のような、南国の澄んだ海のような、そんな形容し難い色の目が、じっとこちらを見据えている。無表情だが、敵意も悪意も感じられない。ただ真っ直ぐ目を見つめていた。
自分にとって未来への希望というものはいつも、砕かれ、否定され、諦めるものだった。
幼い頃、医者になりたいと思っていた。いや、正直なところ、成人した頃だって医者になりたいという夢を完全に諦められていたかといえば嘘になる。
結局、科学者になる道を選んだ。医学よりも科学に興味や適正があるのは自分でもよく分かっていたし、周りからも科学者になるべきだと言われる度に納得していた。
それでも、本当は医者になりたかったんだ。苦しんでいる人々を、助ける人になりたかった。
それを、一度だって口にしたことはない。
家族にも、学生時代からの親友たちにも、ずっと付き従ってくれていた友人にも、誰にだって、この思いを明かしたことはない。自らの内に閉じ込め、封じてきたものだ。子供のような幼稚な夢だと、人として欠陥ばかりの自分には過ぎた夢だと言い聞かせ、まるで一種の悪行だと言わんばかりに自分を責めてきた。
それを、目の前の男は知っている。頭の端に追いやり、目を背け、押さえつけてきた全てを知っている。
人の世で生きる息苦しさを、未知のものに触れる幸福感を、どれだけ努力しても人の心を理解できないもどかしさを、友を得た喜びを、ギア細胞への期待を、己の力不足を実感したときの失望感を、道化を演じたときの押し殺した感情を、友の頭を撃ち抜いた銃の重さを、幼若化させたときの体の倦怠感を、右目の情報定義が書き換えられて翼に変質したときの痛みを、思うように計画が進まないときの焦りと無力感を、自分を恨んでいると知っていたけれど百年以上振りに親友と顔を合わせたときに感じた嬉しさを、再び名を呼んでくれた幸せと罪悪感を、海岸の風の冷たさを、自らの意思で道を選択する恐怖を、変貌した師に対する驚愕を、常に感じている孤独を、己への苛立ちを、多くのものへの諦めを、羨望を、渇望を、劣等感を。
誰とも分かち合うことがなかった、自分を形作る全てを、彼は知っている。
それでも彼は他者だった。
物心ついたときから他者と何かを分かち合うことは不可能なのだと決めつけていた。自分の感覚は決して誰かに理解されるものではないと、逸脱しているのだと、まるで自分は人の形をしただけの別の生物なのだと、そう言い聞かせて生きてきた。
だが、確かに今、自分の全てを知っている他者が目の前に居る。
彼は人工生命体で、この手で作ったものだけれど、自分の内面を理解している他者が存在しているというのは揺るぎない事実である。
「僕は、飛鳥……」
そう口にした途端、眉間や眼窩、こめかみあたりが痛んだ。締め付けられているように、鈍い痛みがじわりと広がっていく。
「飛鳥=R=クロイツだ……」
その痛みはだんだんと左目に集約され、しばらくすると何かが頬を伝う感覚が訪れた。
「そうだ、君は飛鳥だ」
無表情だった目の前の男は、そう言うと目を細めて微笑んだ。その目元の柔らかさが、千年の孤独を知る友のものによく似ていると思った。