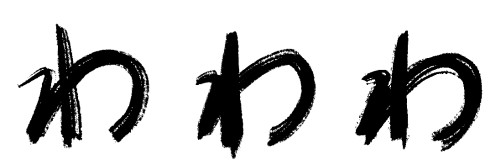※ED後
人が結構死んでます。
チェズレイの父親まわり、本編では出てこない人間や国の捏造設定有り。
ヴィンウェイより愛をこめて発売前に書いたもの。
+++++++
違和感を覚えたのはほぼ同時だった。チェズレイが顔を正面に向けたまま横に並ぶモクマに視線を移すと、同じように瞳をチェズレイに向けていたモクマと目があった。いつもより少し細められたモクマの鋭い瞳からは警戒心が感じられた。チェズレイは持っていた杖を強く握り直すと、ハンドサインだけで『敵情を探ってくる』と示したモクマに対して頷き、彼の後ろ姿を見送った。
チェズレイの故郷であるヴィンウェイの南西に隣接する小さな国、ダブラドラ公国。今回のターゲットはその公国内に存在する貿易会社である。
かつてヴィンウェイの裏社会で猛威をふるっていたチェズレイの父は、他ならぬそのチェズレイによって破滅に追いやられ、彼の組織は崩落していった。しかし多くの傘下組織はチェズレイの父から与えられていた資金の供給が断たれただけで、組織そのものが崩れたわけではなかった。ほとんどの傘下組織は結局資金不足に陥り消滅したが、それでもいくつかの組織は未だに残り続けている。ターゲットであるこの貿易会社——『DF貿易』も、数少ない生き残りのうちのひとつだった。
DF貿易の社長はチェズレイの異母兄弟であるウルージカという男で、十歳以上離れているらしくチェズレイよりもモクマの方が年齢が近い。ウルージカは特にこれといって秀でた面もなく、ある程度成長した時点で使えないと判断されたのか、十歳になるころには父に捨てられていたようだった。兄弟たちの間でも話題に上がることもなく、チェズレイもDF貿易を調べていく中で初めて彼の存在を知ったほどだった。それほど忘れ去られていたウルージカだが、忘れられていたからこそ組織崩壊後に注目されず、バラバラになった傘下組織の残骸をDF貿易に集約でき、表向きは電化製品の輸入貿易会社として、そして裏では武器や兵器を取り扱う武器商人としての地位を築き上げることができた。
だが結局は傘下組織のかき集めでしかなく、勢力は父の組織と比べればほんのひと握り程度でしかなかった。ウルージカ自身も高みを目指しているというよりは、兄弟たちを出し抜いて父の負の遺産をいいように利用したかっただけのように思われた。
大手の武器商人なら他にいくらでも居る。チェズレイもモクマも、DF貿易のような小規模な組織をいちいち狙うほど暇ではない。しかし、ヴィンウェイで開発された最新化学兵器をハスマリーに売ったとなれば話は別だった。
『ルーク』の故郷、祖国であるハスマリーに新たな脅威が持ち込まれたと知り、チェズレイとモクマは入手ルートを特定するべくハスマリーやヴィンウェイを駆け回った。ようやく見えてきた商売相手が、一度も会ったことのない異母兄弟だと知った時、チェズレイはどうしようもない吐き気がこみ上げてくるのを感じた。いや、実際に吐いてしまった。
父を破滅させることで因縁を断ち切り、母の濁りと愛を受けとめ、家族という楔から解放されたとばかり思っていた。しかし、父が遺した異母兄弟たちがまだこの世にはびこっているのだ。顔も知らない、会ったこともない、半分は自分と同じ血が混じっている兄弟がこの世には居るのだと。気持ち悪くて仕方がなかった。憤慨、嫌悪、憎悪、ありとあらゆる負の感情がチェズレイの心に押し寄せてきた。
全てを消し去りたいと、血脈による繋がりを排除してしまいたいと強く願った瞬間、モクマがチェズレイの肩にそっと手を置いた。吐き散らかして、取り乱して、髪もボサボサに乱れた状態のままのチェズレイを、モクマはじっと眺めた。
俺が居るよ。彼はそう言った。それだけを言って、あとは黙ったまま汚れた床を掃除し始めた。モクマに促されてキッチンで口をゆすいだチェズレイは、じわりと浮かんでくる涙の存在に気がついた。勢いよくすがりつくように抱きつき、静かに肩を震わせて涙を零し始めても、その小柄な男はただ黙ってチェズレイを抱きしめ続けた。
兄弟たちは愛を知っているだろうか。手術室の前で待ち続ける苦しみを、愛しい者に名前を呼ばれる喜びを知っているだろうか。
愛とは、ひとりでは決して飲むことのなかった酒を飲むこと。愛とは、危険を顧みずビルから飛び出すこと。それを知る私は、なんと贅沢なことか。
DF貿易に乗り込む際、普段のように催眠は使わないとチェズレイが提案したとき、モクマはたいして驚きもせず二つ返事で了承した。ウルージカと直接話がしたいというチェズレイの想いを汲み取ってくれたのだろう。ハスマリーに兵器を売ったのは許されないことだが、だからといってこちらを認識させないまま警察に突き出そうという気にはなれなかった。チェズレイはDF貿易に向かう途中、頭の中でウルージカにどう話せばいいのか繰り返し考えていた。結局、考えがまとまる前に目的地に到着してしまった。
「チェズレイ」
偵察を終えたモクマが、玄関口の隅に隠れているチェズレイの元へ戻ってきた。小走りで向かってきているというのに足音ひとつ立てていない。
「駄目だ、みんな死んでる」
「そうですか」
想定内の報告に、チェズレイは落ち着いて返事をした。ウルージカと話す機会が失われたことに対して残念だと思う反面、少しだけ安堵している自分も居る。
「ウルージカのやつ、部下を殺したあとに自殺したみたいなんだが……どうもそう思えなくてさ。現場、あんまり見れたモンじゃないけどちょっと見てくれる?」
「もちろんですよ」
見て欲しいとモクマが言うのなら、おそらく今のところは敵の気配もないのだろう。チェズレイは立ち上がり、建物の奥へと歩くモクマの後ろをついていった。
玄関からまっすぐ進み突き当たりの扉を開けると、むわっと血の臭いが中から飛び出してきた。社長室へと続く廊下の途中で、おそらく銃で撃たれた従業員たちがぽつりぽつりと倒れているのが見える。社長室の前は特に死体が多く、ウルージカのボディガードであろう体格の良いスーツの男たちも転がっていた。
既に開いている社長室の入り口の前に立つと、黒々とした革の椅子に腰掛けるウルージカがよく見えた。銃口を自らの口に入れ発砲したと思われる状態でぐったりと背もたれによりかかっている。
「他殺ですね。自殺にしては体勢がおかしい」
チェズレイはウルージカの側まで歩み寄ると、社長室には入らず入り口の前で待機しているモクマに言い放った。
「ほー、言い切るね」
「銃を咥えて自殺してもらったことがあるんですよ。こういう体勢で死ぬことはまずありません」
チェズレイはウルージカの首の角度や、だらりと下がった腕、腰掛けている位置をまじまじと観察した。おそらく口に銃を押し込んでから殺した後、自殺に見せかけようと動かしたのだろう。以前自殺させたときの経験が今に活きている。
「幻滅しました?」
チェズレイはモクマに向かって妖しげに微笑んで見せた。不殺の契りがあるとはいえ、それはモクマと出会ってから結ばれたものであり、それ以前のチェズレイは下衆な連中だと判断すれば殺すことも厭わない人間だった。
「いんや、そういうのをさせないためにおじさんが居るんだから」
でしょ? と首を傾げてモクマが答えた。かつて殺人を厭わない人間であったことを受け入れているからなのか、それともそのくらいやっているかもしれないと予想していたのか、モクマは眉ひとつ動かさずチェズレイの話を聞いていた。出会ったばかりの頃は突けば突いただけ面白い反応を示してくれていたというのに、近頃は何をやっても落ち着いた姿勢を崩すことがない。つまらない、という感情が浮かんでくると同時に、頼もしいという想いも浮かんでくる。
「モクマさんはなぜ自殺に見えないと思ったのですか? あなたもこういう死体を見るのは初めてではない、とか……」
「まさか。なんとなくだよ」
モクマは茶化すように両手を広げた。
「ウルージカのやつ汗ひとつかいちゃいないだろ? いろいろ調べたけど、人を撃ち殺すのも自分の口に銃をブチ込むのも淡々とこなせるような男には見えなかったんだよねえ」
「意外とそうでもないかもしれませんよ」
「ま、あくまで俺の想像さ。どんだけ覚悟してても銃を口に入れりゃ、冷や汗くらいかくでしょ」
開け放たれたドアの先に立つ隙のない男の顔に、一瞬影が落ちるのをチェズレイは見逃さなかった。腹の底から湧き上がってくる嗜虐心を感じながら、乾いた唇をぺろりと舐める。
「あァ、モクマさん……。もし本当にウルージカが自殺していたとして、引き金を引けなかった人間の経験を当てはめるのは、いささか短絡的ではありませんか?」
あなたは引けなかった。全身に大粒の汗を浮かべながら、死の恐怖にも、自ら命を絶つ背徳感にも勝てず、きっと手にした銃を眺めながら呆然と立ち尽くしたに違いない。
モクマはわずかに目を見開いただけで、ぼりぼりと頭を掻くとため息をつき、再び緊張感を身に纏わせた。
「揚げ足取らんといてよ。ま、お前さんの言う通りだけどさ」
そう言うと、モクマは足元の死体に目を向けた。ボディガードたちの体には何発も銃弾が撃ち込まれた形跡が残っている。
「それにしてもずいぶん雑な仕事だね。敵さんも手馴れてるって感じじゃなさそうだ」
「情報が少なすぎますね。他を漁ってみましょう。ここは特に重要なものは置いていないようですから」
チェズレイはウルージカの血の気が引いた顔をしばし眺め、彼の胸ポケットからスカーフを引き抜くとスカーフ越しに開いたままの瞼を閉じさせた。なぜこんなことをしようと思ったのか不可解だったが、特に原因を探ろうとは思わなかった。いくつかの死体を跨いでモクマの元までたどり着くと、タブレットを開いて事前に入手した社内の地図を確認した。
「異母兄弟っていっても意外と似てるもんだね」
だらしなく椅子に腰掛けるウルージカを一瞥したモクマが言った。チェズレイとウルージカはよく似ているというわけではないが、兄弟と言われれば頷ける程度には似通っていた。母似だと本人から聞かされていたモクマは、意外にも共通点のある顔立ちに素直に驚いている。
「……あの男はですね、母の顔しか見ていなかったのですよ」
「つまり?」
「私の母以外にも似た顔立ちの女を侍らせていたということでしょう」
「ははぁ……そりゃ……」
母は違えど、同じような印象の顔立ちならば自然と似る。物のように女を選ぶチェズレイの父に対し、モクマは軽蔑の意を隠さず顔を歪めた。
DF貿易のメインコンピュータや地下にあった倉庫を漁ったが、既にデータは抜き取られ倉庫内ももぬけの殻だった。ウルージカは密かにDF貿易を立て直したらしいが、どうにも後ろ盾かもしくはスポンサー等が居るようだ。チェズレイたちが嗅ぎつけたことで見限られたか、それとも商売相手であるヴィンウェイやハスマリーに消されるような何かをしでかしたのか。DF貿易内で得られた情報は少なく、これ以上ここに居ても無意味だろうと二人は判断した。
「チェズレイ、提案なんだけどさ」
地下の倉庫から地上に上がる階段を上っていると、ためらいがちにモクマが口を開いた。
「ここ、爆破しよう」
「……モクマさん。それはいくらなんでも目立ちすぎますよ」
モクマの突拍子もない提案にチェズレイは顔をしかめた。市街地から離れた立地とはいえ、建物を崩壊させれば何であろうと町の人間は気付くだろう。
「言いたいことは分かる。でもこれを放っておくのは嫌なんだ」
階段を上り終えると、あの死体で飾られた長い廊下が目の前に飛び込んできた。
「とりあえず敵の気配は無いが、いつ現れるか分からん。ひとりひとり埋葬してる暇はないのは明らかだ。それで」
「爆破、と」
「そう。炎も上がってくれりゃミカグラ式になる」
チェズレイは眉間を押さえた。今ここで何もせずに退却できれば、一般人にこの建物がどういうものか知られずに済むのだ。爆破でもすればメディアで騒がれるのは免れないだろう。しかし火葬も兼ねたいと言うモクマの瞳は力強く、こうなればどんなに押してもびくともしないのをチェズレイは知っていた。
「私たちがそこまでする理由は?」
呆れた様子を包み隠さず表に出しながらチェズレイはモクマに問うた。
「無い。自己満足だね」
「だったら……」
「このままじゃハエにたかられてウジが湧くかネズミに齧られるかでしょ。そんな最期は可哀想だ」
「爆風で吹き飛ぶのはいいんですか?」
「う〜ん、それを言われちゃうと何も言えないね。だから言ったでしょ、自己満足だって」
腕を組んで縮こまるモクマに顔を向けつつも、チェズレイの体はしっかりと出口の方角を向いている。
さっさと行きますよ、と言おうとした瞬間。
「俺はお前にそういう風に死んで朽ちて欲しくないって思うよ。だから見ず知らずの悪党相手だとしてもその信念を押し付けたい」
「私は生きていますし、転がっている悪党どもでもありませんが」
「だ〜か〜ら〜、その悪党どもにもそうやって死んで欲しくないって思ってくれてる人が居るかもしれないだろって話。お前だって俺がそんな風に死んだら嫌でしょ」
半ば拗ねたように唇を尖らせているがモクマの瞳には鋭い光が宿っていて、何ひとつ冗談ではないと、本気なのだということをチェズレイに訴えかけている。
しかし、チェズレイも引き下がるつもりはなかった。
「あなたは死にませんし何より私が死なせません。あなたと私の死はあなたと私のものであり、他人と共有するものではありません。彼らの死だってそうです」
しばらく二人は黙って睨み合いお互いの主張を通そうとしたが、先に沈黙を破ったのはモクマだった。肩の力を抜いて、はあ〜っと大きくため息をつく。
「悪いが引くつもりはないよっ!」
「あっ……モクマさん!」
モクマはひとこと吐き捨てると勢いよく体の向きを変え、建物の奥へと駆けていった。チェズレイは珍しく舌打ちをすると、モクマの背中を追いかけた。
「おやおやチェズレイさん。悪党どものことはどうでもいいんじゃなかったんですかい?」
先程とは打って変わって意地悪くにたりと広角を上げたモクマが、チェズレイを肩越しに眺めながら笑った。
「この……下衆が!」
死が二人を分かつまで、チェズレイが殺していい相手はモクマだけ。本当に誰も殺さずにいるのか、モクマはそれを監視し続ける。
一連托生。モクマが飛び出してしまえば、チェズレイはその後を追わざる得ない。もし万が一のことがあれば、死が二人を引き裂いてしまうかもしれないのだから見捨てることなどできない。それを分かって走り出したモクマの背を見つめながら、仕込み杖で貫いてやろうかとチェズレイは思った。
崩落が収まったDF貿易は、まだごうごうと黒い煙を吐き出し続けていた。恐怖や死をたっぷり含んだ黒煙が空を黒く染め上げている。少し離れた建物の屋上からDF貿易を見守っていた二人は、なんの音だと家から出てきた人々から見えないよう影に隠れていた。
煙の根元にはちらちらと鮮やかな赤が舞っているのが見えるので、モクマの望み通りミカグラ式の弔いにはなったようだった。モクマは満足しただろうか。
チェズレイは東洋の龍を思わせる黒煙を仰ぎ見た。その大きな龍はこの一帯全てを喰らいつくしてしまうほど大きく、なぜか途方もない無力感が体中に満ちていくのを感じた。
おそらくウルージカの背後には、実体の見えない敵がまだ潜んでいるのだろう。ようやくハスマリーに運ばれた兵器の足取りが掴めると思っていたが、まだまだ先は長そうだ。
黒煙。ウルージカだったもの。従業員だったもの。ボディガードだったもの。その全てを黒に染め上げ、空へと運んでいくもの。塵となった人間がそこら中に散らばっているのかと思うと、喉の奥から胃液が込み上げてくる気がした。慌ててスカーフを取り出して鼻と口元を押さえたチェズレイを見て、モクマはそろそろここを離れようと提案した。
人間だったものは空へ舞い上がり、やがてその塵が雲を生み出し、この大地に雨となって降り注ぐ。
「ミカグラ式……どうにも度し難いですねェ……」
現場から離れてもなお顔色が悪いチェズレイが、モクマに向かって言い放った。「ごめんて」とモクマは眉尻を下げて謝る。
「俺のわがままに付き合わせちまって悪いね」
「ほんとですよ……」
チェズレイの血の気が引ききった白い頰に、モクマはそっと手を添えた。
「でもおじさんが死んじまったときはミカグラ式で頼むよ」
「……馬鹿なことを言わないでください」
分厚い胸板に一撃をお見舞いしてやろうとチェズレイは拳を握りしめ振りかざしたが、殴る気にもなれず結局弱々しく拳をモクマの頭の上にぽんと乗せただけになってしまった。モクマはその頭上の拳を掴んで自分の方へ引き寄せると、バランスを崩して傾いたチェズレイの体を強く抱き寄せた。チェズレイもかすかに震える指先でモクマの体を抱きしめた。
黒い龍が見下ろす中、二人はしばらく抱きしめ合い、互いの体温を確かめ合った。