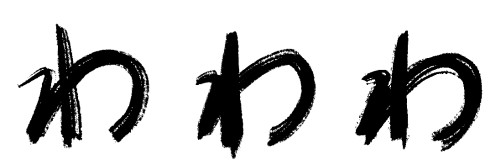騒音と共に通り過ぎるのは小ぶりなスノーモービルだった。昨晩降り積もったであろうサラサラとした粉雪がスノーモービルが通るたびに巻き上げられ、きらきらと輝く白煙を作り出していた。辺り一帯に轟くエンジン音は堆積した雪に吸い込まれ、思っていたよりずっと静かだった。いや、おそらくかなりの轟音なのだろうが、見渡す限り白銀の世界で人どころか動物すらあまり見かけないこの場所で、騒音問題を気にするのは馬鹿げているだろう。ぽつぽつと点在する雪に覆われた針葉樹の間を通り抜けながら、チェズレイはスノーモービルを運転するモクマに抱きついている力を少し強め、まるで世界にふたりだけのようだと思った。
「あそこ、見てよ」
突然失速して停車させたモクマが遠くを指差した先には、不自然に雪が降り積もった楕円形の塊が見えた。モクマはスノーモービルから降りるとその塊に向かって歩き出し、チェズレイは乗車したまま荷台から双眼鏡を取り出した。
モクマは不自然な楕円形の雪の塊に分厚いグローブをはめた手を突っ込むと、何か固いものに触れたところでおもむろに手を左右に振り雪を払った。
「スノーモービルだ。壊れてるね、乗り捨てたみたいだよ」
自分たちが乗っているものよりもずいぶん古い型のようで、いつ壊れてもおかしくないものだったのだろう。
「ちゃんと手入れすりゃまだまだ現役だっただろうに。見てよチェズレイ、こりゃビンテージ物だ」
乗り捨てられたスノーモービルを餌に自分たちを釣っている連中がいないかどうか双眼鏡で辺りを探っているチェズレイは、モクマの呼びかけに対し彼に見向きもせず「そうですね」とだけ返した。チェズレイの冷めきった対応を気にする様子もなく、モクマはスノーモービルの元まで戻り再び走り出した。
チェズレイの祖国ヴィンウェイ。できることなら、あまりこの地を踏みたくはなかったが、巨大なドラッグ加工場を抱えるマフィアの存在を無視することはできなかった。
チェズレイとモクマにかかればこの程度のマフィアを吊るし上げるのは一瞬だった。幹部たちを洗脳させ加工場の場所を吐かせ警察に突き出す。いつものように順調に仕事をこなしていた——はずだった。マフィアたちも一筋縄ではいかない連中だったのだ。
チェズレイたちが乗り込む直前に、幹部のうちのひとりがドラッグのレシピや加工場の設計図、そして大金を持って逃亡。中央から遠く離れたこの国境付近の山岳地帯に、伯父を頼って逃げ込んだというのが後から発覚した。険しい山々に囲まれ、隣国からの移民が住まうこの土地は外界からの侵入を防ぐのにちょうどよかった。祖国といえど、チェズレイですらこの過酷な土地を訪れたことはなかった。
遥か遠方に、ぽつんと山小屋が建っているのが見えた。あたりが拓けているから近くにあるように錯覚するが、まだ何kmも先だろう。モクマはスノーモービルを停車させると、木々の間に隠した。
「どこの景色も似て見えるねえ。こいつの場所を忘れないようにしないと」
モクマは荷台から計器を取り出すと、現在の緯度と経度を確認した。計器に表示された数字を数秒凝視すると、すぐにそれをしまいこむ。ほんの数秒眺めただけだというのに、モクマは全てを暗記してみせる。本人いわく忍びなら誰でもできるらしいが、チェズレイはその通りとは思えなかった。彼の超越した身体能力と記憶力は、相棒となってしばらく経った今でも驚かされることばかりだった。
ふと、モクマが山小屋とは逆方向に顔を向けて遥か彼方まで広がる雪原を眺めた。
「綺麗だねえ。いろんな国を見て周ったけどこんなに綺麗な景色なかなか見たことないよ。ヴィンウェイが好きになっちゃったなあ」
「見た目に惑わされてはいけませんよ。数多の生物が命を落とした死の山です」
寒さが厳しいと言われるヴィンウェイでも最北端にほど近いこの山岳地帯は、標高も高いのも手伝って氷点下三十度まで気温が下がることもあるという。今ふたりはネックウォーマーやマフラーを何重にも重ねて口元を覆っているが、それがない状態で大きく深呼吸をすることがあれば、たちまち肺が凍ってしまい数分も経たず命を落とすことになるだろう。
この山岳地帯は、ナイフのような鋭さを秘めている冷えきった大気で覆われている。この雪の下には、いったいどれだけの死体が埋まっているというのだろう。
「きっと死を孕んでいるから美しいんだ」
遠くを見つめたまま、モクマが呟いた。
「死の気配に誘われているだけなのでは?」
チェズレイは、かつて死に場所を探していた男の顔を眺めた。口元はネックウォーマーに覆われ、目元は暗めの色のゴーグルですっかり隠れてしまっている。何を思っているのだろう。チェズレイ自身もモクマと同じような格好をしているので、もしかしたら目の前の男も同じように考えているのかもしれないと思うとなんだか面白く感じた。
「初めはそうだったと思うよ。でも、今は違う。ただ好きな景色のうちのひとつに雪景色があるってだけ。そこに死を見出してるわけじゃない」
表情は見えないが、落ち着いた、穏やかな声で語る。
「自然ってのは本当に生き物に無関心だ。こんなにも恐ろしい場所なのにこんなにも美しい。生き物を簡単に殺す力を持っているのに、人々の心を強く揺さぶる美しさがそこにあるんだ」
そしてチェズレイの方を向いて——ゴーグルとネックウォーマーに隠れていて見えないがおそらく——微笑んだ。
「ま、この景色が特別だと感じるのは、お前さんが居るからかな。俺ひとりじゃこんなとこ絶対来なかったよ」
見えていないと分かっていて、チェズレイも微笑んだ。
「それはこちらの台詞ですよ、モクマさん。私ひとりではこんな場所にまで足を運んで組織の残りカスを掃除しようとは思わなかったでしょう」
モクマが再び顔を雪景色に向けると、チェズレイも同じように白銀の世界を眺めた。先程と何ひとつ変わらない景色なはずなのに、何故か、何かが劇的に変化したような確信めいたものが胸いっぱいに広がっていくのを感じた。自分でもよく分からないが、生まれて初めて、ヴィンウェイの景色というものを眺めた気がした。
ここに来る途中、各地に点在する移民の集落があった。遥か昔、隣国から渡ってきた移民たちはヴィンウェイに助けを求めたが、当時戦争や財政難を抱え我が国だけで手一杯だった政府は彼らに手を差し伸べることはなかった。
この山岳地帯は、ヴィンウェイであってヴィンウェイではない。あまりにも過酷な場所ゆえに、政府の介入がほとんどないのだ。税金を納めなかったとしてもわざわざ取り立てに来ることはない。祖国にも居られず、この国にも助けてもらえず、この極寒の地が彼らの居場所となった。やがて彼らは凍てつく大地との付き合い方を覚え、独自の文化を築き上げた。
祖国の紛争が終わっても、彼らは帰らなかった。祖国の力もヴィンウェイの力も借りず生き抜いた自分たちの力を信じて。生きることを否定するこの土地を故郷と呼んだ。
ああ、なるほど。チェズレイは心の中で呟いた。
彼らにとってのこの山岳地帯が、己にとってのモクマなのだ。
「さあて、ひと仕事しますかね」
綺麗だと言いながら雪原を眺めるモクマの瞳は、ゴーグルに遮られ全くと言っていいほど見えなかった。チェズレイはその瞳を拝めなかったことに対して、目頭が熱くなるようなもどかしさを覚えた。