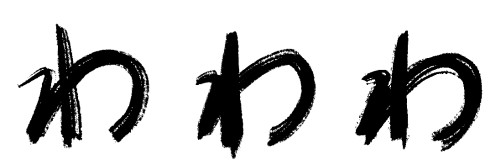三十年ほど前、この国は今より随分静かだったらしい。ただ今がうるさすぎるだけで、以前から小競り合いは絶えず起こっていて、他の国々と比べたら騒がしかったのだと思う。
きっかけはなんだったのだろう。それを明確に答えられる人などいるのだろうか。
政府軍は何のために戦っているのだろう。解放軍は何のために戦っているのだろう。
アーロンにとって、彼らの戦う理由などどうでもよかった。全部全部、どうでもよかった。
望むのは、たったひとつのこと。
ズン、と大地が揺れた。遅れて遠くで——だが、さほど遠くない場所と思われた——銃声が鳴り響いた。
「こっちだ、ついてこい!」
アーロンは歩くスピードが遅い子供たちを数人抱え込み、抱えきれない子供には叫んで指示を出した。五十メートルほど走った先には半壊した家屋があり、瓦礫の下には地下倉庫の入り口のようなものが見えた。抱えていた子供たちを降ろすと、アーロンは瓦礫を静かに、しかし素早く動かし、地下倉庫の安全を確認すると子供たち全員を中へ押し込んだ。
「いいか、三時間経ってもオレが戻らなかったらここから出て家に帰るんだ」
子供たちの中でも特に幼いエミールが、今にも泣きそうな顔でアーロンを見る。
「アーロンはどうするの?」
「心配すんな、すぐ戻る」
ぐしゃぐしゃとエミールの頭を撫でると地下倉庫を飛び出し、子供たちの力でも開けられるくらいの量の瓦礫を扉の上に乗せ直した。
避難させている間にすっかり銃声は鳴り止んでいたが、まだ油断はできない。アーロンは口の中で小さく舌打ちをした。最近、戦線は南下していてこの辺りで兵士を見かけることはなくなっていた。だからこそ、今日は少し先のキャンプに居るアラナの知り合いのところまで出かけたのだ。珍しくチョコレートが手に入ったというから、子供たちを連れていった。
最近『家族』になったばかりのエミールは誰よりも臆病で、アーロンの武器である鉤爪でも怖がるものだから、仕方なく荷物の底に入れて持ち歩いていた。そこにあの銃声。アーロンは荷物を放り投げ、子供たちを抱えて逃げることに全力を注いでしまった。おかげで今は手元に武器は無く、丸腰同然だった。(丸腰でも十分アーロンは強かったが、やはり手に馴染んでいる武器があるのと無いのでは少しだけ心持ちが違う)
子供たちを危険に晒してしまったこと。武器を手元に置いておかなかったこと。今日のありとあらゆる己の迂闊さに、アーロンは吐き気に似た嫌悪感を覚えた。
中腰の姿勢で足音を立てずに進むと、先程の銃声の発生源だと思われる場所にたどり着いた。五、六人ほど死体が転がっている。
(政府軍の格好じゃねえな。解放軍の民兵か)
おそらくゲリラ兵だ。おおかた、政府軍に対する奇襲を考えて潜伏していたところ、あちら側に情報が漏れ襲撃されたのだろう。はた迷惑な話だ、とアーロンは思った。
あまり乗り気ではなかったが、アーロンは死体からアサルトライフルを拾い上げて構えた。撃つつもりは毛頭ないが、ここ最近停戦させようと活動する中で、こちらが武器を持っているか持っていないかで相手の反応が大きく変わることを知った。酷く動揺していたり、パニック状態ではない限り、こちらが銃を持っていると知ると睨み合いになるのがお決まりだ。
そういうわけで、アーロンは牽制用として銃を構えながら辺りにまだ兵士が居ないか見て回った。
もう政府軍は居ないようだ。周囲の安全を確認し終えると、アーロンは砂埃が充満する淀んだ空気を精一杯吸い込み息を整えた。額に滲んだ脂汗を軽く拭うと、銃を死体の脇に置き捨てて子供たちのもとへ向かおうと体の向きを変えた。——その瞬間。
「…………う」
ハッとして顔を上げた。うめき声が耳に入ってきた。
アーロンは捨てたはずの銃を拾い上げるとすかさず構え、声がした方向に銃口を向けた。
本能に身を任せて動いたが、銃口が向いた先は床に転がっていた民兵のうちのひとりだった。自分で向けておいて、目標物が意外なもので目を丸くする。
「こいつ、まだ生きてんのか?」
民兵に駆け寄って脈を確認すると、弱々しいがまだ死神が迎えに来ていないことを教えてくれた。もしや、と思って周囲の民兵全員の脈を確認したが、息絶えていないのはうめき声を上げたこの民兵ただひとりだけだった。
正直言って、アーロンは見捨てようと思っていた。いや、今も見捨てようと思っている、というのが正しい。
「クソッ……ふざけんな!」
だが体が勝手に民兵を担ぎ上げていた。傷は決して浅くないが、今すぐアジトに戻って手当をすれば一命は取り留められるかもしれない。そう思うと、勝手に体が動いていた。
あいつならきっとこうするだろう。そう思いながら。
アラナの手当を受けた民兵は、三日三晩傷の痛みと高熱にうなされながらもどうにか峠を越えた。朦朧としていた意識は次第にはっきりとしてきて、アジトに担ぎ込まれて四日目、ようやく民兵はまともに喋られるようになった。
「なんと礼を言えばいいか……」
「いいのいいの、別にお礼を言って欲しくて助けたわけじゃないんだから」
アラナの快活な笑顔を見て民兵は表情を和らげたが、ドアに寄りかかりながら半ば睨むようにこちらを見ているアーロンに気付き、再び表情を固くした。
「アーロン、そんな顔しないの。怖がってるじゃない」
「はっ、軍人がこんなんでビビるかよ」
トゲトゲしいアーロンの対応にアラナはため息をつくと、誰に対してもどんなときもあんな感じだから気にしないで、と声をかけた。
「名前、聞いてなかったね。あたしはアラナ。んでこっちはアーロン。子供たちは……顔を見せながら説明した方がいいかな。あとで教えるよ」
「俺はウィリアム。……ウィリアム・ブラウンだ」
遠い国で働く相棒のことを連想させる名前に、アーロンは思わず舌打ちをした。
「政府側に見つからずに済んでよかった……」
ウィリアムがそう呟くと、アーロンは低い声で反論した。
「言っとくがオレらは政府側でもなけりゃ民兵側でもねえ。勘違いすんな」
政府軍も解放軍も、どちらにも属さない、どちらの勝ち負けも望んでいない、ただ銃声が爆撃音が響かない日常を望んでいるだけの人間が居ると、想像したことなどあるのだろうか。
「外から来たのか」
ウィリアムの肌は日に焼けているがそれでも白く、本人もしくは祖父母や親が、ハスマリーのような日差しが強い地域の生まれではないということを示していた。
「答えろ!」
「アーロン、落ち着きな」
病み上がりでまだぼんやりとしているウィリアムの首元を掴み、アーロンは返答を促した。間にアラナが入り、手を離すよう目で訴えかける。
「そうだ……俺はヴィンウェイ出身だ」
これまた偶然というべきか、極北の地の名前によって思い出されるむかつく顔に、アーロンの機嫌は更に悪くなる一方だった。相棒と気にくわない詐欺師ばかりを思い出すのは何だか癪だったので、ウィリアムを一瞥して壮年の忍者を彷彿とさせる要素がないか確かめたが、年は自分より少しばかり上だと思われるし、ヴィンウェイ出身ということも納得できる髪と肌の色素の薄さ、軍人らしい大柄な体格と、そう都合よくいかなかった。
「解放軍に雇われたんだ。元々ヴィンウェイで軍に入っていたんだが怪我が原因で退役した」
アラナは眉をひそめた。
「退役軍人なの? じゃあなんでハスマリーなんかに」
「俺はまだ戦える!」
今までの弱々しい声と打って変わって、力強い、怒鳴るような声で言った。
「退役するほどの怪我じゃなかった。俺の所属していた隊の隊長が上司と揉めたらしくて、どうでもいい理由をつけられて隊員のほとんどが辞めさせられたんだ」
怒りのあまり拳を握りしめて震えるウィリアムを、アーロンは変わらず睨むように眺めていた。
「だからってハスマリーに来てまで軍人でいなくたっていいじゃない。ヴィンウェイで新しい仕事を探せばよかったのに」
「あんたに何が分かる」
ウィリアムの青い瞳が、ぎらりと光った。その鋭さにアラナは一瞬たじろいだように見えたが、それを表情には出さずまっすぐとウィリアムを見つめた。
「父も祖父も軍人だった。だから俺は幼い頃から軍に入るよう言われて育ったんだ。退役が決まった時は……実は嬉しかったんだよ。軍人になんかなりたくなかったから」
怒鳴った時は怒りや憤り、そういった感情が顔に張り付いていたが、話すうちにだんだんと恐怖のような色が滲み出てきた。怒りに震えていた拳が、今は恐れからくる震えに変わっている。
「毎晩、毎晩、夢に見るんだ。作戦中に死んだ仲間が。退役して普通に暮らしていた俺を見てくるんだよ。俺は、俺は戦わなきゃならないんだ。銃を持って、敵を前にして、戦わなきゃいけないんだ」
ようやくアーロンは眉間の皺を緩めた。途方もない虚無感が胸に押し寄せてくるように感じた。
「分からねえよ」
睨むこともなく、だからといって微笑むこともなく、ただ何の表情も浮かべないまま、アーロンはウィリアムに言葉を投げた。
「てめえのことなんかオレらが分かるわけねえだろ。だからオレらのこともてめえは分からねえ」
アーロンはウィリアムに背を向けてドアノブに手をかけた。
「オレたちはただ故郷に居たいだけだ。なのにそれがクソほど難しい」
肩越しにちらりとウィリアムを見ると、アーロンを見ようとしてはいるものの、壁や床に視線を移してきょろきょろとしているのが見えた。
「てめえの仲間はどうやって死んだ? オレの家族たちは銃に撃たれ、爆撃に吹き飛ばされて千切れ、飢えて死んでいった」
アーロンは近くの壁を叩いた。壊れないよう力の加減をしつつも、なるべく大きな音が出るように叩いた。
やっとウィリアムの視線がこちらに向いた。
「助けてやったその命をもう一度戦争に使うならオレが殺す」
そう言うと、アーロンは苛立ちを隠すことなくドアを開けて勢いよく閉めた。
二日後、ウィリアムはアジトを出て、解放軍のキャンプに戻ることを決めた。まだ傷は深く、足元がふらついているのでアラナは止めようとしたが、キャンプの方が適切な治療が受けられるから、と説得したようだった。
アラナや子供たちが見送りをしているずっと後ろの方でアーロンはその様子を眺めていた。あれから一言も会話していない。どんな気持ちでキャンプに戻るのか、アーロンは知らないままだ。このまま行かせていいのか決めかねている。
「アーロン」
ウィリアムが声を張って名前を呼んだ。
「あ?」
まだ傷が痛むのか、ウィリアムの顔色は悪く、額には汗が滲んでいる。どう見たって動いていい状態じゃない。
くそ。
「おい、キャンプはどの辺だ」
「えっ」
ウィリアムのそばまで近寄ると、アーロンはウィリアムの荷物を担いだ。
「行ってくる」
アラナに声をかけると、
「了解」
素直じゃないんだから、という姉の言葉は聞かなかったことにして歩き始めた。
「……」
何か言いたげなウィリアムの顔色を一瞬だけ伺ったアーロンは、先導するように二メートルほど前を歩いた。
「別に死んでほしいわけじゃねえ」
前を向いたまま口を開いた。アラナが必死になって繋ぎとめた命を無駄にしてもらっては困る。殺すだなんだと吐き捨てたが、命を粗末にするつもりはない。
「アーロン、あんたに会えてよかったよ」
弱々しい声だったが、正面のアーロンに向かってウィリアムは話し始めた。目を逸らさずアーロンの後頭部に言葉を投げかける。
「俺は、熱で意識が朦朧としているとき、思ってたんだ。なんで俺が生き残ったんだろうって。皆と死ねればよかったのかもしれないって」
アーロンは振り向かなかった。ただただ、前を向いて歩き続けた。
「でもアーロンに助けられて、俺は今生きてる。他の人じゃない、俺が生き残ったんだ」
ウィリアムの足音が止まった。仕方なくアーロンは振り向いてウィリアムを確認すると、やっとこっち見てくれたな、とニヤリと笑う顔が良く見えた。なぜだか舌打ちする気も起きなかった。
「生き残った意味を考えてみようと思う。アラナやアーロンに助けられた意味を」
ウィリアムの青い瞳が真っ直ぐアーロンの瞳を見つめていた。顔色は悪く、足元もおぼつかない。それでもウィリアムは歩こうとしている。前に、前に。
「俺にできることを精一杯やってみるよ。これが俺なりの恩返しだ」
そう言うと、傷の痛みを堪えながらウィリアムは再び歩き始めた。立ち止まっていたアーロンの横を通り過ぎ、まだまだ遥か彼方にあるキャンプに向かって一歩一歩確実に歩いている。
ふた呼吸ほど時間をおいてアーロンも再び歩き始めた。今度はふらつくウィリアムの右隣りに並んで。
キャンプの影が見えてきたあたりでウィリアムが「ここまででいい」と言うまで、ふたりは一切会話をしなかった。
「気をつけろよ」
去り際にアーロンが言い放った言葉に、ウィリアムは口の端を緩ませた。
「ありがとう」
アーロンから荷物を受け取り、あんたたちのことは何も報告しないから安心してくれ、と言った。何がどう安心できるのか分からないと思いながらアーロンは適当に相槌を返した。
オレも、ありがとう、と言うべきなのだろうと思った。オレたちの行為に、こいつは誠心誠意応えようとしている。それに対して感謝をするべきなのだろうと思った。
だが、アーロンの口は固く閉ざされたままだった。キャンプに向かって歩いているウィリアムの背中を眺めながら、結局何ひとつ声をかけることも出来ず、ただ後ろ姿を眺めていた。
あいつのように、純粋に人を信じられたらどれだけいいだろう。きっとあいつだったら、ありがとう、だの、また会えるといいですね、だの、そういう台詞がぽんぽん出てくるに違いない。
安心してくれ、とウィリアムは言った。それを信頼して安心できるほど、ハスマリーは、人間は、単純じゃない。
アーロンは静かに息を吸うと、長いため息をついた。
安心したい。一瞬でもいい。家族と共に暮らすこの故郷で安心できる環境が欲しい。
それだけなのに、どうしてこんなにも難しいのだろう。
一週間後、ウィリアムの居るキャンプの付近まで向かったアーロンは絶句した。キャンプは爆撃され、無惨な姿を晒していた。
「なっ…………」
アーロンは立ち尽くした。残骸を漁ってウィリアムを探す気になれなかったし、何より想像もしていなかった惨劇を前に頭が真っ白になってしまっていた。なぜだ、なにが起きたんだ、そういう疑問がアーロンの脳内を駆け巡り、どこか冷静な自分がどれだけ考えても答えは出ないだろ、と諭す。
政府軍の仕業だろうか。ウィリアムたちのゲリラ部隊も襲撃されていたから、本拠地であるこの場所も知られていてもおかしくはない。
「クソッ……」
それとも。
唐突に浮かんだ最悪な解釈に顔を歪める。
ウィリアムの恩返しが『これ』だとしたら? 解放軍の主要キャンプのひとつがこうなってしまえば、解放軍側は一旦立て直しをするまで引き下がるしかない。解放軍がある程度静かになってしまえば、政府軍も躍起になって攻撃することもない。
ハスマリーの紛争は互いの戦力が拮抗しているからこそ勝敗がつかず、相手の出方を伺っては奇襲をかけ、延々と戦争を繰り広げている。確かに、一方の戦力が大きく削がれれば勝敗が決まり、紛争は収まるかもしれない。
だがハスマリーの三十年ほど続いた紛争状態は、そんな単純なものではないだろう。
「…………」
アーロンはその場にしゃがみ込み、俯いて心を落ち着かせた。これがウィリアムの仕業というのはあくまで想像でしかなく、確証は何ひとつ無い。
でももし、本当だとしたら、オレがあいつを助けたことで、このキャンプの人間の命を奪う結果に繋がったということになる。
分からない。確証は無い。
どうすればよかったんだ、オレは。
ハスマリーに生きるとは、こういうことだ。ハスマリーの残酷さに揉まれても、ルークは純粋でいられたのだろうか。オレだから、こんなになっちまったんだろうか。
心が弱っている気がして、アーロンは首を振った。
どうしようもなくルークの声が聞きたくて仕方がなくなったが、アーロンはしばらくその場でしゃがみ込み俯き続けていた。