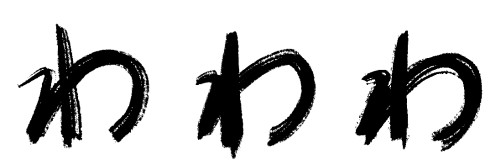見慣れた馴染み深い弁当の中身を見て、自分は何を思っただろう。城内の兵士に食われそうになったとき、脳裏に浮かんだのはなんだっただろう。
ここに来ると決めてからというもの、自分の感情を抑えてばかりだった。いざ自分の想いを見つめようとすると、なんだか少し離れた場所から自分の背中を見ているような、背中ばかりでどんな表情をしているのか分からないような感覚がした。おれは何がしたいんだ? 何を思っているんだ?
気が付けば走り出していた。あの場所に行かなければ、と背中を押された気がした。何が背中を押したのか分からないが、もはやそんなことどうでもよかった。
ジェルマも死ぬ。おれも死ぬ。こうするしかない。覚悟を決めた。
だったらこれが最後のチャンスだ。誰かに自分の飯を食って欲しかった。今更新しく作る余裕なんてないから、この弁当を食ってもらうしかない。
冷たい雨を頬に感じながら、ただひたすらに走った。あの場所へ、あの場所へ。どうか、最後だけでもおれをサニー号のコックだと感じさせて欲しい。帰りたかった場所の空気を思い出させて欲しい。せめてその空気を抱いて死にたい。
船長が居るはずの場所で、転がる人影をひとつひとつ確認する。お前じゃない、お前じゃないと確認するたびに舌打ちをしたくなった。顔を視認した人数が増えれば増えるほど、心の奥底でぼんやりとした重く暗い気持ちが広がっていくのを感じていた。
待ってくれやしないのだと。あんなことを言っていたけれど、もうとっくに見限られたのだと。誰も、誰ひとりとして自分を必要としてなんかくれないのだと。
手が止まった。ほんの僅かな救いを求めていた心が、ゆっくりと萎えていくのを感じた。今更何があるというのだろう。どうせ死ぬんだ。コックとしての、クルーとしての矜持に縋って何になるというのだろう。
弁当の入ったバスケットが、やけに重たく感じた。この手を離せば楽になるかもしれないと思った。自分は何から楽になりたいんだ? 何が苦しいんだ?
突如、雨音をかき消さんばかりの腹の虫の音が耳に届いた。音がした方を振り返ると、力無くだらりと座り込んだ船長が目に入る。
考えるよりも先にルフィの元へ歩き出した。
弁当を差し出し、食えるもんなら食えと口では言ったが、彼なら必ず食べてくれるだろうという確信があった。かつて母がぐちゃぐちゃになった弁当を食べてくれたように、ルフィもまた同じように食べてくれるだろうと。その瞬間の為に己はここまでやってきたのだから。
うまい、うまい、と弁当を貪るルフィの顔を見て、ああ、来てよかったと思った。本当ならばもっといいものを食わせてやりたかった。厨房で見かけた食材はどれも上等なものばかりだったから、手の込んだ料理にうってつけだろう。見たことのない野菜や魚もたくさんあった。ひとつずついろいろな調理法を試して、皆の口に合う食事を作ってやりたかった。
ああ、駄目だ。駄目だ。
「本心を言えよ!」
左頬に受けた拳など、無抵抗のルフィを蹴ったときに比べたら微塵も痛くなかった。駄目だ、駄目だ。
瞼の裏に焼きついて離れない情景が。耳の奥で響き続ける仲間の声が。魂に刻まれた料理人としての矜持が。海賊という生き様と夢を捨ててまでひとりの男が守った己の命が。
見えない振りをしていたもの全てが、大きな波となって胸に押し寄せる。押さえつけようとしても、みるみると膨れ上がり、涙となって瞳からこぼれ落ちた。己の根幹を支えてくれている想い、手離したくなかったたくさんのもの、逃げ出したいほどの恐怖、まるでこどものような我儘。
ここから、そしてジェルマから逃げられないと分かったその瞬間から、ずっとずっと飲み込んできた言葉があった。
「サニー号に……帰りたい……!」
そう思っては駄目だと、口に出したらもう二度と現実に向き合えなくなると、喉元にまでこみ上げてきたこの言葉を一体何度飲み込んできただろう。周囲の人間にも、そして仲間たちにも悟られまいと、必死で押し殺してきた。
たったひとりで抱え込んでいた想いが、次から次へと口からこぼれて出ていく。サニー号に帰りたい。あそこに戻りたい。だけど、なんの思い入れのない血の繋がった家族たちを見捨てられない。恨みしかないのに、むしろ死んでしまえと思ってすらいるのに、心のどこかでそう思いきれていない。でもどうしたらいいか分からない。
こんなの現実が見えてないこどもの駄々だ。それでもそう思わずにはいられなかった。笑われても構わない。決壊したダムのように、勢いよく流れてくる感情をそのまま吐き出した。
「……うん!」
船長の、そのたったひとつの相槌で、重くぐちゃぐちゃと胸のうちに渦巻いていた心がふっと軽くなった気がした。
「……だって、それがお前だろ!」
肉親に散々否定し続けられた自分にとって、必要なのはこの言葉だったんだ。そうだ、これがおれだ。雨に濡れて惨めに泣き喚いている情けねえ男が今のおれだ。
昔、姉に言われた言葉を思い出した。
——いつか必ず優しい人達に会えるから!
レイジュ、会えたよ。たくさんの優しい人達に。
おれは母に愛されていた。レイジュの優しさは同情からだったかもしれないが、その優しさに救われたのは事実だ。育ての親は、おれが心から父だと言える唯一の男は、不器用ながらもおれを愛してくれている。バラティエにいるときは、料理を通して様々な人に出会った。罵詈雑言が飛び交う場所ではあったが、感謝の言葉が全くなかったわけじゃない。何の縁か知らないが今は海賊として、麦わらの一味としてこの地に立っている。
立とう。自らの意思で。ジェルマの城を抜け出そうとした過去の自分の為に。泣きながら背を押してくれたあの日の姉の為に。自らの命を危険に晒してまで自分を産んでくれた母の為に。命を救い育ててくれた父の為に。自分を信じてくれている仲間の為に。
足掻け。命の限り。おれに与えられた優しさや愛に誇れる人間になれ。
「おれ達がいる! 式をブッ壊そう!」
笑顔の先に、瞳の先に光を見た。その光は明るく澄んだ海の色をしていた。