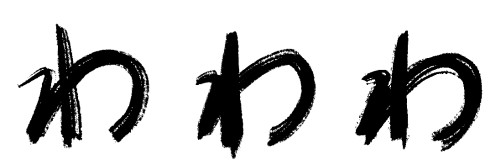在りし日の夕餉
水辺の、自分より背の高い葦が覆い茂ったところに飛び込んでいった幼馴染の名を呼ぶ。
「モクマ〜」
返事はない。
確かにこの目で葦原に潜る彼を見たはずなのに、なんだか本当なのかどうか分からなくなってきた。今日は風が強く葦をざあざあと横に振り回すので、モクマが動いて音がしているのか、風が弄んでいるのか、カンナには判断できなかった。
「ねえ、モクマぁ」
だんだん、帰ってしまおうか、という気持ちになる。モクマは居ないのかもしれない。日も傾いてきたし、薄暗い河川敷にひとりで居るのはどうにも寂しくて仕方がない。
「かえっちゃうからね」
そう言った途端、黒い塊が葦の間から飛び出してきた。
「あったよ」
ほら、とモクマが手を差し出す。そこには、見かけたことのある手ぬぐいが握られていた。
今朝ガコンの家に遊びに行ったとき、朝の強風で手ぬぐいが飛ばされてしまったとガチャンがぼやいていたのを思い出した。からくり師の親子は忙しそうだったから昼にはもう家を後にしたが、そういえば今日モクマはきょろきょろと辺りを見ていた気がする。河川敷を通ると一目散に葦原に突っ込むものだから、カンナは何が何だか分からず、ずっとモクマが出てくるのを待っていた。
ガチャン愛用の手ぬぐいだ。彼がいつも使っているのをふたりは良く見ていた。
「とっつあん、よろこぶかな」
達成感で顔を輝かせるモクマが、からくり師たちの家の方向に体を向ける。
「きっとよろこぶよ」
ふたりは土手を駆け上がり、少し人里離れた工房へと走り出した。
「こンの……馬鹿モンが!」
ガチャンの拳がモクマの頭頂部に吸い込まれていく。
ごつん、と鈍い音が家中に響き、カンナは思わず目を瞑った。ふた呼吸ほど置いて恐る恐る目を開けば、頭を押さえ床にうずくまっているモクマが目に入った。
へんなの。カンナは思った。あの程度の拳なら、モクマは余裕で避けられるだろうに。
「あの川は一昨日の雨で増水しとるんだぞ!」
山奥だから良かったものの、里の中央だったら三軒先まで届くであろう大きな声でガチャンが怒鳴る。
すると、大きく深呼吸したかと思えば、モクマの目線に合わせてしゃがみこんだ。怒鳴ったときの怒りは、もう無いように見えた。
「葦原なんぞに入りおって……知らぬうちに川に足を取られたらどうする。溺れ死んどったぞ、お前」
「……とっつあん」
「手ぬぐいなら、買い直しゃいい。そうだろ?」
モクマの肩をばしばしと叩くと、ガチャンは「どっこいせ」と年寄りみたいに言いながら立ち上がってその場を離れた。
「おいガコン、なんか食わせてやれ。そいで食い終わったら家まで送ってやれ。ワシはもうちょい工房にこもる」
そう言い放つとあっという間に工房に姿を消した。
「親父なりに心配してるんだ」
炊きたての米を茶碗によそいながら、呆れた様子でガコンが呟いた。モクマとカンナに茶碗を渡すと、次は囲炉裏にかけてある鍋から山菜汁をよそい始める。
「工具で殴られないだけマシだな」
山菜汁をよそい終えると三人は囲炉裏を囲んで座り、いただきます、と言って夕飯を食べ始めた。
「たんこぶになってないか?」
「へいき」
あんなに痛そうにしてたのに、とカンナは思った。モクマが葦原に入るのを止めなかった自分まで怒られるのではないかと思ったので、床にうずくまって痛みに耐えているモクマを見ながらカンナは必死で言い訳を考えていた。
「おカン、ごめん。つきあわせちゃって」
だからモクマに謝られたとき、カンナはどうにも居心地が悪い気持ちになった。一方的にモクマの所為にして逃げようとしていたのだから。
適当にはぐらかすか、という考えが浮かんだ瞬間、それよりもモクマに対する申し訳なさの方が膨れ上がり、カンナは山菜汁を飲む手を止めた。
「あやまるのは、あたしのほうさ。あたしもいっしょにおこられるんじゃないかって、モクマがとっつあんのゲンコツくらってたとき、どう言いわけしようかずっとかんがえてた……」
きょと、とモクマは目を丸くする。
「へんなの、おカンにつきあわせたのはおれなのに。おれのせいにしていいんだよ」
「よくないから、ごめんねって言いたかったんだって」
なんとなく気まずくなってカンナは山菜汁に目を向け、縮こまって俯いた。やけに家が静かだ。隣の工房の作業音が聞こえてくるほどだった。
そう、いつだって自分ばかり喋っているのだ。モクマもガコンも、決して言葉数が多いわけではない。そんなふたりに甘えて、自分は喋ってばかりいる。
「おカン」
沈黙を破ったのはモクマだった。
「ありがと……河川敷でずっと待っててくれて」
モクマの言葉に顔を上げると、力の抜けた笑みを浮かべこちらを向いていた。カンナも思わずつられて笑顔になる。
「なにかあったら、こんどはあたしの名前をよんで。あたしもたすけてあげるから」
「うん」
ふたりはお互いの瞳を眺めた。モクマの目には頼もしい力強い光が宿っている。しばらく見つめ合っていたが、どうにも面白おかしく思えてきて、ふたりとも声を上げて笑い始めた。
「笑うのはいいが、もう外はすっかり夜だぞ。早く食って早く帰る支度をしろ」
ガコンが微笑ましそうに眺めながらもふたりに注意をすると、はあいと元気よく返事をし、夕食を腹へ流し込んだ。
くちなしは語らず
よく晴れた空を眺めていた。雲ひとつない青空はひどく眩しくて鮮やかで、向かいの山の稜線をくっきりと描き出している。
城に呼び出され、用事を終えて帰路につく途中、カンナはどうしようもない疲労感を覚えて道端の岩に腰掛けた。同じく城に呼び出されていたガコンも、腰掛けるカンナを見て隣に座る。
カンナは手に持っていた巾着袋を膝に乗せ、中身のひとつをそっと取り出した。使い古された筆や硯などの筆記用具がまとめて入れてある。
視界がぼやけるのを感じた。目の調子が悪いとか、ゴミが入ったとか、そういうことではない。目のあたりが、ぎゅっと熱くなり、どんどん目の前の景色が歪んでいく。
「おカン……」
隣に座るガコンがカンナの背を撫でた。大きく無骨な手は普段より冷えきっていて、いつも感じられる頼もしさは無かった。
カンナは取り出した筆を握ったまま、大きな瞳から零れ出る涙を拭うことなく俯き続けた。
城に呼び出されたのは、これを受け取るためだった。
これは遺品だ。
王を殺したと噂された幼馴染は、島中を捜索してもついに見つけることは叶わず、とうとう主の後を追って海に身投げしたということにされたのだった。
宿舎に遺されたわずかな私物は、カンナとガコンに引き渡された。ふたりはそのわずかな遺品をそれぞれ受け取り、重い足取りで城を後にしたところだった。
カンナが涙を零すのは、幼馴染の死を嘆いているからではなかった。分からないのだ。何もかもが分からないのだ。どうしてこんなことになったのか、里の人間の誰ひとりとして説明できる者など居ない。
本当にモクマは王を殺したのだろうか。本当にモクマは身投げしたのだろうか。確かな答えは何も無い。
叫んで、怒り狂って、暴れたいと思っても、誰に怒ればいいのか分からず、どうしようもないもどかしさだけが宙ぶらりんになり、振り上げた拳は虚空を殴るほかない。
イズミ姫の流産、タンバ王の崩御、モクマの失踪。どれかひとつ取っても大事件だというのに、あろうことか全てが一気に押し寄せてきた。これには元気だけが取り柄だと豪語するカンナも、流石に憔悴し弱りきってしまっていた。
くやしい。そんな気持ちが浮かんでくる。
「どうしろっていうんだい……」
込み上げてくる嗚咽を必死でこらえ、喉から声を絞り出した。
「どうしろっていうんだい……!」
幼馴染の遺品を前に、自分は何をすればいいというのだろう。何も頼ってもらえなかった自分は、何もできなかった自分は、死んでいったもののためにこれから何をすべきだというのだろう。
「モクマの、ばかやろう! 帰ってこいったら!」
向かいの稜線に向かって叫んだ。
あんたは本当にタンバさまを殺したのかい。そんなことしないよね。そういう思いと、何故か頭の片隅には主殺しが事実なのだと納得する思いが同居している。
モクマは、多くを語らない。己を偽ることも、虚偽で塗り固められることも、全く厭わない。モクマの周りには常に事実と虚偽がぐちゃぐちゃに混ざりあっていて、何が本当で何が本当ではないのか、この里でモクマと共に居る時間が最も長かったと思われるカンナですら真偽を見抜くことはできなかった。
それでも確かなことがひとつだけあった。モクマは己がどれだけ傷付こうと、まるで他人事のように俯瞰して気にすることはなかったが、己の所為で誰かが傷付くことを何よりも嫌った。カンナやガコンが被害を被るような事件や事態になることは避けていた。
だからこそ。
「モクマの、ばかやろう」
とめどなく涙が溢れてくる。
幼馴染が姿を消した。罪をなすりつけられても甘んじて受け止める彼が。悪い噂が友人に降りかかる場合、どうにか回避しようとする彼が。
主殺しをした途端、自分たちを頼ることも、黙って己の罪だと受け止めることもせず、ただ姿を消したのだ。
カンナとガコンは何日も事情聴取を受けた。モクマに手を貸したのか、モクマを匿っているのではないかと。主殺しの友人だと、罵られたこともあった。
幸いなことに、ふたりはそういった罵詈雑言で心を痛めることはなかったし、事の発端であるその幼馴染と縁を切ろうという気持ちになることもなかった。
ふたりを何より打ちのめしたのは、何ひとつ事実が明らかになっていないというのに、この里が元通りになりつつあることだった。
タンバの崩御に伴い行われたフウガの即位式も、もう半年ほど前の出来事だった。つまり、モクマが姿を消してからそのくらい経ってしまっている。カンナとガコンを取り巻いていた主殺しの友人という評価も既に薄れ、以前と同じように接する人がほとんどになった。
カンナは袖で涙を拭うと、向かいの山に目を向けた。日が落ちてきたからか、ふたりの間を抜ける風が冷たい。
「帰ろう、冷えてきた」
ガコンが立ち上がり、カンナの肩をぽんぽんと軽く叩き立ち上がるのを促した。
「うん……」
取り出していた筆を巾着袋にしまうと、重い腰をゆっくりと上げた。
ふたりは一言も会話をすることなく、俯いて帰路を歩き続けた。足取りは重く、いつもより家までの道のりが随分遠いように思えた。
カンナは河川敷の横を通るとき、幼い頃はよくここでモクマと釣りをしていたな、というのを思い出し、引っ込んだはずの涙がまたじわりと滲んでくるのを感じた。もう泣いてやるものか、と心の中で呟くと上を向いて、もしモクマが帰ってきたら何と言ってやろうかと考え、とりあえず一発殴るか、と結論を出した。
サウダージ
「まったく……一体誰の差し金だい? ルーク? それともスイちゃんか?」
大正解。そう思いながらも、ガコンは口角をにやりと上げるだけでモクマの問いには答えなかった。隣に立ち並ぶカンナもガコンの心情を察したのか、同じようににやりと笑い珍しくだんまりをきめこんでいる。
扉から顔だけ出して、拗ねているような、恥ずかしがっているような表情をしているモクマは、黙ったままのふたりをじとっと睨みつけた。
「勘弁してよ……」
力なくため息をつくモクマを見て、ふたりは思わず声を上げて笑い出した。いつも冷静で落ち着いていた友人を翻弄するのは思いのほか面白い。すっかり白くなった頭髪を見れば、二十年いろいろと苦労したのだろうと推測できるが、こっちだってこいつの所為でいろいろと苦労した。このくらい遊んだって罰当たりにはならないだろう。
慣れない洋服に袖を通してみるものだな、とガコンは思った。
およそ一週間ほど前、避難所にルークとスイが訪れた。その時、ガコンはコズエとともにブロッサム開発事業担当者との会議に参加していたため、ふたりがどんな目的で訪れたのかは分からなかった。しかし会議が終わり、ふたりがコズエと少し話したと思うとガコンのところにやってきたのだった。
「ガコンさん。来週の土曜日って空いてますか?」
ルークはそう言うと、懐から長方形の紙を二枚取り出す。
「まあ、空いているが……」
モクマ経由で少し話したことがあるとはいえ、まさか自分に話しかけてくるとは微塵も思っていなかったガコンはたじろいだ。
「ねえガコンさん。ニンジャジャンって知ってる?」
「ニンジャジャン?」
「あはは、知らないよね。子供向けの、えーっと、舞台劇って言えばいいのかな」
タブレット端末を持ったスイが近付いて、ガコンにもよく見えるよう画面を傾けて見せた。
「これは……」
画面には忍者——ただし忍びというには随分と派手な装いだ——が映し出されていて、その下には一週間後の日付が書かれている。どうやら今度行われる舞台劇の詳細が書かれているらしい。
「モクマさんの今のお仕事なんですよ。都合が合えば……なんですけど、おカンさんと見に行ってみませんか?」
ルークの手には二枚のチケットが握られていた。本当はもっといろんな人に見に行って欲しいんですけど、二枚しか取れなかったんですよ、と苦笑する。
そういえば、この二十年は職を転々としていたと聞いただけで、詳細は聞いていなかったことを思い出した。この手のものが好きらしいルークが行くべきなのではと思い断ろうとしたが、無視できないほどの好奇心がそれの邪魔をした。
「決まり、ですね!」
屈託のない笑顔を浮かべたルークが、ガコンの手にチケットを乗せる。
あの、モクマが、子供向けの舞台劇で劇役者をしているんだぞ? 気にならないわけないだろう。
ガコンはルークとスイに礼を言うと足早にその場を去り、炊き出しの準備を始めようとしていたカンナのもとまで向かった。
「面白そうじゃないの!」
カンナは二つ返事で了承してくれた。
そんなわけで、ガコンはカンナとともにニンジャジャンショーを見に行ったのだった。目立たないよういつもの着物ではなく、ブロッサムらしく洋服を着て。
しかしさすがモクマと言うべきか、敵に襲われそうになった民の前に颯爽と現れた瞬間、そのニンジャジャンと呼ばれた忍びはこちらを向いてしばし固まった。司会者の呼びかけで我に帰ると、あとはこちらを気にすることなく舞台で演じきったのだった。
ニンジャジャンショーが終わると、ふたりはルークたちに言われた通り楽屋に足を運んだ。モクマは恥ずかしさからなのか楽屋の扉から顔を出すだけで、出てこようとはしなかった。
「なあに恥ずかしがってんのよ。ほら出てきなって」
ついにカンナに扉を開けられて、モクマはずるずるとガコンの前まで引きずり出された。劇が終わったばかりだからか、衣装の下に着ていたであろう黒いインナー姿だった。アクロバティックな演技も多かったので、まだ汗も引いていないようだ。
「来るなら言ってよ」
「言ったら面白くないでしょ」
わはは、とカンナの笑い声が辺りに響く。通路を歩く劇の関係者らしい人たちが、何事かとこちらを見るのでモクマは更に恥ずかしげに顔を赤くした。
「ちょっと着替えてくるから、えっと、あとみんなに挨拶して、そしたらどっかで茶でも飲もう。飯がまだなら飯でもいい」
「分かった、表で待っているとしよう」
「ちゃんと来なさいよ〜」
早く出てってくれと言わんばかりにモクマはふたりの体を無理矢理出口に向けさせた。しょうがない、とふたりは楽屋に背を向けて歩き出したが、遠くからわずかに聞こえてくるモクマと同僚のやりとりを聞いて顔を綻ばせた。
あの人たち誰? とか、お友達ですか? とか、そういう質問をされて慌てているのが聴こえてくる。モクマが以前言っていた「この二十年、悪いことばかりではなかった」というのは本当らしい。ずっと里に居たら、こんなモクマを見ることなどなかっただろう。
手早く着替えと挨拶を済ませたモクマが到着すると、三人は近場の定食屋に入り遅い昼飯を食べることにした。
「こうやって三人だけでご飯食べるなんて、随分久しぶりじゃないかい」
鯖の味噌煮を頬張るカンナがしみじみ言うと、そういえばそうだ、と男ふたりが呟いた。
「あたしとモクマが城仕えになってから三人で集まる機会が減っちゃったもんねえ。何年振りかしら。二十五年以上だったりして、あはは」
「おれもそのくらいの時期は工房にこもることが増えていたからな」
幼い頃は毎日のように同じ釜の飯を食べていたというのに、モクマが見習い忍者から一人前の忍者になって、ガコンにも仕事が来るようになって、カンナがイズミの世話係になって、たまに話すことはあったものの、三人で揃って何かをすることはほとんどなくなった。二十五年以上の空白があるというのに、こうして食卓を囲むとその空白を感じさせない空気になるのをガコンは感じ取った。随分と軽口が達者になったモクマだが、意識しているのか無意識なのかは分からないが、カンナとガコンの前では少しだけ昔の雰囲気を覗かせてくれる。
「あんたが劇役者だって聞いてたまげたよ、まったく。どんなもんかと思ったけど、板についてるじゃないか」
モクマは腹が減っているらしく、どーも、と軽く言うだけで白米やら唐揚げやらを次々と口に放り込んでいた。
「今度避難所でもやったらどうだい? 娯楽もないし、きっと子供たちも大喜びさ」
「ま、気が向いたら」
「前向きに検討してよ。みんな気丈に振舞ってるけど、結構まいっちまってるみたいだよ」
ふと箸を止めたモクマが、正面に座るカンナからその隣に座るガコンへと視線を移した。
「そういやルークから聞いたよ。マイカを模した場所を作るんだって? 忙しくなりそうだ」
「まあ、そこそこな」
ガコンはここ最近ブロッサム開発を担う事業の人たちとひっきりなしに会議を重ねていて、まだ全貌が決まっていない今の段階でもそれなりに忙しかった。今日のショーはいい息抜きになった。
「おカンはこれからどうするんだ」
「それがねえ、全然決まってないのよぉ。みんなこれから何をして生きていくかなんてな〜んも分かんなくてさ」
昔と変わらず、すっかり箸が止まっているカンナが、少しだけ身を乗り出した。
「ねえモクマ、あんたいろんな職業に就いたんでしょ? 里の人たちの相談役になっとくれよ。右も左も分かんない人たちばっかりだから、ちょいと経験談を話してくれるだけでも違うと思うのよね」
王族の子が王族であるように、からくり師の父を持つガコンがからくり師であるように、マイカの里において職業というのは基本的に生まれる前から決まっていた。忍びの家系、城仕えの家系、農家の家系。親の職種を継ぐことに、何ひとつ疑問を持つこと無く——いや、疑問を持つことは許されず——生まれる前から決まっている職を継いで、子を成して、その子供に職を継がせて、そうやって家というものを形作ってきた。
その文化も、里とともに崩壊した。
ブロッサムという新しい土地で、そこに合った職を見つけなくてはならない。自分の意思に関わらず出生前から与えられていたものを一から探す必要がある。おそらくブロッサムの人間で、この苦労が一体どれだけのものなのか理解できる人は居ないのだろう。
里の外には自由があった。決してマイカでは手に入れることのできない自由が。しかし自由とは、自分は何者で、何をしたいのか、何をしたくないのか、それをはっきり示す必要がある。
モクマはマイカの希望だった。里の外で長らく過ごした人間など彼の他に誰も居ないのだから。生きるために、何でもした。彼はそう言っていたが、里の者にはそれすら難しい。
「まあ、まだちょっとは島に居る予定だから、出来る限り避難所に足を運ぶようにするよ」
モクマの返しに、カンナとガコンは目を丸くした。一度お互い目を合わせ、またモクマを見る。
「俺、島を出るよ」
てっきり、彼はこれから島にずっと居てくれるものだと思っていたふたりは、モクマの言葉をうまく受け止めきれず、目をぱちくりとさせていた。
「やりたいことがあるんだ」
そう言って、笑みを浮かべた。
長らく見ていなかった、一切の曇りのない微笑みを。
「そうかい、たまには帰ってくるんだよ」
カンナはいつだってモクマが欲しいと思っている言葉をかけてくれる。本当のところは分からないが、ガコンはそう思っていた。
おれたちはどれだけ彼女の言葉に救われてきただろう。
おれはおカンのように適切な言葉を選べないが、お前がお前の好きなように人生を歩めるならば、それを応援したい。
「次帰ってきたら、きっと驚くぞ」
ガコンは自分の不器用さに苦笑した。それでも気持ちが伝わったのか、モクマは照れくさそうに頭を掻いた。
「そりゃあ、楽しみだね」
かつて、ガコンの家で夕飯を食べたとき。かつて、カンナの家で昼飯を食べたとき。あのときと変わらない空気が、三人を包んでいた。
あの日より随分と年を取ったけれど、あの日より少しだけみんな変わってしまったけれど、それでもこれから何年も何十年も経っても、きっとこうして食卓を囲み、他愛のない話をして——おそらくほとんどカンナが話すと思われるが——笑い合えるのだろう。
そんな気がした。