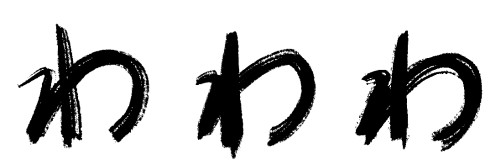賑やか声が部屋中に広がっている。無口な店主で有名な小さな昔ながらのバーは、貸し切りの客でいっぱいになっていた。
貸し切りの客とは、ワン・コンサーンに所属する化学者で──その中でもB棟の第3ラボで研究する化学者たちだった。今週、ここ数年行っていたプロジェクトがついに上層部の目に留まり新たに予算を割いてもらえることになって、数年の努力を讃えるのと前祝いも兼ねてバーを貸し切って仲間たちと騒ぎ合っていたのだ。
B棟の中でもあまり成果を出せずにいた第3ラボだが、ようやく他のラボと同じラインに立てた、と第3ラボの最高責任者が涙ながら話していた。ここからが踏ん張りどきだぞ、と仲間たちに声をかけると、わあっと歓声があがった。
ティーガンは浮き足立っている仲間たちを見ながら、同期の女性と苦笑を浮かべていた。ティーガンたちは今年入ったばかりの新入社員で、まだ半年しかこのラボに所属していない。このラボがどれほど孤立しているのか、周りからどう思われているのか、あまりよく分かっていないし気にしてもいなかった。
このラボ配属になった理由は、多分“あれ”だろう。新入社員の配属が決まっていない頃に施設の説明を受けている途中、ティーガンは上司の些細なミスを指摘してしまった。些細なミスだけど、化学者として致命的なミス。つい、口を出してしまったのだった。あの時の上司の顔は、今でも鮮明に思い出せる。恥辱と憤怒。今ティーガンのとなりにいる女性は、そのとき上司を指差して大笑いしていた人でもあった。
そういう訳で、ふたりは仲良く第3ラボ配属になったのだった。
そういえばあのとき、もうひとり大笑いしている人が居たな、とティーガンは思い出した。
空になったグラスを持ち上げると、ティーガンは新しいものをもらってくるよ、と言ってその場を後にした。
バーカウンターまで向かい、甘めの度数の低いカクテルを注文すると目線をカウンターのいちばん端に移した。
孤立しているラボの中で、更に孤立している男。
確か、エルロという名だったはずだ。
まだ成人していないようで、エルロはジンジャエールを飲んでいた。
第3ラボの中でもチームがいくつか分かれているが、その中で最も重要な研究を行うチームにエルロは所属していた。ティーガンより1年だけ先輩らしいけれど、チームリーダーからよく意見を聞かれていたり、ラボの責任者が会議にエルロを連れていったりするのを見るに、かなりの実力者というのが伺える。
カクテルが完成しバーテンダーが声をかけると、ティーガンはひとこと礼を言ってカクテルを持ちエルロの方へ歩いた。
「となり、座っても?」
ティーガンが尋ねると、エルロは顔を見ずに頷いた。
「あなた、エルロだよね。えっと、私は…」
「ティーガンだろ」
エルロはティーガンが自分の名前を言う前に、得意げに答えてみせた。ようやくティーガンの方を向いたエルロは、意外にも明るく穏やかな表情をしていた。
「研修のときの、その、よく覚えてるよ。素晴らしい指摘だった」
はは、と声を上げてエルロが笑うと、ティーガンは途端に恥ずかしくなって顔を赤らめた。自分は間違ったことをしたとは思っていないし、むしろ化学者として当然のことをしたと自信を持って言える。だがこうやって誰かから言われるとなぜだか無性に恥ずかしくなってしまう。この男に話しかけたことは、間違いだったかもしれないと思い始めた。
「ああいうやつが多いんだ。特にシティ・ワン出身のやつがな」
エルロがそう言うと、ティーガンはエルロの言う“ああいうやつ”の意味が分からず首を傾げた。
「シティ・ワン出身のやつらの多くは親のコネでコンサーンに入ってる。知識も技術も無い人間がそこらじゅうに居るのさ」
「第3ラボも?」
ティーガンがすかさず尋ねると、エルロは肩をすくめてみせた。我らが第3ラボも例外ではないらしい。
「今回のティルビノの研究だって、上層部は気に入ってくれたみたいだけど、俺はどうにも気に入らない。ティルビノの話は聞いたか?」
ティーガンは首を振った。第3ラボの中でティーガンが所属しているチームは、掃除をしたり必要な機材を借りにいったり、いわゆる雑務担当のチームだった。そのなかでもまだ新人のティーガンは掃除ばかりで、トップチームの研究内容まで耳に入ることはなかった。
「ティルビノって、ティルビノオイルのこと?」
「そう、それだよ」
ティルビノオイルとは、最近シティ・ワンで流行している健康食品のことだ。アギ科の植物の種から作られる油で、詳しいことはよく分からないがとにかく健康に良いらしく、食しても良し肌や髪に塗っても良し、今シティ・ワンの人間にとって欠かせないものだという。流行に疎いティーガンでも名前を聞いたことがあるくらいだった。
エルロは後ろを振り向き部屋を見渡した。バーカウンターに座るふたりを気にする人間は誰一人としておらず、皆ほろ酔い気分で騒ぎ合っていた。エルロはティーガンの方に向き直り、話を続けた。
「そのティルビノをアイボリーに混ぜて反応させると、非常に強い熱エネルギーが発生することが分かったんだ。おそらくティルビノに含まれるロノイという成分が、アイボリーと反応してる。それをうまくコントロールできれば、今までの半分の量のアイボリーで世界中のエネルギーを回せるようになる」
ティーガンは目を丸くさせて驚いた。まさかそんな画期的な研究が第3ラボで行われていただなんて。
ここ数年、アイボリーの枯渇が問題視されている。エルロの言う通り今までの半分のアイボリーで生活するためのエネルギーがまかなえるようになれば、それだけアイボリー資源の寿命が伸び、枯渇問題に向き合える時間が長く持てるということになる。
少し興奮した様子でティーガンが言った。
「それは、本当に素晴らしいことじゃないか!ティルビノとアイボリーを合わせようなんて、だれも考えつきやしないよ。」
「偶然だったんだ。ティルビノがたまたまラボにあって、いろいろバタついているときに誰かがひっくり返した」
エルロはそっけない態度で返したが、ティーガンはそのままの勢いで話続けた。
「すごい、ほんとうに、エネルギー問題解決の手助けになる技術だと思う。その、私はなにもしていないけれど、なんだかとても誇らしい気分だ…」
ふと、ティーガンはエルロの表情に気付き話を止めた。彼の顔に、喜びの色はない。
ひとりで浮かれてしまったのが、恥ずかしいというよりも何故か申し訳なく思えてティーガンは思わず俯いた。そしてひと呼吸置いてからエルロに尋ねた。
「エルロは、嬉しそうじゃないね。どうしてだい」
エルロは結露で濡れたグラスを持ち上げて、ジンジャエールをひとくち飲んだ。
「その技術が確立できたとしても、実装できるのはシティ・ワンくらいなんだ」
そう呟いたエルロの表情からは、何の感情も読み取れない。
「何故?」
そうエルロに尋ねたが、エルロは何も答えなかった。ただまっすぐティーガンを見つめ、沈黙を貫いた。
ティーガンは突然黙り込んでしまったエルロに動揺したが、だんだんエルロが自分に何を求めているのか理解し始めた。
エルロは、ティーガンを試しているのだ。
この目の前の新人が、親のコネで入った薄っぺらい人間共と同じかどうか見極めようとしている。
ティーガンは頭を働かせた。今の話を聞いていて何か引っかかるものを感じていたが、これだ、と明確に言えるものではなかった。
ティルビノ、アイボリー、シティ・ワン。
この3つが鍵だというのは確かだ。
しばらく沈黙が続いていたが、やがてエルロのグラスの氷がほとんど溶けたころ、ティーガンが急に顔を上げた。
「ティルビノの原料…!」
そう言うとティーガンはエルロの顔色を伺った。どうぞ続けて、と促すだけで表情は変わらなかった。
「ティルビノオイルの原料はアギ科の植物の種…。アギ科っていうとジャントやレヴラとか高山植物が多いから、所構わず栽培できるものじゃないし、量産するにはそれなりの設備が必要になると思う」
エルロはティーガンの話を聞きながら、口の端をわずかに上げて笑った。この新人は、当たりかもしれない。ようやくまともな仲間に出会えた喜びが、じんわりと胸の内に広がった。
ティーガンはエルロの変化に気付かず、そのまま話を続けた。
「もしロノイを抽出しなければならなくなったら、また更に手間がかかってしまう。ティルビノを使ってアイボリー消費を抑えられたとしても、今度は他の問題に発展してしまうんだね。経費が高くなってしまうとか、設備をどうするかとか」
エルロが深く頷いた。
「その通りだ。シティ・ワンみたいに既にティルビノ工場があれば良いが、俺の故郷ブロックロックなんかいちから作らなきゃならない。金も時間もアイボリーもかかる。この技術が確立したとしても、どうせ実装されるのはシティ・ワンだけだってのは目に見えてるんだ」
今更意味もないか、と思ったがエルロは声をひそめて話し始めた。
「連中は、地元さえ栄えれば良いと思ってるし、名声欲しさにここに居る。俺は……」
そう言うと、何か言葉を飲み込んで黙ってしまった。言おうか言うまいか迷っているのだろう。目線をキョロキョロさせている。
「なんだい、聞かせてよ、エルロ」
ティーガンはエルロが飲み込んでしまった言葉が気になった。どうしてか分からないが、ティーガンが聞きたい言葉を、エルロが言おうとしているんじゃないかと思えてならなかった。
少し悩んでから、エルロは口を開いた。
「俺は、あんな連中と同じになりたくない。化学は出世の道具じゃないし、上層部の機嫌を取るための手段でもない」
小さな声だったが、ティーガンの耳にはしっかりと入ってきた。怒りなのか、それとも悲しみなのか分からないが、強い感情がこもっているきとだけははっきり分かった。
「裕福な人間だけが楽な暮らしを送れるなんておかしい。もっと真剣に向き合えば、いろんな方向からアプローチすれば、金も手間もかからない方法が絶対あるはずなんだ。俺はもっと、そういう、研究をしたいんだ」
そう言い終わると、エルロはなんだか恥ずかしそうに頭を掻いた。
「悪い、なんか、結局は愚痴だよ。とくにこれといって言いたかったことがあるんじゃなくて、その…」
ティーガンはそんなエルロを見て、ふふっと笑った。さっきまではものすごく大人びて見えたのに、もごもごと言い淀んでいる姿はとても年相応に見える。内にさまざまな強い想いを秘めている人なんだな、とティーガンは思った。その強さは、強靭そうで、なぜだか脆くも感じた。
「私も、一部の人だけじゃなくみんなのために研究できたらって思うよ」
エルロの話を聞いて感じた素直な感想を述べた。ティーガンも幼い頃、決して裕福な環境ではなかったから、シティ・ワンだけ栄えていく今の状況に対するエルロの気持ちがよく分かった。
「君のとなりで仕事をするのが楽しみだ」
「……は?」
ティーガンが突然、話の方向性を変えてきたので、エルロは思わず声を出した。そんなエルロを見て、ティーガンは満面の笑みを浮かべた。
「まさかここまで突っ込んだ話をしておいて、何もないなんてことはないよね?」
「ちょっと待て、話が読めない」
エルロはティーガンが何の話をしているのか分からず頭を抱えた。何か聞き逃しただろうか。何かそういう類の話をしていただろうか。正直、何も思い当たらない。
「私も混ぜてよ。君のチームに。そういう話だろ?私の考え方を聞いて、良い人材だって思ってくれたんじゃないのかい?」
「いや、まあ、そうだけど…」
少し早口で言い立てるティーガンを見て、エルロは顔をしかめた。
「……結局はお前も出世狙いか?ん?」
自分と同じような化学者にようやく会えたと思ったのに根は他の連中と変わらないのか、と落胆しかけたとき、ティーガンが前のめりになって言い放った。
「違うよ!君のとなりで、君の手助けをしたいんだよ!君の考えはとても素晴らしいと思う。同じ志を持つ仲間と働きたいと思うのは、ごく普通のことだと思うんだけど」
怯むでもなく、慌てて訂正している風でもなく、当たり前のことを当たり前に話している様子でティーガンは言った。
エルロは口元を押さえて唸った。ティーガンの意図が全く読めなかったからだ。本当に心から言っているのか、それとも本心を隠しているのか、ティーガンの表情や行動からは何も読み取れない。
「君からチームリーダーに話しておいてくれよ。私を是非チームの一員にしてくださいってね!いいかい?頼んだからね!」
ティーガンはエルロの肩をぽんっと叩いて、ものすごく明るい笑顔で言うと、じゃあまたね、とひとこと挨拶をして人混みに消えていった。
エルロはしばらくティーガンの去った方向を見て、ぽかんと口を開けていた。
「はあ……なんなんだ、あいつ」
深いため息とともに呟いた。同じチーム配属にするよう頼まれたが、エルロにそんな権限は無い。それに、これは個人的なものだが、エルロはチームリーダーが苦手だった。ただでさえ人と関わるのが得意ではないのに、あの無口で堅物のチームリーダーに向かって個人の思い入れだけのメンバーを推薦するなんて、考えただけでも胃が痛くなりそうだった。
だからといって、エルロ自身もティーガンが言ったように、同じ志の仲間と研究をしたい気持ちが無いわけではない。ここで自分が何も行動を起こさなかったら、せっかく歩み寄ってくれた仲間の手を突き放すことになってしまう。
「…くそっ、どうしたらいいんだ」
エルロは何度目か分からないため息をついた。
氷が溶けきって薄まったジンジャエールを眺めながら、エルロはティーガンと話し込んでしまったことを静かに後悔していた。