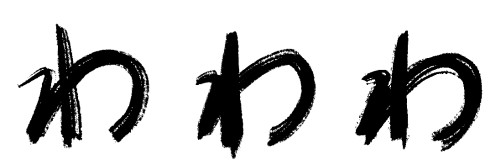120%捏造、幻覚
グスターヴォとティーガンの出会い
捏造民族、モブ、なんでもあり
___
一面真っ白な世界に、ぽつり、ぽつりと黒い点が浮かんでいる。黒山羊だ。ダーランド坂にうろつく黒山羊を眺めながら、グスターヴォはゆっくりと坂を登っていた。
麓の同胞が言っていたことは本当だった。
グスターヴォたちのような「海賊」の大半はイシルガーに集結しているが、なんらかの理由で海を離れ、大陸で細々と暮らす集団が無い訳ではない。麓で会った同胞たちは、数世代前にここまでやってきたと言っていた。理由について尋ねたが、詳しくは教えてくれなかった。
ワン・コンサーンの本部がある山の麓で隠れるように暮らしている同胞たちはかなりピリピリしていて、どうしようもない喧嘩ばかりが起きているらしい。今朝だって、ある家族の家畜の柵が壊されてたと騒ぎになって大変だった。
グスターヴォは、捕まえられるなら捕まえてみるか、と思ってダーランド坂に黒山羊の様子を見に来ていた。
遠巻きにグスターヴォを見ている黒山羊たちは、一定の距離を保ってこちらに近付いて来ることは無かった。こりゃ無理だな、とグスターヴォが諦めたとき、ふと視界に入った何かが気になった。その何かを確かめるため、目を凝らして辺りを見渡すと、一ヶ所だけ雪が大きく削れているところがあった。そこは崖の端で、崖下に雪が落下したようだ。
昨日は一日中快晴だったらしく、昼間に溶けた表面が夜に再び固まっていてある程度の硬さがあったから気付かなかったが、よく見ると大きく削れた場所の付近には山羊の足跡と人間の足跡がある。山羊の足跡だけが山頂に向かって続いているので、おそらくここから人間が落下したのだろうと予測できた。
(まずいな…)
グスターヴォは急いで下を覗き込もうとしたが、崖周辺の雪は崩れやすくなっていて、あまり近付くことができなかった。下に回れる道があったのを思い出し、グスターヴォはなるべく早く、しかし安全な速度で坂を下り始めた。
+++
ティーガンはぼんやりと空を眺めていた。猛禽類が飛んでいるのが見える。
私は、ここで死ぬのかもしれないな、と思った。
コンサーンの本部から少し離れたところに、廃棄物処理場がある。主にアイボリーのチリなどを捨てる施設だ。
その廃棄物処理場からさらに少し離れた岩場に、ケミコ・コントラが集めた情報をまとめるための小さな基地が隠してあった。
ティーガンはラボで出たゴミを捨てに行くついでに、こっそりと基地に向かい情報を確かめに行こうとしていたところだった。処理場も基地もさほど遠くないため、そこまで厚着をしてこなかったから、とにかく早く済ませて暖かい室内に戻ろうとティーガンが駆け出したときだった。
岩影から突然、真っ黒な山羊が飛び出してきた。あまりにも突然すぎてティーガンは叫び声を上げてしまい、その声に山羊も驚いて途端にお互いパニック状態になった。急に跳ねた山羊に踏まれないようその場から慌てて逃げ出したものの、逃げた先が崖っぷちだったためそのまま足を滑らせて転がり落ちてしまった。
幸いなことに崖全体が雪に覆われていて岩肌に体を打ち付けることはなかったが、それでも再び凍った雪は固く、ティーガンの体を容赦なく攻撃した。ティーガンは頭を守ろうと手を首の後ろに回して頭全体を腕で覆おうとしたが、その瞬間左腕に激痛が走った。痛みに顔を歪ませながら必死で左を向くと、この辺りでよく見かける棘が鋭い植物が生えているのが見えた。棘と言うにはあまりにも鋭く、文明が栄える前は武器として使われたこともあったらしい。今でも動物除けに畑の前に敷き詰める人もいると聞いたことがある。
ティーガンはその鋭い棘に左腕を引っ掛けてしまい、肘上から肩にかけてざっくりと深く切ってしまったのだった。鈍い痛みに思わず歯を食いしばったが、一番下まで落下した強い衝撃が背中一面を襲い更なる激痛に意識が飛びそうになった。肺の空気が一気に外に押し出されたようで、呼吸することもままならなかった。
ティーガンは時間をかけてゆっくりと息を整え仰向けになりながら空を見上げると、このまま訪れる死を待つしかないのかもしれないとぼんやり思っていたのだった。
ティーガンの上を飛んでいた猛禽類が、徐々に地面へ近付いてきた。おそらくティーガンはもう動かないと思い、捕食しようとしているのだろう。
案外あっけないものだな、とティーガンは思った。どんなに世界の為を思って活動していても、人々の未来を想っていようとも、そんなことは関係なく最期は猛禽についばまれて死ぬなんて、どうしようもなく惨めな気持ちになる。
猛禽がティーガンの側に降り立とうとした瞬間、どこからか雪の塊が一直線に飛んできた。雪は体を掠めただけで当たらなかったが、猛禽は周囲を警戒したのか勢いよく再び上空に戻った。
「しっ、しっ、あっち行けって。お前の獲物じゃないぞ!」
雪の塊が飛んできた方向から人影が浮かび、その人影が大声で叫んだ。
「西の方に子山羊が居たぞ!狙うならそっちを狙え!」
すると猛禽はその言葉を理解したように、西の空へ飛び去っていった。猛禽の姿が見えなくなったのを確認すると、声の主はティーガンの元まで駆け寄って来た。ティーガンは焦点の合わない目で駆け寄って来た人物を見ると、海賊の男らしいということが分かり、わずかに身を固くした。男は気にする素振りを全く見せず、そのままティーガンの傷を確認し始めた。
「頭は……打ってないな。たいしたもんだ、ちゃんと頭を守ってる。問題はこっちだな。山の剣にやられてる。早く治療しないと……」
山の剣とは、あの棘の鋭い植物の俗称だ。男はリュックを下ろすとごそごそと中を漁り、ポーチを取り出した。治療を始めるかと思いきや、男は顎に手を当てて、うーんと唸り悩んだように首を傾げていたが、やがて申し訳なさそうにティーガンの顔を覗き込んだ。
「悪いね。本当は薬で感覚を鈍らせた方が良いんだろうけど、時間が惜しいんだ。ちょっと荒っぽい治療をさせてもらうよ、ごめんな」
ティーガンの耳にも届くように、大きな声でゆっくりと言うと、男はハンカチをティーガンの口に押し込んだ。
「ん…!う……!?」
「あまり痛みに慣れてなさそうだから一応ね!ちょっとだけ我慢しててくれよ!」
ティーガンは驚いて身を引こうとしたが、それよりも先に男がティーガンの上にまたがって膝だけで体を固定したので、その場から全く動くことができなかった。
ティーガンは、喉の奥から恐怖がせり上がってくるような感覚がした。逃げなくては、と思うのに男に押さえつけられていて何もできない。
男は恐怖に怯えるティーガンのことなど全く気にせず、傷に手を伸ばし、指で傷口をつまみ合わせ始めた。
左腕全体が貫かれたように痛み、ティーガンは必死で痛みから逃れようと呻きながら身をよじったが、的確に押さえられた体は縄で縛られたように動かない。
男は裂けて離れた肉と肉をつまんでくっつけると、慣れた手つきでティーガンの腕に布をきつく巻きつけ始めた。布を巻き終えると、男はティーガンの右肩にそっと手を乗せて落ち着かせるように言った。
「大丈夫。死にやしないよ。俺が絶対助けてやるから、安心しな」
ティーガンは痛みと恐怖と寒さでがたがたと震えていたが、少しずつ、少しずつ、落ち着きを取り戻してきた。
男はリュックを前側に抱え、傷を刺激しないよう慎重にティーガンを背負うと、なるべく体を揺らさず歩き始めた。
ティーガンは背負われながら、あまり身長の変わらないこの男の背中が妙に大きく感じて、なぜか胸の奥が温かくなった。
そういえば、誰かに背負われたのは初めてな気がする。幼少の頃の記憶をたどってみても、背負ってもらった記憶はどこにも見当たらない。
ティーガンは力を抜いて男の背に体を預けると、重い瞼を閉じて深い眠りについた。
___
ティーガンが目を覚ましたのは、それから半日経ったあとだった。どこかの岩窟なのか、壁や床はどこもゴツゴツとしていて、柔らかい寝袋に包まれていても少し寝心地が悪い。
視線を横にやると、海賊の男がアウトドア用のコンロに乗せた鍋で何か煮ているのが見えた。男はティーガンがこちらを向いていることに気がつくと、慌てて口を開いた。
「起きた?悪いね、本当はもう少し移動しようかと思ったんだけど雪が降ってきてさ」
人懐っこい笑みを浮かべ、ティーガンの方へ歩いてきた。
「俺はグスターヴォ。しがない医者さ。基本的に外科専門だけど、まあ内科も診れないこともないかな。ははっ、山に”海賊”が居てびっくりしたろ」
ティーガンは返事をしようと口を開いたが、口が乾ききっているのか掠れた音が出ただけで、意味のある言葉を発することができなかった。グスターヴォに伝わるよう頷こうとして、左腕に激痛が走り思わず呻いた。
「しばらく痛いだろうけど、もうちょい我慢してくれよ。熱も出てきてるから、そこを乗り越えれば、うんと楽になる。まあ乗り切るためにもちょっとくらい飲食はしとかないとね」
グスターヴォは痛みに喘ぐティーガンを支えながら起こしてやると、鍋に入っていたミルクをマグに注ぎ、少し冷ました後に手渡してきた。
香草と煮たのだろう。香ばしい良い香りが漂ってくる。
ティーガンはそのミルクを口に含むと、思い切り眉間に皺を寄せた。そんなティーガンの表情を見て、グスターヴォは頭を掻いた。
「やっぱ駄目か?けっこう誤魔化せてると思ったんだけどなあ」
ティーガンの口の中いっぱいに香ばしさと山羊臭さが広がる。山羊の乳だ。蜂蜜も混ぜてあるが、どうしても山羊臭さが抜けきれていない。
「慣れなくて大変だろうけど頑張って飲んでくれよ。熱が出ると体力もってかれるからさ」
山羊臭いミルクを少し飲んで潤ったティーガンの口から、ようやく言葉が紡ぎ出された。
「早く、戻らないと。……手当てをして、くれたのは、本当に、感謝してる。でも、早く戻らないと、仲間が危険な目に、あってしまうかも、しれなくて……」
「君、コンサーンの人だろ?」
ティーガンの言葉を遮るように、グスターヴォが尋ねた。ダーランド坂に居る人間なんて基本的にコンサーンの者くらいだから、そこを改めて確認するグスターヴォに対して怪訝な顔をして見せたが、ティーガンは素直に頷いた。
「俺は、ほら、見ての通り海賊だから、コンサーンの人間に知られたくないんだよ。君を本部まで送り届けてあげたいけど、俺は姿を見られたくない。君がひとりで安全な足取りで歩けるようになるには一晩以上かかる。だから君をすぐに帰すことはできないんだ」
グスターヴォが自分の肌を指差して言うと、ティーガンをまっすぐ見つめて言った。
「敵なのに、私を助けて、くれたの?」
「敵?君と俺は敵かい?確かにコンサーンと俺たちの一族はよくドンパチやってるけど、この場に居るのは怪我人と医者だろ?」
グスターヴォも手元のマグにミルクを入れ、ふうふうと息を吹きかけながら飲み始めた。
「人間ってのは知らないものが怖いのさ。俺はいろんなとこ回っていろんなものを知ってるから、他の人より恐ろしいものが少ないのかもな」
肩をすぼめてグスターヴォが笑うと、つられてティーガンも笑った。
山羊臭いミルクを飲み終えると、体の芯まで温まった。ひと息つくとティーガンは瞼がどんどん重くなり、このまま寝てしまいそうになったが、なんとか眠気を抑えグスターヴォに話しかけた。
「私は、コンサーンの研究者だけど、秘密裏に、コンサーンの思想に…反する活動を、行ってる。私たちの活動に、気付き始めた、連中が居て、私の失踪が、何かの活動だと、思われてしまったら、仲間が、危険な目に、あってしまうかも、しれないんだ……」
眠気や痛みと戦いながら、ティーガンはどうにかグスターヴォに自分の考えていることを伝えようと必死で声を出した。
「それで戻りたいんだな。でも外は雪が降ってる。俺がついていってあげたって本部にたどり着けやしないよ。なんとかならないか、俺もいろいろ考えてみるからさ、とにかく今は眠らなきゃ。熱が上がってるんだし」
グスターヴォはティーガンの隣に座り、寝る体勢に戻るのを手伝った。確かに体がずっしりと重くて、頭がぼうっとしている。
ティーガンは瞼を閉じると、すぐに意識を失った。
+++
次にティーガンが目を覚ましたのは、2日後の朝だった。怪我の影響だけでなく、最近残業続きで疲れていたからか、どうやら一晩と丸一日、泥のように眠っていたらしい。
グスターヴォは、起き上がったティーガンを見ると、少し外を見てくると言って岩窟を出て行ってしまった。
覚醒したばかりでふわふわと夢心地だったティーガンは、徐々に自分の置かれている状況を思い出してくると、自責の念で押しつぶされるような気持ちになった。
熱に浮かされていたとはいえ、ケミコ・コントラの存在を軽率に話してしまった自分を恨んだ。グスターヴォは実はコンサーンと繋がっていて、今のうちに兵士やエージェントと連絡を取っているのかもしれない。
最後の晩餐が山羊のミルクか、もう少し良いものがよかったな、と考えていると、折りたたみ式のバケツいっぱいに雪を入れたグスターヴォが帰ってきた。
「雪、もう降ってなかったぞ。熱も下がったみたいだし、朝飯食べたら外出るか」
下手にいろいろ考えるより、本人に直接聞いた方が早いと思ったティーガンが尋ねた。
「あ、あのさ、君は、どうして私を助けてくれたの?コンサーンの人間と繋がってたりするの?裏でコンサーンに逆らっている私を本部に報告したりした?」
「いや、直接聞きすぎだろ!」
グスターヴォが笑った。
「疑り深くなってる人には薄っぺらい言葉に聞こえるかもしれないけどさ、俺は困ってる人を助けたいだけなんだよ。それに昨日言ったろ?俺もコンサーンの人間に知られたくないんだ。困ってたり、怪我してたりするなら俺はコンサーンの人間でも助けるけど、マザーを信仰しているわけじゃないからコンサーンと関わったっていいこと無いと思うんだよな」
そう言いながらグスターヴォは鍋で雪を溶かすと、あまり馴染みのない香りのする茶を淹れてくれた。パサパサとした携帯食料もティーガンに手渡した。
携帯食料を食べながら、グスターヴォは自分のことを話し始めた。「海賊」と呼ばれているけれど、本当は「イシの一族」であること。イシの人々はどんな文化や技術を持っているのか、どういう信仰があるのか。そしてどうして自分がこうして医者をやっているのか、故郷に居づらい理由まで、包み隠さず話してくれた。
「君たちの、その反コンサーンの活動に役立つ情報が、俺たちのラボにあるかもしれない。手を組めば、良い未来を掴めるかもな」
「どうしてそこまでしてくれるの?今の話だって、あまり外部に出しちゃいけないような話だったんじゃない?」
「人は、知らないから恐れるんだ。イシの人たちは隠しすぎてると思うし、外の人たちはマザーを信じすぎてると思う。俺たちは生まれた場所も、染み付いた文化も違うけど、同じ人間だ。きっと歩み寄れるはずさ」
グスターヴォが話し始めたとき、ティーガンはこの男は自分を信頼させるためのカバーストーリーを話しているんじゃないかと疑っていたが、イシの文化に馴染めない自分自身を語るグスターヴォの表情を見てその考えを改めた。悲しみや怒りではなく、諦めの色が濃く浮かんだその表情は、グスターヴォのどんな言葉よりも彼自身の人生を語ってくれているような気がした。
「そうだ、これから君をどうするかって話なんだけど」
「だいぶ頭もスッキリしたし、ひとりで帰れると思うよ」
「いや待て待て、その治療のことはどう説明するんだ?」
立ち上がろうとしたティーガンを、グスターヴォが慌てて座らせた。
「焦る気持ちも分かるけど、君は山羊に襲われて落下した。それは事実だろ?別に特別な活動をしてるわけじゃない。何か決定的な動きがない状態でコンサーンが動くとは思えないし…。まあ、君の仲間が下手に動いてなければの話だけどね」
「私たちケミコ・コントラは助け合いの精神を何より大事にしているけれど、生死が分からない仲間のことは深追いせず切り捨てるようにと言われてる。みんな、もう私は居なかったものとして活動してるだろうね」
ティーガンは口ではそう言いながらも、きっと多くの仲間たちは自分を心配してくれているんだろうな、と思っていた。
いや、でもあの無愛想な天才は、本当に綺麗さっぱり切り捨ててしまっている気がする。無事に本部に戻ったとしても、あの男はきっと何ひとつ以前と変わらずに接するんだろうな、と心の中で苦笑した。
「よかった、じゃあ俺の考えを聞いてくれ」
グスターヴォは茶を一気に飲み干すと、落ち着いた雰囲気で言った。
「この山の麓にある集落がある」
同胞が隠れて暮らしている場所とは、真逆の方向をグスターヴォが指差す。イシの人たちとは違い、コンサーンから隠れず堂々と暮らしている民族の集落が大きな湖の近くにあるのだ。
「狩人たちって、知ってるか?」
ティーガンは大きく頷いた。
大地や自然を神と崇め、自給自足の生活を送る狩人。詳しくは知らないが、ティーガンでもなんとなく聞いたことがあった。
マザーを崇めない異教徒だからと、昔はコンサーンもあれこれ狩人たちに口を出していたらしいが、アイボリーを使うわけでもコンサーンに文句を言うわけでもなく、山に入り木の実を採り狩りをし火を起こして静かに生活する彼らは無害であると認識したのだろう。今は全く視界に入れていないらしい。
「狩人たちはたまに、狩りに使う山の剣を採取するってんで山に登ってくるんだ。俺はちょいと狩人たちと顔なじみでね、君は狩人たちに助けられたってことにしようかと思うんだ」
「狩人と知り合いだって?」
ティーガンは驚いて大声を上げた。噂で聞く限り、狩人たちは無口で、無関心で感情なんて感じられない人たちだ。
「無知が生み出す恐怖の典型的な例だな!彼らが恐ろしいかい?じゃあ知ってみなくちゃ!狩人たちの集落に向かうよ」
呆れたようにグスターヴォが笑った。
「集落まで距離がある。君が落下したところから集落まで運ばれたとして、君は2日くらい寝てただろ?今すぐ本部に帰ったらあまりにも早すぎるからっていろいろ疑われると思うんだよな。一度集落にお邪魔して一晩お世話になろう。俺がちゃんと話しをしてやるから、多分面倒ごとにはならないよ」
そう言うとグスターヴォはてきぱきと片付けをし始めた。ティーガンは、自分が何を言おうがグスターヴォは狩人の元へ行く以外の選択肢を用意していないのだと察すると、片付けを手伝おうとした。
「いいよ、君、怪我人だろ」
「でも悪いよ」
「君の悪いところといえば、雪山で薄着だったことだな!なんでまあこんな薄着で…!」
「こんなことになるなんて思ってなかったんだよ!ていうか私だけじゃなくみんなこんなだって!」
ティーガンが怒鳴るように反論すると、グスターヴォはリュックを整理しながら「君、意外とやかましいんだな!」と返した。どうやら気に障ったらしく、ティーガンはそっぽを向いて黙り込んでしまった。
片付けが終わると、グスターヴォは傷が開かないようティーガンの左腕を胴体に固定したあと、銀色のシートとタープ用の布で体全体を覆った。かなり動きにくくなるが、凍死するよりマシだろう。
ふたりは岩窟を出ると、狩人たちの集落に向かって歩き始めた。
___
一面真っ白な景色が続いていたが、徐々に雪が減って、森林限界の高度より下がると一気に青々とした緑が目に飛び込んできた。
気が付けば、ふたりは深い森の中を歩いていた。
「なんだい、あれ」
ティーガンが指差した先には、大きな石像が佇んでいた。
「神様さ。ここからが狩人たちの場所ってわけだよ」
苔むした石像は人の形をしているように見えるが、どこか抽象的で男なのか女なのか分からない。
グスターヴォは石像に触れられるまで近付くと、突然オオカミのような遠吠えを上げ始めた。
「なっなにを…!」
ティーガンは驚いて声を上げたが、グスターヴォに口を塞がれ、何が起こったのか何のためにやっているのか聞くことができなかった。
妙な抑揚をつけて遠吠えを上げ続けていると、だんだんどこからか似た遠吠えが返ってくるようになった。もう何回か遠吠えを上げると、グスターヴォは笑ってティーガンの方を見た。
「迎え入れてくれるってさ」
「どういうこと?」
「今のは狩人の合図のひとつなんだよ。抑揚をつけることでいろんなことを伝えられるんだ」
「グスターヴォは今なんて言ったの?」
「俺だよ〜グスターヴォだよ〜訳ありの友達居るんだけど入って良い〜?って」
ティーガンは、なんだか子供扱いされている気がして少しムッとしたが、そこで怒ったら本当に子供だな、と思って口には出さなかった。
「それで?なんて返ってきたの?」
「いいよ!だってさ!」
石像をあとにしてそのまま真っ直ぐ進むと、思いの外すぐに集落が見えてきた。小さなログハウスが立ち並んでいて、奥には湖が見える。
噂では、狩人たちは無口で無愛想な民族だと聞いていたが、グスターヴォが集落に近付くと外に居た狩人の何人かが笑顔でこちらに向かって来た。
グスターヴォと狩人たちが話しているのを見て、ティーガンはなぜ狩人は無口であるという噂が広がったのか、なんとなく理解した。
言語が違うのだ。
グスターヴォは当然のように狩人たちの言葉を喋っている。
「ティーガン、長のところまで行こう。あのいちばん大きな家だ。事情を話して、一晩泊めてもらおう」
狩人たちから解放されたグスターヴォが、少し遠巻きにみんなを見ていたティーガンの元に戻ってきた。
「ティーガン?」
「えっ、ああ、なんでもない。行こうか…」
ティーガンは立ち並ぶログハウスを眺めながら眉間に皺を寄せた。バイクやスノーモービルが留めてある家が点在している。
まるで自分の家のようにずかずかと長の家に入るグスターヴォの後に続いて、ティーガンはひとこと断ってから、家にお邪魔した。
狩人の長はかなり大柄だった。頭髪はすっかり白くなっていたが、杖をつくことなく胸を張って背筋をピンと伸ばしていて、老いを感じさせない雰囲気をまとった老人だ。
これまでの経緯を話してくれているのか、グスターヴォは時折ティーガンを差しながら長と話している。話の内容が分からないティーガンは、家の壁に掛けてある動物の剥製や見事な刺繍が施してあるタペストリーをひたすら眺めていた。
ふたりが5分ほど話し込んだあと、グスターヴォはリュックから白い液体で満たされた瓶を取り出して長に渡した。
「ア、アイボリー…!!」
ティーガンは思わず指を差して叫んでしまい、長が不思議そうに彼女を眺めている。
アイボリー燃料。この世界に欠かせないもの。
人類はアイボリー無しに生活できないからこそ、ケミコ・コントラはアイボリーに変わるエネルギーを探し続けているのだ。
自然エネルギーだけで生活していると言われていたこの狩人たちも、やはりこの世界の人間だったということか。
ティーガンは咳払いをして、何事もなかったかのようにまたタペストリーを眺め始めた。
また5分ほど話し込んだあと、グスターヴォは長に一礼して、ティーガンとともに家を出た。
「あっちに長の娘さん夫婦が住んでるんだってさ。今晩、君はそこで泊まることになるって…」
グスターヴォの方を向いて、ティーガンは厳しい顔をして仁王立ちしていた。まだ片手は不自由なままだったが、とにかく怒っているのか、不信感をつのらせているのか分からないが、睨むようにグスターヴォを眺めていた。
「アイボリーの密売は重罪だ。君がコンサーンに見つかりたくない理由ってこれだったんだね。ここの人たちはアイボリー無しで生活できるんじゃないの?」
「密売って、助けてやったのにずいぶんな言い方をするんだな。密売の手助けをしたと思われるのは嫌か?」
「そうじゃない!ただでさえアイボリーの減少が問題になってるのに、こうやって密売する人がいるからどんどん深刻な問題に発展していってるんじゃないか!」
アイボリーの密売の多くは、シティ・ワンやコンサーンから遠く離れた地域のものが使われる。コンサーンの警備が薄く、そこまで質が良くないので重要視されていないのだった。比較的簡単に手に入りやすい地方のアイボリーを入手して、各地で密かに活動しているレジスタンスグループなどに売り付ける手口がほとんどだ。密売人のおかげで地方のアイボリー配給可能数が緩やかに減少しており、アイボリーの値段が上がり、貧しい人々ばかりがさらに苦しい生活を強いられ、その人たちが密売に手を出し始めるという負のサイクルができあがっている。以前はコンサーンも積極的に取り締まりを行なっていたが、各地で暴動が起こったり、聖罰が頻繁に下されることでその対処に追われたりと、密売にまで手が回らない状態だった。
ティーガンが声を張り上げてまで怒っているのは、許可無しにアイボリーに触れた罪を自覚させるためではない。
罰せられるかどうかは問題ではないのだ。
たったひと瓶のアイボリーで、どのくらいの人々が救えるのか、それを良く知っていたからだった。
グスターヴォは頭を掻いたあと、しっかりとティーガンの目を見て言った。
「文句ならあとでいくらでも聞くから、とりあえず俺の話をひたすら聞いてくれないか?」
ティーガンは口を開きかけたが、そのまま無言で頷いた。
「ありがとう。何から話すかな…」
少しキョロキョロと周りを見たが、またすぐにティーガンへ視線を戻した。
「ええと、まず、ひとつめ。俺は密売人じゃない。うーん、誤解させちまったな。先に言っておけばよかった。悪かったよ。ほら、さっきアイボリーと交換してもらったものだ」
そう言うとグスターヴォは持っていた大きな袋を両手で持って、ティーガンに見えるよう開いて見せた。
食料や薬草などが、ぎっしり詰まっている。
「それで、ふたつめ。あのアイボリーはどっかから奪ってきたものじゃなくて、譲り受けたものなんだ。よく特別に調合した薬を持って行ってあげてる知り合いがいるんだけど、その人がさ、分けてくれるんだ。自分のアイボリーを、俺のためにって、瓶に入れてくれるんだ」
そう語るグスターヴォの瞳には、深い悲しみの色が浮かんでいた。
「んで、最後な。狩人たちは、もともとアイボリーに頼らなくても生活できてた。でも地殻変動が起こったり、アイボリーの減少…は関わってるかどうかちょっと分からないけど、まあいろいろあって、生態系がガラリと変わっちまったんだとさ。ずっと遠くまで狩りをしに行かなきゃいけなかったり、冬場の冷え込みが厳しくなったりして、アイボリーが必要になったってわけだ。多分、頑張ればアイボリー無しでも生活できると思うけど、暖房器具を使えるようになって死人がうんと減ったって聞いたよ」
「その……ごめん、グスターヴォ。早とちりだった」
「いいって。人を想って行動するってのは意外と普通にできないものさ」
本当に優しい人だな、とティーガンは思った。
おおらかで、誰かを責めたりしない。
誰かを助けることに、全てを注いでいるかもしれない。
ティーガンは、アイボリーの密売人だと疑ってしまった自分が酷く愚かしく思えて、思わずため息をついた。
聖三角形を信仰している人たちは視野が狭く、考え方が凝り固まっているなと思うことが多かったが、きっとグスターヴォには同じように見えているのかもしれない。
「医者をやってくのだってタダじゃない。俺はアイボリーを渡して、薬草や食料を貰う。その薬草で薬を調合して患者に渡す。ある患者からアイボリーを分けてもらって、狩人たちに渡す。そういうサイクルがここでできてるんだ。マザーや彼のお方はこういうやりとりを気に入らないのかもしれないけど、少なくとも俺は聖罰を受けてないし、狩人たちだってそうだ。これは生きていくために必要なサイクルで、共生関係なんだよ」
狩人たちは必要最低限の暖房や移動手段のみでアイボリーを使い、それ以外は昔からの生活をそのまま受け継いで生活している。湖から水を汲んだり、獲ってきた動物の皮を剥いだりしているのが、ここからでも良く見えた。
きっと私たちはアイボリーに頼りすぎている。
昔は、同じような生活をしていただろうに。
「私はコンサーンに戻ったら、狩人に助けられたと報告してしまうよ。もし本部の人間が見に来ることがあったら大変なことになってしまうんじゃない?」
バイクやスノーモービルを眺めてティーガンは言った。
「山の上にいるんじゃ気付かないだろうけど、もうここいら一帯は春だ。彼らはみんな家の地下にに秘密の隠し倉庫を持ってるんだって。春はウサギや鳥やらがいっぱいいるから移動もしないし、安心してくれって長が言ってたよ」
「よかった…」
グスターヴォが落ち着いた声で答えると、ティーガンはほっと胸を撫で下ろした。
狩人たちは強かだ。聖三角の下で生きる人間が、きっといちばん弱々しいのだろう。
ティーガンはグスターヴォに案内してもらい、長の娘夫婦の家に泊まることになった。
「じゃ、俺はこれから長の家で簡易診療所を開くから。また明日な!」
そう言ってグスターヴォは長の家に戻ってしまった。言葉が通じない人たちに囲まれた状態でひとりにされたのはとても心細かったが、長の娘は優しく丁寧に接してくれて、何も不自由を感じることはなかった。
傷がまだ痛むからか、慣れない環境で緊張しているのか、ティーガンは用意してくれたベッドに入ってもなかなか寝付けなかった。
壁に掛けられた鹿の頭からの視線を感じながら、ティーガンは目を瞑り、なんとか寝ようと試みたが、結局ほとんど眠ることはできなかった。
太陽が顔を覗かせる前に、狩人たちの朝は始まる。
ティーガンがようやく眠れそうだと思った頃、急に周りが騒がしくなり、あっという間に目が冴えてしまった。
朝食を貰い、スープと焼きたてのパンをゆっくり食べた。赤いスープはトマト味だろうと思ったが、どうやらトマトではなく赤い果実を使っているらしく、酸味よりも甘みが強く感じられて脳が混乱した。ゴロゴロと入っている野菜も、見慣れないものが多い。
シティ・ワンなんかよりもずっと近いこの場所に、言語も文化も全く異なる民族がずいぶん昔から住んでいたと思うと、なんだか不思議な気持ちになる。
(私たちは、この世界のこと、何も知らないんだな)
ティーガンは窓の外を眺め、忙しなく働く狩人たちを見ながら思った。
ふと、誰かがこちらに向かって歩いて来るのが見えた。グスターヴォだ。
ティーガンは右手だけでぎこちなく窓を開けると、グスターヴォに向かって挨拶をした。
「おはよう、狩人たちの朝は早いんだね!」
「おはようさん!顔が疲れてるな。そんな眠れなかったか?」
「大丈夫!温かいスープをご馳走になったから元気出たよ!」
ティーガンの元気な受け答えを聞いて、グスターヴォは表情を和らげた。
「そりゃよかった!もう少し経ったら出発しても平気そうだな」
ちょうど空が白んできて、そろそろ太陽が昇る時間だった。この時間に出発すれば、日が高いうちにコンサーン本部に着けるだろう。
ティーガンは世話になった家の人たちに、言葉は通じないけれど自分なりに目一杯感謝を伝えると、外に居たグスターヴォの元に向かった。
グスターヴォの隣には、見慣れない女性が立って居た。
「ああ、ティーガン。俺は昼くらいまでここに残ることにしたんだ。あそこの爺さんの体調がどうも悪くてね。ごめんな」
小さなログハウスを指差しながら申し訳なさそうに言った。
「ついてきてくれるつもりだったの?私はここからひとりで戻るものだと思っていたけど」
「ばか!君は怪我人なんだぞ、ひとりで山を登らせたりするか!」
グスターヴォが珍しく怒鳴ったが、怒っているというより呆れの感情が強い怒鳴り方だった。ティーガンが思わず声を上げて笑うと、「笑いごとじゃない」と更に怒られてしまった。
「とにかく、君をひとりにするわけにはいかないから、俺の代わりに彼女がついていってくれることになったんだ。狩人たちの中でも雪山を歩くのが群を抜いて上手くて、それに道案内も得意だ。言葉が通じなくても、きっと君を安全に本部まで導いてくれるよ」
グスターヴォの隣に居た女性が、歯を見せてにこっと笑った。
よく見るとティーガンよりずっと若く、まだ少女と呼んでも違和感は無い。しかし、小柄でまだ幼さが残る彼女だが、ティーガンよりもはるかに体格がしっかりしていて、か弱さなど一切感じさせない力強さがあった。隣に居るだけで安心感を覚えるほどだ。
ティーガンはこの頼りがいのある少女の名を尋ねたが、狩人独特の発音とイントネーションが難しく、どうしても呼ぶことができなかった。
___
狩人の少女は、何かあったとき用の寝袋や数日分の水と食料を背負い、ティーガンは今日の昼食分だけを腰に括り付け旅支度を済ませた。ほとんど何も持っていない状態のティーガンは、なんだか申し訳ない気がして何か荷物を背負おうとしたが、思っていた以上に傷が痛み、仕方なく少女に甘えることにした。
グスターヴォは石像のところまで見送りに来てくれた。
昨日は気が付かなかったが、石像付近は森が開けていて、ここからでも山が良く見えた。今からあそこを登っていくのだと思うと、少し気分が萎えた。
「じゃあな、ティーガン。もう怪我すんなよ」
「うん、本当にありがとう。君は命の恩人だよ。心から感謝してる」
「当たり前のことをしただけだよ」
グスターヴォが素っ気なく答える。彼からしたら、こういう人助けはいつも通りのことなんだろう。
「それでも、ありがとう。当たり前のことを当たり前にできる人間って意外と少ないんじゃないかなって思うんだ。助けてくれたのが君でよかったよ。いろいろなことも学べた」
「君が良い人だから、俺が君に引き寄せられたのかもしれないな」
「なんだい、それ。どういう意味?」
「そのままの意味だよ」
最後の最後まで、グスターヴォのペースでしか会話ができなかった気がするな、とティーガンは思った。この男は、どこか掴めない雰囲気がある。
「またいつか、会えるといいね」
ティーガンが言った。
「会えるさ、そんな気がする」
グスターヴォが返した。
傷に触れないよう、ふたりはそっとハグをした。
「じゃあ、気をつけて」
ティーガンはそう言うと、グスターヴォからゆっくり離れ、狩人の少女と共に山に向かって歩き始めた。
しばらく歩いてから後ろを振り向くと、石像の近くでグスターヴォがまだ大きく手を振ってくれているのが見えた。ティーガンも大きく手を振り返し、すぐに正面を向いて歩き続けた。
(不思議だな…)
コンサーンの人間とイシの人間が狩人の集落で寝泊まりしてたなんて、数日前の自分に教えたら一体どんな反応をするのだろう。そう思いながらも、あまりにも現実離れしたことが続いたからか、ティーガン自身も夢を見ているような心地だった。
(私たちに必要なのは、きっと歩み寄る勇気だ)
ティーガンはグスターヴォが言っていた言葉を思い返した。
人間ってのは知らないものが怖いのさ。
そうかもしれないし、知ればより恐ろしくなることもあるかもしれない。
マザーを崇めていても、祖先の教えを崇めていても、自然を神だと崇めていても、この大地が崩れてしまえば、信仰など関係なく生きとし生けるものすべてに滅亡が訪れる。
(私は、何をすべきなのか…)
山を登るティーガンの瞳には、強い光が宿っていた。