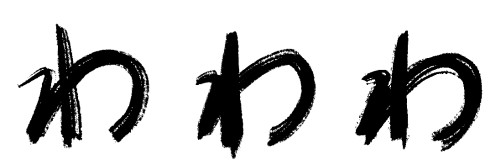狩人たちに助けられたという作り話は、案外すんなりと本部の人間に受け入れてもらえた。
コンサーン本部の出入口まで、狩人の少女がついてきてくれたからだろうか。それともティーガンが、狩人たちからもらった色鮮やかな刺繍が施してあるポンチョと、キツネの顔が付いている毛皮のマフラーを着用していたからだろうか。
できれば、前者であって欲しいとティーガンは願った。
ティーガンは医務室で2日ほど休んだ後、ほぼ1週間ぶりに仕事に復帰した。
まだ傷は痛むが、利き腕ではなかったので仕事に支障は無いだろうと判断したのだった。
久しぶりにラボに向かうと、ティーガンを心配していた同僚たちがわらわらと集まってきて、怪我は大丈夫かとか無理はするなとか、ひと通り気遣う言葉をかけてくれた。中には本当に死んだんじゃないかと思っていた人も居て、涙ぐみながら、よかった、生きててよかった、と声をかけてくれた。
ケミコ・カンパニーに所属する職員たちの中でも、ケミコ・コントラに属さない人は、つい敵のように思ってしまうこともあるが、多くの人はコンサーンの思想に疑問を抱かないだけで別に悪い人たちではない。
ティーガンは声をかけてくれたひとりひとりに礼を言い、心の中でこのラボは自分の居場所のひとつなのだと実感できたことにも感謝した。
敵とか、味方とか関係なく、自分はこのラボの一員なのだ。
なぜか、そう思えたことが無性に嬉しかった。
同僚たちへの挨拶が済んだころ、ティーガンは大きなため息をついた。
期待していなかったはずだけど、実際想像通りになるとどこか寂しい気持ちになる。
「エルロは?」
ラボのメンバーのほとんどがティーガンを囲んでいるが、そこによく知る人物の顔は無く、ティーガンはキョロキョロと辺りを見渡しながら尋ねた。
「資料室。見たい論文があるって朝からこもってるよ」
よくエルロと喫煙所で休憩している同僚が、呆れた様子で答えた。エルロの数少ない、人付き合いをしている同僚のひとりだ。
想像通りだったが、想像通りすぎて落胆した。
エルロに期待する方が間違っていたのかもしれない。
でも少しくらい心配して欲しかったというのが本音だ。
ティーガンはフゥと息を吐いて気持ちを切り替えると、1週間振りに自分のデスクに腰を下ろした。
「なあ、ティーガン」
正面のデスクに座る同僚が、パソコンの脇から顔を出して声をかけてきた。
「なあに、ここ1週間でデスクの配置が変わったりしたの」
「違う違う、そいつのことだよ」
同僚がティーガンの隣のデスクに視線を移した。今は誰も座っていないが、デスクの上は資料で散らかっている。エルロの席だ。
「エルロがどうかした?」
「それがさ…」
ティーガンは不思議そうに同僚を見た。
あまりエルロと関わりのない人が彼の話をするとき、大抵みんな深刻そうな顔をしているが、目の前の同僚は面白がっていることを隠そうともせずに、ニヤニヤと笑っている。
「あいつ、お前が居なくなった数日、食堂に行ってたんだよ。昼にわざわざ。きっとお前を探しに行ってたんだぜ」
「エルロが食堂に?ありえない」
「ほんとだって、何人も目撃してる」
ティーガンは目を丸くした。
エルロはいつも昼食を適当に済ませている。
昼はラボの休憩室でゼリー飲料やら携帯食やらを軽く食べて、あとの時間は仮眠を取るのが決まりだ。食堂に行くところなど見たことなかった。
ティーガンはエルロとは対照的で、毎日必ず食堂に向かい、事務や医療、アイボリー配給などの様々な部署の同期たちと会ってランチタイムを過ごすのが日課だった。
食生活を疎かにするエルロを、ティーガンは良く一緒に食堂へ行こうと誘っていたが、一度だって誘いに乗ってくれたことはない。
そんなエルロが、食堂に居た。
「何かの見間違いなんじゃないのかい?」
「見間違いなもんか。あいつは……」
そこまで言うと同僚は慌てて席に座り、仕事に取りかかり始めた。ラボの入り口を見ると、印刷した論文を脇に抱えているエルロが立っていた。
「おはよう」
ティーガンは隣のデスクまで来たエルロに向かって、いつも通り挨拶した。
「おう」
いつも通りの返事だ。
+++
ティーガンは寮の自室で、ひたすらノートに書き記していた。
ダーランド坂で出会ったグスターヴォのこと。
グスターヴォが教えてくれたイシの文化のこと。
麓の集落で触れ合った狩人たちのこと。
たくさんの異文化に触れて自分自身が感じたこと。
彼らと過ごしたのはたった数日と短い時間だったが、ティーガンが生涯築いてきた価値観を揺るがすには充分な時間だった。
いかに自分の視野が狭かったのかが良く分かったし、世界の広さを改めて感じたし、イシの人間だろうが狩人だろうがコンサーンの人間だろうが、みんな同じ人間なのだと実感した。
何にも変えがたい体験だった。
左腕の怪我はまだ痛むが、この怪我のおかげで貴重な体験ができたと思えば、全く苦ではなかった。
次は何を書こうと悩んでいると、突然ノックの音が耳に入ってきた。
「はい、今開けます!」
ティーガンは慌ててノートを小さな薄い箱に入れて鍵をかけると、ベッドの下の収納ボックスを開けて、服と服の間に仕舞い込んだ。
音を立てないよう静かに収納ボックスを閉じると、急いで扉を開いた。
「よ、元気か」
「エルロ!どうしたんだい」
上司かと身構えていたティーガンは、よく知る見慣れた顔を見て静かに安堵したが、安心したのは一瞬で、すぐに怪訝な顔をしてみせた。
「君が私の部屋を訪ねるなんて、初めてじゃない? 一体どんな風の吹き回しかな?」
エルロは特に返事もせず、右手に持っていたふたつの瓶をティーガンの視界に入るよう持ち上げた。
ひとつは炭酸水の瓶。
もうひとつはビールだ。
「あ! エルロ最高!」
ころっと表情を変えたティーガンを見て、エルロは苦笑した。
「現金なやつ」
「好きなだけ言えばいいよ。傷もまだ痛むし、飲みに行くのは控えようと思ってたけど、やっぱり飲みたいなあって思ってたところだったんだ。さあ、入って」
ティーガンはエルロを自室に通すと、机の引き出しから栓抜きを取り出してエルロに手渡した。
「開けてよ、まだ傷が傷むんだ」
「はいはい」
そう返したエルロは、栓抜きと瓶をそのままテーブルの上に置いてティーガンをまっすぐ見つめた。
「傷、見せてみろ」
「えっ?」
「傷を見せろって言ってるんだ」
「ちょっと、君は、いや、えっと」
ティーガンは睨むようにエルロを見た。
「これ、セクハラとして訴えても許されるよね?」
「はあ?あのな、俺は……」
そこまで言うと、エルロは不服げに黙り込んだ。面倒だと思うとすぐ口をつぐむ、エルロの悪い癖だ。
静かにしているけれど、文句を言いたげな表情が顔にしっかりと張り付いている。
文句を言いたいのはこちらなのに、とティーガンはため息をついた。
「部屋に来たのは傷を見るため?」
ティーガンがエルロに問いかけるが、むすっとした顔のまま口を開こうとはしなかった。
「エルロ、コミュニケーションを放棄するのはやめて。私の部屋に来たのは君だ。君の何かの目的のために私と会話を始めたのなら、ちゃんと責任を果たしてよ。無責任すぎる」
エルロはしばらく黙っていたが、ティーガンの一歩も譲らない強い意志を感じたのか、頭を掻きながら口を開いた。
「傷を見るのは、ついでだ。誰にやられたのか知りたかった」
「誰って?」
「報告じゃ山羊に襲われて崖に落ちたとかなんとか書いてあったけど、本当じゃないんだろ? 何に襲われたんだ? お前に怪我させたのはどこのどいつだ」
「いや、その…」
「よくそんな適当な話が通ったな。やったのはコンサーン兵か? それとも全く関係ないやつ?」
「エルロ」
「上層部があやしいと思ってるんだ。お前がいなくなったとき食堂で秘書たちの話を聞いてたら、レジスタンスが潜んでるだのどうの言ってたんだよ。暗殺とかそっち方面の話だったから俺たちじゃないと思うが、もしかしたら違う組織と間違われて…」
「聞いて!エルロ!」
ティーガンが叫ぶように名前を呼ぶと、エルロは動きを止めた。
「山羊に襲われて崖から落ちたっていうのは本当のこと! ありえないくらい全身痣だらけだし、左腕の傷は転がり落ちてる途中、山の剣っていう鋭い植物に引っ掛けちゃったの!
っていうか君、食堂に行ったっていうから、私を探しに行ってくれてたのかと思ってたのに、情報収集のためだったんだね!」
自分の失態をわざわざ正しく訂正することがこんなにも恥ずかしいとは思わなかった。
ティーガンは羞恥心と、エルロへの若干の怒りで顔を赤くした。
当のエルロは、もう興味をなくしたのか、へえ、とか、ああそうなんだ、とか、ぱっとしない返事をボソボソと呟いただけだった。
「でも、報告が全部事実ってわけじゃないんだろ?」
変なところで勘のいいエルロが、すかさず尋ねた。本当に直感だけで聞いているのか、それとも独自に調査したことを照らし合わせた上で聞いているのかは分からない。
「さすがエルロだね。その通りだよ。後でケミコ・コントラのみんなにも情報を共有しようと思ってたんだ」
ティーガンはグスターヴォの名前や生い立ちは伏せながら、イシの一族の文化や技術について話した。
ケミコ・コントラの目標である、アイボリー以外の活用可能なエネルギーの発見。イシの人たちと手を組めば、今よりずっと現実的な方針が決められるかもしれない。
「なあ、ティーガン。あまりにも話が出来すぎてないか?」
ティーガンの身に起こったことを黙って聞いていたエルロは、ひと通り話終わったあと、静かに口を開いた。
「海賊っていえば、今週だってコンサーン兵とぶつかってた。コンサーンを目の敵にしててもおかしくないだろ。お前、いいように利用されてるかもしれないぞ」
エルロの言うことも分かる。
コンサーンの人間の多くが、海賊を一目見たら怖がるように、きっと逆だって同じように怖がっているに違いない。
ティーガンに恩を売って、利用しようとしているのではないかと考えるのは、当たり前なのかもしれない。
しかしティーガンはどうしても、グスターヴォや狩人たちが自分を利用しようと考えているとは思えなかった。
「君の言いたいことも分かるけど、私はそう思わないんだ。私を介してコンサーンに見つかる危険性があったのに、私を助けてくれた」
「それが怪しいんだよ。何か裏がありそうだ」
「彼らは善意だけで私を助けてくれたんだよ!」
「数日一緒に居ただけで内面まで理解できるもんか」
ティーガンは、ふとグスターヴォの言葉を思い出した。人間は知らないものが怖いのだと。
エルロもきっと、海賊という正体の分からない相手に恐怖しているのかもしれない。
どうにか説得して、イシの人も狩人も敵ではないと分かってもらわないと。
そう考えていると、エルロが無表情のままティーガンに言い放った。
「お前、なんか変だ」
冷たく、どんな感情も示さない顔が、まっすぐこちらを見ている。
「……ちょっと違うけど、あれなんじゃないのか。なんだっけ、なんとか症候群って。極限状態の中で人に親切にしてもらったから、好意を持ってるんだ」
ティーガンの眉がぴくりと動いた。
「……なんだって?」
「普段のお前なら、もう少し冷静に考えられるだろ。海賊がコンサーン側をどう思ってるかなんて分かりきってるじゃないか」
「そんなことない! それに海賊じゃなくて、イシの人たちだ。私たちはあまりにも彼らを知らなさすぎるだけなんだよ」
「お前のその肩入れ具合が変なんだって言ってるんだ」
どうして分かってくれないんだ。
グスターヴォのことを話せば分かってくれるかもしれないが、ケミコ・コントラの仲間にも彼のことは話さないと約束した。
命の恩人であるグスターヴォを裏切る真似はしたくなかった。
「ティーガン、目を覚ませ! お前は利用されてるかもしれないんだぞ」
そのエルロの言葉で、ティーガンの胸にぐちゃぐちゃと渦巻いていた、もどかしさややるせなさが途端に弾けた。
「エルロ、部屋から出ていって!」
座っていた椅子を倒す勢いで立ち上がると、ティーガンは部屋の扉を指差した。
さすがのエルロも驚いた顔をして、ぽかんと口を開けてこちらを見ている。
「君の言いたいことは分かるよ! 君はいつだって冷静だし、客観的に物事を見れる。だから君の考え方は間違ってるとは思わない!」
「落ち着けって……」
「私は君のそういう素直な姿勢を評価してるし、仕事をする上で言葉を飾らない君の意見はとても貴重だと思ってる…! でも今の私は、君の素直さと冷静さに耐えられない!」
椅子に座らせようとするエルロを無視してティーガンは叫ぶように話を続けた。
とてつもなく怒っているようで、しかし今にも泣きそうな表情をしているティーガンの顔を見て、エルロは静かに困惑した。
「私は、本当は……!」
ティーガンは少し言葉に詰まった。
止めどなく溢れてくる言葉に、ティーガン自身も困惑していたからだ。
「本当は、嬉しかったんだ。君が食堂に向かったと聞いたときも、今こうして部屋を訪ねてくれたことも……! いつも何にも興味がなさそうなエルロが、私の心配をしてくれたんだってね。でも違った、君は私なんか見ていないんだもの! ティーガンという形をしている情報源にしか興味がない! 君はいつも通りで、労いの言葉ひとつだってかけちゃくれない! 頭じゃ分かってるんだよ、君はいつだってそういう人だったって! いつもなら、ああエルロはそういう感じだよねって流せるけど、今は無理なんだ!」
ティーガンの瞳から、ぼろぼろと涙が溢れた。
「分かる? 私、死ぬところだったんだよ!? 死ぬって思ったんだ! 怪我をして動けなくて、生きたまま猛禽についばまれるところだった! 夜には狼や狐にかじられて、山のいろんなところに私だったものが散乱して、そうなっててもおかしくなかった! 彼らのおかげで、今、私はここにいるんだよ! 本当に恐ろしかった…! 彼らだけが心の支えだったんだ!
君の気持ちは分かる、分かるから、彼らを疑うならこの部屋の外に出てからにしてくれ!」
ティーガンは、込み上げてくるものすべてを吐き出した。
涙が頬を伝って首元を濡らしていたが、拭うこともせず、鋭い眼差しでエルロを見つめていた。
「……分かった」
しばらく沈黙したあと、エルロは先程と変わらない様子でひとこと言い、そのまま扉に向かった。
ドアノブに手をかけようと右手を伸ばしたが、途中で動きを止め、落ち着かない様子で視線を上下に動かし、ドアを見つめたままティーガンに話しかけた。
「……最初、食堂に向かったのは、お前を探しに行くためだった。連絡が来てないだけで、本部にもう戻ってると思ったんだ。食堂が想像よりはるかにデカくて途方に暮れてたとき、秘書たちの話し声が聞こえて…」
エルロは頭を掻いた。
「ああ、違うな、えっと。悪かった。俺は話す順番を間違えた」
そう言うと、エルロは後ろを振り返り、泣いて目を真っ赤に腫らしたティーガンを見た。
「まず、こう言うべきだった。無事で、何よりだ。いや、怪我はしてるけど、生きてて、よかった。その、信じてもらえないかもしれないけど、心配してたんだ、これでも」
変なの。
ティーガンは思った。
エルロがティーガンに対して嘘をついたことなんて、ほとんどなかった。
エルロは、ずるい。
信じるしかないじゃないか。
「えっと、じゃあ、また明日」
「待って」
慌てて部屋を出ようとするエルロの背中に向かって、ティーガンは声をかけた。
「ごめん、私も取り乱してた。戻ってきてくれる? 瓶を開けて欲しいな」
「……いいのか?」
「うん…」
ティーガンの前まで戻ってきたエルロは、テーブルの上の瓶の栓を取ると、ビールをティーガンに手渡した。
「ありがとう……」
「…乾杯」
エルロは持っている炭酸水の瓶を、ティーガンのビール瓶に軽く当てて呟いた。
飲みたかった念願のビールは、なんだか味気なく感じて、なぜか、あんなに不味くて不味くて仕方なかった山羊のミルクが、急に飲みたくてたまらなくなった。
+++
グスターヴォは目を凝らして、目の前の男のたくましい腕を眺めていた。
「適当に刺せばいいものを」
目の前の男が言った。
「あのですね、アッシュ。人間は体中に血管がありますけど、この注射器で採血するには太い血管にちゃんと刺さないとうまく採血できないんですよ」
大きなため息をつきながらグスターヴォは返した。
超越者であるアッシュの血管には、白いアイボリーが流れている。
彼の血管を探すのは至難の業で、採血を行うときは普段の倍以上の時間を要してしまう。
「今日は機嫌がいいな、グスターヴォ」
ようやく見つけた血管に針を刺していると、アッシュがグスターヴォの顔を見て、珍しそうに言った。
グスターヴォは穏やかで優しい男だが、フラットな状態以外の姿をあまり見せることはない。いつも落ち着いていて、慌てることも、怒ることも、喜ぶことさえしないように思えた。
そんなグスターヴォが、なんとなく心躍らせている気がして、アッシュは言い表せない嬉しさを覚えた。
「そう見えます? 良いことがあったんですよ。ちょっとだけね」
採血を終えると、グスターヴォは注射器に入っているアイボリーを小瓶に詰め替えた。
これを持って、薬や食料を交換しに狩人たちの集落に向かうのだ。
「いつもすみませんね。助かりますよ」
「なに、助けてもらっているのは私の方だ」
「まあこれも共生関係ってやつですか。そうだ、これ、今回の薬です。ちょっと少ないですけど、もう春になりましたし、薬草もこれからたくさん生えると思うので、次はもっと持ってこれますからこれで我慢してください」
グスターヴォはリュックから調合した薬を取り出すと、アッシュに手渡した。
「効き目が悪くなったらすぐ言ってくださいね。他のを試してみるので」
「ああ…。いつもありがとう」
「いいんですよ」
アッシュの元を訪れると、彼はいつも申し訳なさそうな顔をした。
グスターヴォは、アイボリーをもらえるのはとても助かるからそのお返しだと言ってこまめに来てくれているが、それ以上の働きをしてくれていると思えて仕方がない。
「すごく、かっこいい人に出会ったんですよ」
採血を終えて、粗末なテーブルと椅子でお茶会をしていると、グスターヴォが楽しそうに話し始めた。
「正義感が強くて、ガッツがあって、それにすごく、綺麗で…」
「ほお、それは…」
「ああっと、今のは無しで」
アッシュがにやりと笑って、前屈みになってグスターヴォを覗き込んだ。
この人、意外と色恋話が好きなのか、とグスターヴォは心の中で苦笑した。
「そういうんじゃないですよ。ただ、かっこいいなって思ったんです」
怪我を負っても、挫けない強い眼差し。
イシの人間や狩人たちを受け入れる寛容さ。
人間としての純粋な強さを感じさせる人だった。
「…もう少し、その話をしてくれないか。時間に余裕があるならだが」
アッシュが座る位置を直しながら、グスターヴォに笑いかけた。
「ええ、良いですよ。時間はいっぱいあるので」
微笑み返したグスターヴォは、リュックからボールペンを一本取り出した。
「どこから話せばいいかな…」
コバルトブルーのキャップが被せてある、綺麗なボールペンを指で少しなぞりながら呟いた。
かっこよくて美しい人がくれたボールペン。
彼女は制服のポケットに入れていた愛用のボールペンを、グスターヴォにプレゼントしてくれたのだった。
渡せるものがこれくらいしかないけど、と苦笑していたが、グスターヴォは、こういうのは気持ちが大切なんだ、と丁寧に受け取った。
「そうですね、まずは山羊の話でも…」
そう言いながら、グスターヴォは山羊のミルクを飲んだティーガンの顔を急に思い出してしまい、ひとりで突然笑い出してしまった。
何も分からないアッシュは、目の前で笑い転げているグスターヴォを茫然と眺めていた。